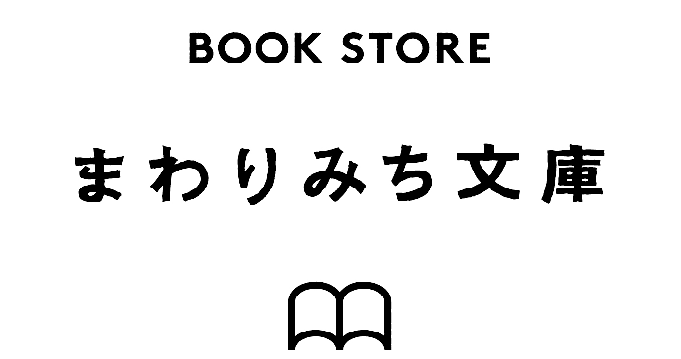-

黒人と白人の世界史
¥2,970
著者:オレリア・ミシェル 訳者:児玉しおり 解説:中村隆之 発行元:明石書店 376ページ 195mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ヨーロッパ人は、アフリカ人を奴隷にしたために人種主義者になった」。本書は、大西洋奴隷貿易、奴隷制、植民地主義とともに、「人種」がどのように生み出され、正当化されていったのかを歴史的に解明する。ル・モンド紙が「まるで小説のように読める」と評す、人種の歴史の新たな基本書。 【目次】 序文 イントロダクション―ニグロと白人、言葉の歴史 第Ⅰ部 奴隷制と帝国 第1章 奴隷という制度 制度としての奴隷 奴隷制の社会的意味 第2章 サハラ砂漠以南のアフリカにおける奴隷制 古代以来のナイル川北部とサハラ砂漠の商業上の地位 アラブ世界の拡大と奴隷売買ルートの発展 西アフリカにおける奴隷交易国の形成 奴隷制の歴史的重み 第3章 ヨーロッパのダイナミズム ヨーロッパ建設における一つのパラドックス 一五世紀の南大西洋におけるポルトガル人とカスティーリャ人 大西洋の植民地化のメカニズム/交易の支配 大西洋の農園 第4章 アメリカの発見 アメリカにおける事業 インディアンの奴隷化 “ニグロ”貿易 結論 奇妙な帝国 第Ⅱ部 ニグロの時代 第5章 ニグロのプランテーション(一六二〇~一七一〇年) プランテーション―ブラジルからカリブ海の島々まで ブラジルからカリブ海の島々に向かったオランダ人 黒人奴隷貿易国 一八世紀への変わり目における植民地拡大 第6章 不可能な社会(一七一〇~一七五〇年) 捕獲という奴隷生産 拉致からプランテーションまでの「長い旅」 プランテーションと良い農園主 不安定な秩序 ニグロという虚構 第7章 危機に向かって(一七五〇~一七九四年) 経済発展の危機――入植と奴隷貿易の対立 フランスにおけるパラダイムの変化 奴隷制と奴隷貿易への異議 人種隔離主義、“血の純潔”および植民地の階級化 パリとサン゠ドマングの間の革命危機 結論 ニグロと暴力 第Ⅲ部 白人の支配 第8章 ドミ・ネーション(一七九〇~一八三〇年) 徴用された国家(一七九四~一八一五年) アメリカ合衆国の奴隷制維持とフランスの奴隷制復活/解放奴隷をどうするか 植民地の転換とイデオロギーの急変(一八一五~一八三〇年) 奴隷制擁護派、リベラル派、一八二〇年の危機/奴隷制廃止主義と新たな支配/所有者の国家 第9章 奴隷制から人種へ(一八三〇~一八五〇年) 奴隷制からの脱却(一八三〇~一八四〇年) 人種の科学(一八四〇~一八五〇年) 「ニグロの虚構」から白人の虚構へ 第10章 新たな支配(一八五〇~一八八五年) 奴隷制なき植民地労働の再編(一八五〇~一八七五年) アメリカにおける社会関係の転換の難しさ/アフリカにおける新たな生産計画/白人の科学 ベルリン会議(一八八五年) 第11章 人種の統治(一八八五~一九一五年) ネオプランテーション(一八八五~一九一〇年) 人種政策 白人優位の物語を強化する 国家の退廃と純粋さの間にある国家身体 第12章 妄想、悪魔、民主主義(一九二〇~一九五〇年) 第一次世界大戦後の人口調整 都市――人種と近代化/植民地 一九三〇年代――人種主義者という群衆 一九三〇年代に入る時期の二つの人種危機/否認と熱狂の間で 結論 人種の策略 「ニグロの虚構」 「白人の虚構」 人種を終わらせるために 謝辞 解説 中村隆之 原注 参考文献
-

反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー
¥4,180
SOLD OUT
著者:ジェームズ・C・スコット 訳者:立木勝 発行元:みすず書房 296ぺージ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ある感覚が要求してくる——わたしたちが定住し、穀物を栽培し、家畜を育てながら、現在国家とよんでいる新奇な制度によって支配される「臣民」となった経緯を知るために、深層史(ディープ・ヒストリー)を探れ、と…」 ティグリス=ユーフラテス川の流域に国家が生まれたのが、作物栽培と定住が始まってから4000年以上もあとだったのはなぜだろうか? 著者は「ホモ・サピエンスは待ちかねたように腰を落ち着けて永住し、数十万年におよぶ移動と周期的転居の生活を喜んで終わらせた」のではないと論じる。 キーワードは動植物、人間の〈飼い馴らし〉だ。それは「動植物の遺伝子構造と形態を変えてしまった。非常に人工的な環境が生まれ、そこにダーウィン的な選択圧が働いて、新しい適応が進んだ…人類もまた狭い空間への閉じこめによって、過密状態によって、身体活動や社会組織のパターンの変化によって、飼い馴らされてきた」 最初期の国家で非エリート層にのしかかった負担とは? 国家形成における穀物の役割とは? 農業国家による強制の手法と、その脆弱さとは? 考古学、人類学などの最新成果をもとに、壮大な仮説を提示する。 【目次】 はじめに 序章 ほころびだらけの物語——わたしの知らなかったこと 国家と文明の物語のパラドックス/国家の正しい位置づけ/手短な行程表 1 火と植物と動物と……そしてわたしたちの飼い馴らし 火/集中と定住——湿地仮説/湿地と定住/なぜ無視されてきたのか/ギャップに注目する/そもそもなぜ植えるのか 2 世界の景観修正——ドムス複合体 新石器時代の植え付けから百花繚乱へ——耕作の影響/進化のモジュールとしてのドムス/狩猟民の獲物から農民の囲い物へ/人間の類似点に関する推論/わたしたちの家畜化 3 動物原性感染症——病理学のパーフェクトストーム 苦役とその歴史/後期新石器時代複数種再定住キャンプ——病理学のパーフェクトストーム/多産と人口に関する注釈 4 初期国家の農業生態系 国家作りの農業地理/穀物が国家を作る/壁が国家を作る——防御と閉じこめ/文字が国家を作る——記録と識字力 5 人口の管理——束縛と戦争 国家と奴隷制/メソポタミアの奴隷制と束縛/エジプトと中国/「人的資源」戦略としての奴隷制/略奪的資本主義と国家建設/メソポタミアの奴隷制および束縛の特殊性/飼い馴らしと重労働と奴隷制に関する推測的覚書 6 初期国家の脆弱さ——分解としての崩壊 初期国家の罹患率——急性疾患と慢性疾患/病気——過度の定住、移動、国家/環境破壊——森林破壊と塩類化/政体の消滅——戦争とコアの搾取/崩壊万歳 7 野蛮人の黄金時代 文明とその野蛮な周辺部/野蛮人の地理、野蛮人の生態系/略奪/交易ルートと課税可能な穀物コア/闇の双生児/黄金時代だったのか? 索引/原注/参考文献
-

世にも奇妙な人体実験の歴史(文春文庫)
¥1,133
SOLD OUT
著者:トレヴァー・ノートン 訳者:赤根洋子 発行元:文藝春秋 464ページ 文庫判 148mm × 128mm *********************** 発行元紹介文より *********************** 性病、コレラ、寄生虫……人類の危機を救った偉大な科学者たちは、己の身を犠牲にして、果敢すぎる人体実験に挑んでいた! 自身も科学者である著者は、自らの理論を信じて自分の肉体で危険な実験を行い、今日の安全な医療や便利な乗り物の礎を築いた科学者たちのエピソードを、ユーモアたっぷりに紹介します。 解剖学の祖である十八世紀の医師ジョン・ハンターは、淋病患者の膿を自分の性器に塗りつけて淋病と梅毒の感染経路を検証しました。十九世紀の医師ウィリアム・マレルは、ニトログリセリンを舐めて昏倒しそうになりますが、血管拡張剤に似た効果があると直感。自己投与を続けて、狭心症の治療薬として確立するもとになりました。二十世紀、ジャック・ホールデンは潜水方法を確立するために自ら加圧室で急激な加圧・減圧の実験を繰り返し、鼓膜は破れ、歯の詰め物が爆発したといいます。 その他にも放射能、麻酔薬、コレラ、ペストなどの危険性の解明に、自らの肉体で挑んだマッド・サイエンティストたちの奇想天外な物語が満載。その勇気と無茶さに抱腹絶倒するうち、彼らの真の科学精神に目を開かされる好著です。
-

市民的抵抗 非暴力が社会を変える
¥3,080
著者:エリカ・チェノウェス 訳者:小林綾子 発行元:白水社 402ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 革命をもたらす3.5%の力 「ある国の人口の3.5%が非暴力で立ち上がれば、社会は変わる」。 この「3.5%ルール」で一躍有名になったのが本書の著者で、ハーバード大学ケネディ行政大学院教授のエリカ・チェノウェスだ。 本書は、この「3.5%ルール」をはじめ、市民的抵抗の歴史とその可能性を探る試みである。どこか弱々しく、悲壮なイメージがつきまとう非暴力抵抗だが、実証的にアプローチしてみると、その印象は一変する。 過去120年間に発生した627の革命運動の成功率を見てみよう。暴力革命と非暴力革命とではどちらが成功したのだろうか? 1900年から2019年の間、非暴力革命は50%以上が成功した一方で、暴力革命はわずか26%の成功にとどまる。 これは驚くべき数字である。なぜなら、暴力行為は強力で効果的であるのに対して、非暴力は弱々しく効果も乏しいという一般的な見方を覆す数字だからだ。 他方、この10年で非暴力抵抗の成功率は下落傾向にある。「スマートな独裁」とともに、運動がデモや抗議に過度に依存していることが背景にある。 社会を変革するための新たな方法論の本邦初訳。
-

戦争は女の顔をしていない(岩波現代文庫)
¥1,540
SOLD OUT
著者:スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 訳者:三浦みどり 発行元:岩波書店 506ページ 文庫判 148mm × 105mm ~出版社紹介文より~ ソ連では第二次世界大戦で100万人をこえる女性が従軍し、看護婦や軍医としてのみならず兵士として武器を手にして戦った。しかし戦後は世間から白い目で見られ、みずからの戦争体験をひた隠しにしなければならなかった――。 500人以上の従軍女性から聞き取りをおこない戦争の真実を明らかにした、ノーベル文学賞作家の主著。(解説=澤地久枝) アレクシエーヴィチはこれまで、ソ連の一般市民に対する綿密なインタビューを重ねることによって、大文字の歴史からはこぼれ落ちてしまう市民の生の声をすくいあげ、世界中に衝撃を与えてきました。とりわけチェルノブイリの事故処理を担った一般人など、ともすれば国家権力に圧殺されてしまいがちな弱者の声に耳を傾けるその姿勢は、社会性および人道性の観点から高く評価され、また、市井のさまざまな証言を集め、多声的なドキュメンタリー文学作品に仕上げるその創作手法は、芸術性の点でもきわめて高い到達を示しているとして、これまで数々の文学賞が授与されてきました。それが認められて2015年ノーベル文学賞を受賞しました。 その創作スタイルがドキュメンタリーの手法であるため、文学賞として認められるか懸念されましたが、スウェーデン・アカデミーは「私たちの時代の苦悩と勇気への記念の碑」と称え、「文学の新しいジャンルを案出した」と評しました。 本作はアレクシエーヴィチが1984年に発表した最初の作品です。雑誌記者だった30歳代の彼女が1978年から取材を開始して、500人を超える女性から聞き取りをしました.完成後2年間は出版を許されず、ペレストロイカ後に出されました。ベラルーシの独裁者ルカシェンコ大統領は彼女を「外国で著書を出版し祖国を中傷して金をもらっている」と非難し、長い間ベラルーシでは出版禁止にされてきました。 ソ連では第二次世界大戦で100万人をこえる女性が従軍し、看護婦や軍医としてのみならず兵士として武器を手にして戦ったのですが、しかし戦後は世間から白い目で見られ、みずからの戦争体験をひた隠しにしなければなりませんでした。英雄としてではなく生身の人間としての従軍女性(パルチザンや抵抗運動に参加した女性をふくむ)に本書が初めて光をあてたのです。 ベラルーシのドキュメンタリー作家アレーシ・アダモーヴィチいわく, 「戦争は女の顔をしていない.しかし,この戦争で我々の母親たちの顔ほど厳しく,すさまじく,また美しい顔として記憶されたものはなかった」
-

夜と霧 新版
¥1,870
著者:ヴィクトール・E・フランクル 訳者:池田香代子 発行元:みすず書房 184ページ 193mm ×135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 〈わたしたちは、おそらくこれまでのどの時代の人間も知らなかった「人間」を知った。では、この人間とはなにものか。人間とは、人間とはなにかをつねに決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りのことばを口にする存在でもあるのだ〉 「言語を絶する感動」と評され、人間の偉大と悲惨をあますところなく描いた本書は、日本をはじめ世界的なロングセラーとして600万を超える読者に読みつがれ、現在にいたっている。原著の初版は1947年、日本語版の初版は1956年。その後著者は、1977年に新たに手を加えた改訂版を出版した。 世代を超えて読みつがれたいとの願いから生まれたこの新版は、原著1977年版にもとづき、新しく翻訳したものである。 私とは、私たちの住む社会とは、歴史とは、そして人間とは何か。20世紀を代表する作品を、ここに新たにお送りする。 【目次】 心理学者、強制収容所を体験する 知られざる強制収容所/上からの選抜と下からの選抜/被収容者119104の報告——心理学的試み 第一段階 収容 アウシュヴィッツ駅/最初の選別/消毒/人に残されたもの——裸の存在/最初の反応/「鉄条網に走る」? 第二段階 収容所生活 感動の消滅(アパシー)/苦痛/愚弄という伴奏/被収容者の夢/飢え/性的なことがら/非情ということ/政治と宗教/降霊術/内面への逃避/もはやなにも残されていなくても/壕のなかの瞑想/灰色の朝のモノローグ/収容所の芸術/収容所のユーモア/刑務所の囚人への羨望/なにかを回避するという幸運/発疹チフス収容所に行く?/孤独への渇望/運命のたわむれ/遺言の暗記/脱走計画/いらだち/精神の自由/運命——賜物/暫定的存在を分析する/教育者スピノザ/生きる意味を問う/苦しむことはなにかをなしとげること/なにかが待つ/時機にかなった言葉/医師、魂を教導する/収容所監視者の心理 第三段階 収容所から解放されて 放免 『夜と霧』と私——旧版訳者のことば(霜山徳爾) 訳者あとがき *********************** 店主コメント *********************** アウシュヴィッツ収容所を生還した心理学者による収容所の体験記。 その克明な記録は、絶望的な状況の中で人を生かすものが何なのかを朧げながらも伝えてくれます。それは真理に近いようなものだと思いますが、この本を2回読んだ私も「何か精神的なもの」としか言いようがありません。けれども、極限状態を生き抜いた人の言葉はやはり重みがあります。読後は確かな手ごたえや感触を与えてくれる紛れもない名著。 ちなみに、ハンセン病患者の姿をとおして「生きがい」を考察した神谷美恵子『生きがいについて』という本があります。人を生かすものについて考察し書かれているという点で、『夜と霧』と共鳴する部分があると思います。ぜひ合わせて読んでみてほしいです。
-

澤田教一 故郷と戦場
¥4,950
SOLD OUT
著者:澤田教一 発行元:羽鳥書店 296ページ 270mm × 210mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 青森・三沢に撮られた写真、世界中に配信された電送写真、前線からフィルムを送った封筒、従軍時に持ち歩いた手帖、原稿が掲載された新聞・雑誌、夫人への手紙、「ピュリツァー賞ポートフォリオ」全28点(初公開)など、貴重な資料とともに、澤田の34年の生涯をたどる。 図版327点 寄稿:生井英考、石川文洋 青森県立美術館「澤田教一:故郷と戦場展」公式写真集 【目次】 1936-61 青森 1961-65 東京 1965 ベトナム 1966-68 ベトナム 1968 ベトナム:フエ 1969 香港 1970 カンボジア