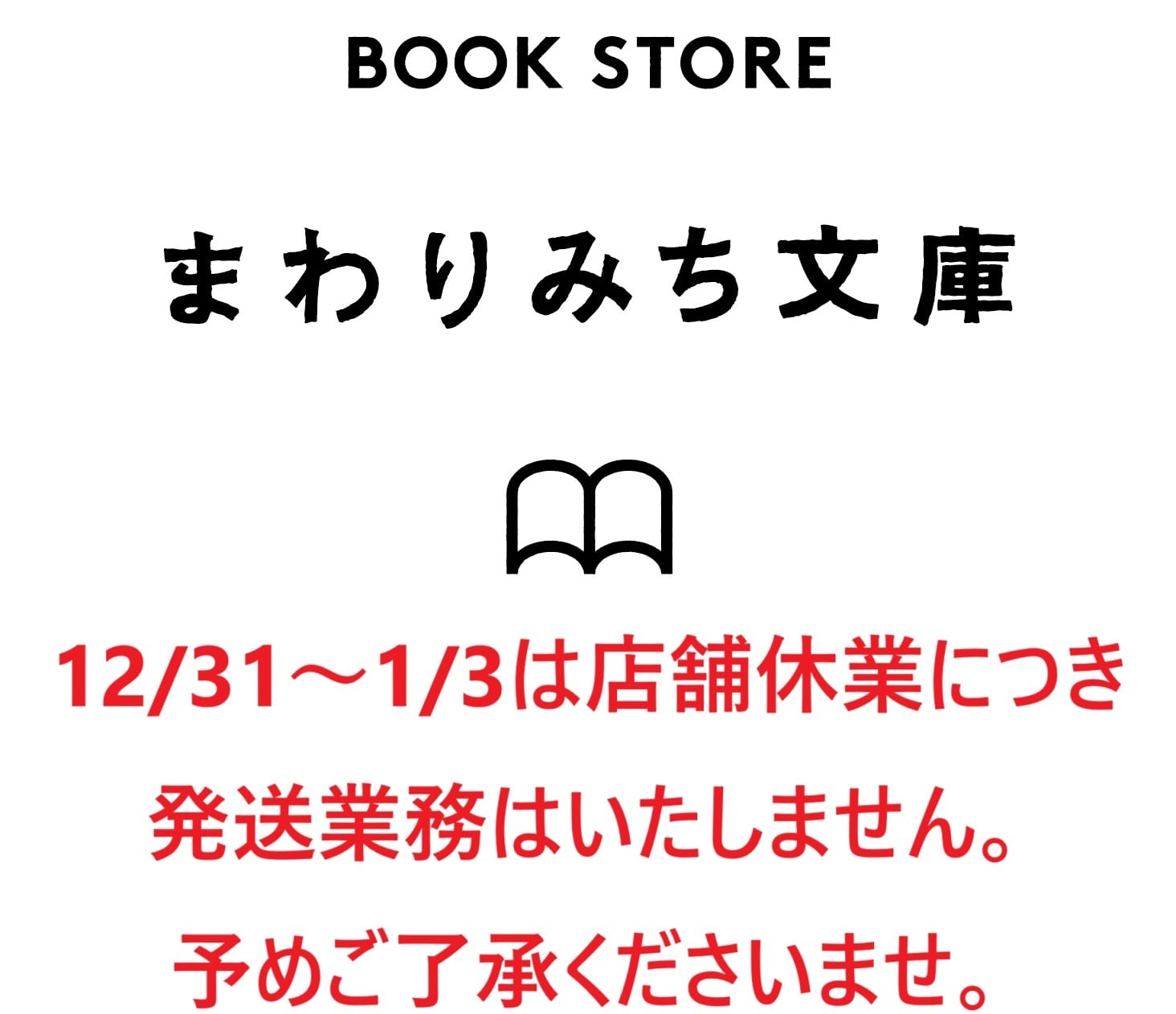-

1994-2024 ミルクマン斉藤レトロスペクティブ 京阪神エルマガジン社の映画評論集
¥3,200
SOLD OUT
著者:ミルクマン斉藤 発行元:京阪神エルマガジン 600ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 2024年1月に逝去した映画評家・ミルクマン斉藤。その活動のスタートは、1994年『Meets Regional』への寄稿だった。以降、30年に及ぶ『Meets』『SAVVY』『月刊誌LLmagazine』をはじめとする、京阪神エルマガジン社の媒体で執筆した膨大な量の原稿を書籍化。ミルクマン斉藤と深いかかわりを持つ執筆陣によるコラムも収録。不世出の映画評論家である斉藤氏の集大成として、また90年代以降の、映画文化の貴重な記録集となっている。 【目次】 はじめに Meets Regional 1994.1~1999.10 Meets Regional 2006.5~2011.11 Column. ♯1 試写室の闇の恐怖!午後にからまるアングラ魂/沢田眉香子 Meets Regional 2011.12~2023.4 Column. ♯2 好きなこと、で生きる。/安田謙一 Meets Regional 2023.5~2024.2 Column. ♯3 『最後の連載を担当して』日記。/松尾修平 SAVVY 1994.4~1998.4 SAVVY 2005.1~2007.3 Column. ♯4 ただ楽しかった、その感覚は鮮明に。/岡本仁 Column. ♯5 後世に伝えるべき最高の映画評論家。/小柳帝 SAVVY 2007.4~2010.10 SAVVY 2009.6~2017.5 Lmagazine 1997.5~1999.5 Lmagazine 1999.6~2000.12 Column. ♯6 もう一度「ミルクマ~ン」と呼びたくて。/辛島いづみ Lmagazine 2001.1~2007.6 Lmagazine 2007.7~2009.2 Column. ♯7 キャッチを付けるのは、私だって苦手だし、面倒だという話。/嶋津善之 Book and Mook 2005、2009 Lmaga.jp 2014.2~2023.9 Column. ♯8 でも、まだ言っている。/春岡勇二 The Long Goodbye ミルクマン斉藤と長いお別れ 超個人的9つの思い出話 あとがきにかえて 田中知之 Special thanks 編集部より/おわりに
-

新版 映画の構造分析
¥2,420
SOLD OUT
著者:内田樹 発行元:晶文社 332ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 映画に隠された驚くべき物語構造を読み解く、 スクリーンから学べる現代思想、精神分析、ジェンダー。 大幅増補の決定版映画論。 物語には構造があり、映画にも構造がある。そして映画の構造を知ることが、人間の欲望の構造を知ることにつながる……。『エイリアン』『大脱走』『裏窓』などハリウッド映画の名作を題材にした映画論にして、ラカンやフーコーなど現代思想の入門テキストとして高い評価を受けた旧版『映画の構造分析』に、『君たちはどう生きるか』『ドライブ・マイ・カー』『怪物』『福田村事件』など、近年の話題作を分析した論考を大幅増補した決定版映画論。〔2003年初版〕 【目次】 新版へのまえがき まえがき ■第1章 映画の構造分析 0 物語と構造 1 テクストとしての映画 2 欠性的徴候 3 抑圧と分析的知性 4 「トラウマ」の物語 ■第2章 「四人目の会席者」と「第四の壁」 ■第3章 アメリカン・ミソジニー──女性嫌悪の映画史 ■第4章 そして映画は続く 『ゴッドファーザー』と『北の国から』 『君たちはどう生きるか』をどう観るか 「父」からの離脱の方位──『1Q84』論 『ハナレイ・ベイ』のためのコメント 『ドライブ・マイ・カー』の独創性 『ノルウェイの森』の時代感覚 『ハウルの動く城』を観に行く 『怪物』について 『福田村事件』へのコメント 『愛の不時着』──男性目線と女性目線の交錯 『冬のソナタ』──予定調和的な宿命 『秋日和』──非婚は彼女たちの意思ではない 『精神0』──それに人間は抗うことができない 『演劇1』『演劇2』──演劇の平田オリザ、映画の想田和弘 『三島由紀夫VS東大全共闘』──政治の季節の予感 『プレシャス』──史上初の男性嫌悪映画 『バービー』──哲学的な映画 デヴィッド・リンチ追悼 オリジナル版のあとがき 新版のためのあとがき 解説 「お話を一つ思いつく」を巡って 春日武彦
-

女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選
¥1,980
著者:北村紗衣 発行元:書肆侃侃房 224ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「もうダメかも……」を「楽しく生きよう!」に変える、映画の力でサバイブするための100選 あのヒロインみたいになれたらいいな、私と同じだな、私とは違うけどステキだな……。 映画を見ることで、女性であること、少数派であること、自分自身でいることの楽しさに気づける。もっと楽しく生きる準備をするために、あなたを待っている映画がきっとある。 クラシックな名作から近年の話題作まで、労働問題、恋愛とセックス、フェミニズム、クィア、人種、民族など、多様な視点から厳選した100本の映画ガイド
-

映像のポエジア 刻印された時間(ちくま学芸文庫)
¥1,650
SOLD OUT
著者:アンドレイ・タルコフスキー 訳者:鴻英良 発行元:筑摩書房 416ページ 文庫判 148mm × 105mm *********************** 出版社紹介文より *********************** 『惑星ソラリス』『鏡』『ノスタルジア』『サクリファイス』……。 透徹した精神性と至高の映像美で、独自の映画世界を作り上げたタルコフスキー(1932-1986)。死去するまでの20年間、彼は映画をめぐる思索を膨大に書き残していた。内面へ深く沈潜しつつ、時に自作を、時にブレッソン、ベルイマン、黒澤ら外国人監督を論じていく。 本書は、訳者がタルコフスキー夫人ラリサ(1938-1998)から送られたタイプ原稿を基に訳出された、日本オリジナル版である(同時期に、ドイツ語版・英語版も出る。当時のソ連ではタルコフスキーは著作を公刊できなかった)。映画を超えて、芸術そのものに関心を持つすべての人に届けたい名著。 【目次】 序章 第1章 はじまり 第2章 芸術―理想への郷愁 第3章 刻印された時間 第4章 使命と宿命 第5章 映像について 第6章 作家は観客を探究する 第7章 芸術家の責任 第8章 『ノスタルジア』のあとで 第9章 『サクリファイス』 終章
-

ホラー映画の科学 悪夢を焚きつけるもの
¥2,750
SOLD OUT
著者:ニーナ・ネセス 訳者:五十嵐加奈子 発行元:フィルムアート社 352ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** ホラー映画を見るとき、私たちの脳・心・身体で何が起こっているのか? モンスター、暴力、トラウマ、音……さまざまな切り口から、脳科学や心理学で〈恐怖〉のしくみを解き明かす もっと眠れなくなること必至の、ホラー映画×科学の世界! 私たちはなぜ、ホラー映画という〝悪夢の燃料〟を求めるのか? 私たちの脳や身体はホラー映画の何に恐怖を感じ、どのように反応するのか? 本書では、科学コミュニケーターとして活動する著者が多彩なホラー映画を例に、人が恐怖を感じ、脅威に対処するメカニズムを紹介。脳科学・心理学・神経科学・生物学の知見から、〈恐怖〉のさまざまな側面を明らかにする。 登場する映画は、『サイコ』『エクソシスト』など古典的名作から、『ヘレディタリー/継承』『アス』『クワイエット・プレイス』など現代のヒット作まで約300本。サイコ、SF、スラッシャー、スプラッター、クリーチャー、オカルトなどのサブジャンルを縦横無尽に扱いながら、ホラー映画の歴史もおさらい。いかに映画における〈恐怖〉が作り出されてきたのか、そして私たち観客はいかにそれを受け取るのかに迫る。 各章には、ひとつの作品を掘り下げるコラムと、映画の製作者や研究者へのインタビューも収録。尽きることのないホラーの魅力を存分に楽しめること間違いなし。 【目次】 はじめに ホラーを定義する難しさ 第一章 恐怖を感じると、脳はこうなる 脅威 ジャンプスケア 【注目作品】『キャット・ピープル』(42/ジャック・ターナー監督) 嫌悪感 映画で見る恐怖 【注目作品】『ヘレディタリー/継承』(18/アリ・アスター監督) 【インタビュー】ジェイミー・カークパトリック(映画編集者) 第二章 ホラー映画の歴史 静かな恐怖 初期のホラー映画(1890年代頃‐1920年代初頭) 全盛には至らない時期(1920年代‐30年代) 原子力の登場(1940年代‐50年代) 他人という悪魔(1960年代) 暴力的な結末(1960年代後半‐70年代) 【注目作品】『暗闇にベルが鳴る』(74/ボブ・クラーク監督) スラッシャー、悪魔系パニック、ビデオ・ナスティ(1980年代) ホラー映画の……低迷?(1990年代) 新たなミレニアムに向けたホラー映画(2000年代) 現在のホラー映画と今後の展望(2010年代以降) 【インタビュー】アレクサンドラ・ウェスト(映画研究者) 第三章 モンスターの作り方 【注目作品】『遊星からの物体』(82/ジョン・カーペンター監督) 捕食者としてのモンスター 【注目作品】『エイリアン』(79/リドリー・スコット監督) 人間(または人間のような)モンスター 永遠のモンスター 第四章 耳からの恐怖 【注目作品】『クワイエット・プレイス』(18/ジョン・クラシンスキー監督) 不協和音 人の可聴域ぎりぎりの音 【注目作品】『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(99/ダニエル・マイリック、エドゥアルド・サンチェス監督) 叫び 【インタビュー】ローネン・ランダ(映画音楽作曲家) 第五章 恐怖が付きまとう理由 【注目作品】『ジョーズ』(75/スティーヴン・スピルバーグ監督) 人はどのように恐怖を抱きはじめるのか? 【注目作品】『鮮血の美学』(72/ウェス・クレイヴン監督) どうすれば恐怖心がなくなるか? 【インタビュー】メアリー・ベス・マッカンドリューズ(ホラー・ジャーナリスト)&テリー・メスナード(クリエイター) 第六章 暴力的メディアと暴力行為 【注目作品】『チャイルド・プレイ3』(91/ジャック・ベンダー監督) 誰か、子どもたちのことを考えてくれませんか? 感度の低下 ホラー映画はより暴力的になっているのか? 第七章 血、ゴア、ボディホラー 身体の内側からの暴力 身体の外側からの暴力 見えない場面 血みどろなほどいいのか? 【注目作品】『サスペリアPART2』(75/ダリオ・アルジェント監督) 目にまつわる恐怖 【インタビュー】ジョン・フォーセット(映画監督) 第八章 ホラーの変わらぬ魅力 万人のためのホラー ホラー愛は遺伝するのか? 刺激欲求 カタルシス説 恐怖に寄り添う 【インタビュー】アレクサンドラ・ヘラー=ニコラス(映画評論家) あとがき 謝辞 訳者あとがき
-
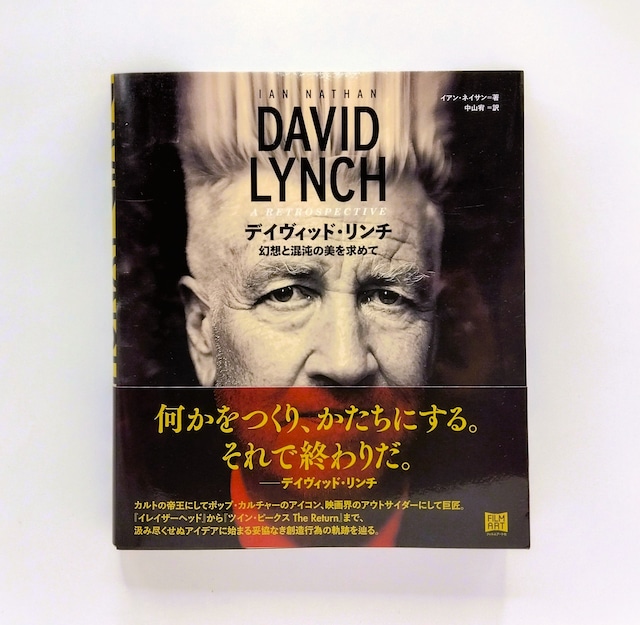
デイヴィッド・リンチ
¥3,520
SOLD OUT
著者:イアン・ネイサン 訳者:中山宥 発行元:フィルムアート社 310ページ 210mm × 183mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** アメリカ映画史上「最も過激で、強烈で、奇妙で、滑稽で、恐ろしく、深遠で、忘れがたい作品」を生み出したデイヴィッド・リンチ。 1960年代の実験的な短編作品や『イレイザーヘッド』、『エレファント・マン』、『ブルーベルベット』、『マルホランド・ドライブ』などの長編映画、そしてTVシリーズ『ツイン・ピークス』『ツイン・ピークス The Return』。 長年にわたり、リンチの作品は見る者を魅了し、挑発してきた。 本書は「リンチアン(Lynchian)」を理解するための探究書である。「リンチアン」とは「リンチの映画ならではのスタイル、感覚、雰囲気、物語の語り口、登場人物のタイプ、ジャンルのアレンジ、話しかた、風景、街、ユーモアとホラーの融合、現実というヴェールの向こう側への旅、心の奥底にある欲望の考察、リンチが故郷と呼ぶ国の奥深くへの探検」を意味する言葉だ。 中産階級の愛情深い両親のもとで幼少期を過ごし、ユーモア雑誌やボーイスカウトに夢中になったデイヴィッド・リンチは、やがて芸術家の道を志し、フィラデルフィアのペンシルヴェニア美術アカデミーへ入学する。のちに「腐敗し、衰退していて、奇妙に邪悪で、暴力的で、恐怖に満ちていた」と述懐するこの街で、リンチは自分のめざすべき道は「動く絵画」であると気づく――。 本書では、リンチの長編映画10本とTVシリーズ2本について詳しく解説するとともに、彼の生い立ちや多様で豊富な芸術や表現がどのように作品に影響を与えたのか、貴重な場面写真やオフショットとともに、「リンチアン」の謎に迫る。 自らの理想と想像力に従って作品を作り続け、映画のストーリーテリングの限界を押し広げてきた唯一無二の映画監督の本格評伝。 【目次】 イントロダクション 特定の都市への恐怖 悩ましく暗き物どもの夢 『イレイザーヘッド』の内幕 皮膚の下 『エレファント・マン』の驚くべき真実 迷える宇宙 『デューン/砂の惑星』の苦悩と驚異 わが家に勝る所なし 偉大なる倒錯 『ブルーベルベット』 大衆向けのマグリット 『ツイン・ピークス』のテレビ版と映画版の奇妙な事件 オズの国へひた走るエルヴィスとモンロー 『ワイルド・アット・ハート』の逃避行 イン・ザ・ループ 『ロスト・ハイウェイ』を解き明かす 芝刈り機の男 涙腺を刺激する『ストレイト・ストーリー』 気がつけば謎のなか 『マルホランド・ドライブ』の果てしない誘惑 超現実の旅 『インランド・エンパイア』と踊り明かす きみが好きなあのチューインガム、復活するってさ 『ツイン・ピークス』への待望の帰還 フィルモグラフィ 参考文献 謝辞
-

夢みる部屋
¥4,950
SOLD OUT
著者:デイヴィッド・リンチ/クリスティン・マッケナー 訳者:山形浩生 発行元:フィルムアート社 704ページ 210mm × 148mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 世界中で大反響! 名匠・デイヴィッド・リンチの自伝、待望の翻訳! 異能の映画監督デイヴィッド・リンチの創造的な人生を、リンチ自身の言葉と、身近な同僚、友人、家族の言葉の両面からひもといていく、 いまだかつてないユニークな自伝! 本書は、比類なきビジョンを追求し続けてきたデイヴィッド・リンチの、映画、アート、音楽その他さまざまな「創作人生」と、彼が直面してきた苦悩や葛藤も明かされる、リンチにとって初めての伝記と回想録を融合させる試みである。 共著者のクリスティン・マッケナによる評伝のセクションは、元妻、家族、友人、俳優、代理人、そして映画制作の多様な分野で協働する同僚たち、総勢100人以上の登場人物からなる驚くほど率直なインタビューによって、パーソナルな「人間・リンチ」を浮き彫りにする。リンチ自身の回想のセクションは、叙情的で親密、そして何事もタブーにすることなくすべてを赤裸々に語る──過激なユーモアももちろん忘れない──パーソナルな考察であり、リンチの美的感覚や人生哲学にあふれている。 最も謎に包まれた、最も独創的な一人の表現者の、 人生と心の中にアクセスする、すべてのリンチ信者必読の歴史的な一冊。 リンチ自身が全自作を語る決定版! 鮮烈なデビュー作『イレイザーヘッド』(1977)から、出世作『ブルーベルベット』(1986)、社会現象になったテレビシリーズ『ツインピークス』(1990-1991)、『ロスト・ハイウェイ』(1997)、そして最新作『ツイン・ピークス The Return(邦題:リミテッド・イベント・シリーズ)(2017)等々リンチの全映画作品、さらにはデビュー前の初期作品や、知る人ぞ知る短編作品、コマーシャル、企画が頓挫し実現しなかった作品まで、すべてを語り尽くす! 【目次】 はじめに 1. アメリカの田舎暮らし 2. アート人生 3. 死の袋がにっこり 4. スパイク 5. 若きアメリカ人 6. 幻惑されて 7. ちょっと変わった郊外ロマンス 8. ビニールに包まれ 9. 地獄で見つける愛 10. 上り調子から転落へ 11. 真っ暗のお隣 12. 白い稲妻と女の子のショット 13. 何かの一切れ 14. ハッピーエンドの中のハッピーエンド 15. スタジオにて 16. 私の丸太が黄金に 謝辞 原注 写真クレジット 訳者解説 山形浩生 フィルモグラフィ 展覧会歴 索引
-

仁義なきヤクザ映画史
¥2,365
著者:伊藤彰彦 発行元:文藝春秋 312ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 血沸き肉躍るアウトロー映画の歴史 「死んでもらいます」 健さんが斬る! 「弾はまだ残っとるがよう」文太が吠える! 任俠の起点たる『忠次旅日記』に始まり、『仁義なき戦い』を経て、『孤狼の血』に至るまで、執念の取材でヤクザ映画100年余の修羅に踏み込む。そこに映し出される「暴力の近現代史」を描き上げる画期的労作。 【本書に登場する作品】 「日本映画最初の侠客」尾上松之助『侠客 祐天吉松』(1910)/「落ちていく無頼漢」大河内傳次郎『忠次旅日記』(1927)/「野良犬でなく狼になれ」高橋英樹『狼の王子』(1963)/「死んでもらいます」高倉健『昭和残侠伝』シリーズ(1965~1972)/「インテリヤクザ」安藤昇『血と掟』(1965)/「底知れない虚無」市川雷蔵『ひとり狼』(1968)/「何かギラギラするもの」千葉真一『日本暗殺秘録』(1969)/「ヤクザの青春群像劇」菅原文太『仁義なき戦い』(1972)/「差別のタブーに踏み込む」高島礼子『極道の妻たち 死んで貰います』(1999)/「在日コリアンヤクザ登場」北野武『アウトレイジ 最終章』(2017)/「全編広島ロケ」役所広司『孤狼の血』(2018)/「任侠ファンタジー」本宮泰風『日本統一』(2019)/「元ヤクザの更生」役所広司『素晴らしき世界』(2021)etc.
-
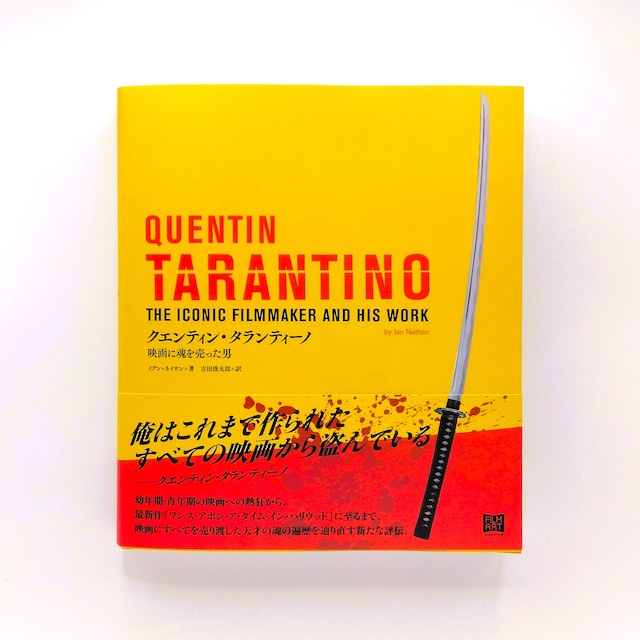
クエンティン・タランティーノ 映画に魂を売った男
¥3,300
SOLD OUT
著者:イアン・ネイサン 訳者:吉田俊太郎 発行元:フィルムアート社 224ページ フルカラー 210mm × 183mm ソフトカバー ~出版社紹介文より~ カルト映画の帝王から、現代を代表する巨匠へ...... 孤高の最新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』に至る、映画にすべてを売り渡した天才の魂をめぐる最新評伝。 幼年期から青年期の映画への熱狂から、『パルプ・フィクション』での批評的・興行的成功を経由し、独自の映画哲学と信念を突き通しつつ、そのほとんどの作品を批評・興行の両面で成功に導き、いまや紛れもなく現代を代表する巨匠のひとりとなったクエンティン・タランティーノの軌跡を網羅的に紹介。 監督作のみならず原案・脚本作の成立背景やテーマを精緻に解き明かし、旺盛な創造意欲に満ちた作品群に初めて触れるための絶好の入門書でありつつ、コアな観客がその才能の真価を改めて発見するための必読書ともなるだろう。 豊富なスチール写真やオフショット、さらには影響を与えた諸作品の資料(スチール、映画ポスター)が、フルカラーで多数掲載!! 作品の内側と外側を横断しながらタランティーノ・ユニバースを味わい尽くせ。 【目次】 1. 「俺は映画学校じゃなく、映画に通ったんだ」 ビデオ・アーカイブス 2.「この映画は自分のために作ったんだ、 みんな勝手に楽しんでくれたらそれでいいけどね」 『レザボア・ドッグス』 3.「どれも別れた元カノみたいなもの……」 『トゥルー・ロマンス』『ナチュラル・ボーン・キラーズ』 『フロム・ダスク・ティル・ドーン』 4.「このキャラクターたちはいつまでも お喋りをやめようとしないんだ……」 『パルプ・フィクション』 5.「向こうから俺に忍び寄ってきたような感じだね」 『フォー・ルームス』『ジャッキー・ブラウン』 6.「自分の事をアメリカ人映画作家だと 思ったことなんて一度もないよ……」 『キル・ビル Vol.1』『キル・ビル Vol.2』 7. 「スラッシャー・ムービーは正統派さ……」 『グラインドハウス』 8. 「とにかく奴をぶっ殺しちまえ」 『イングロリアス・バスターズ』 9.「命は安く、クソみたいに扱われ、 バッファロー・ニッケル(5セント)の価値しかない」 『ジャンゴ 繋がれざる者』 10. 「まるで一度も時代映画を作ったことが ないような気分にさせられるよ」 『ヘイトフル・エイト』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
-

ギレルモ・デル・トロ モンスターと結ばれた男
¥3,300
著者:イアン・ネイサン 訳者:阿部清美 発行元:フィルムアート社 240ページ 210mm × 183mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** モンスターや魔術を偏愛した幼少期、デル・トロはH・P・ラヴクラフトの小説やルイス・ブニュエルの映画、『ウルトラマン』などの日本の作品に胸をときめかせながら成長した。弱冠23歳にしてアルフレッド・ヒッチコックについての大著を出版。長編監督作『クロノス』で華々しくデビューした後、『パンズ・ラビリンス』『パシフィック・リム』『シェイプ・オブ・ウォーター』などでの成功を経て、現代を代表する映画作家の一人となる。 本書では、彼の生い立ちから現在に至るまでの軌跡を網羅的に紹介。長編監督作全ての制作背景やテーマ、俳優やスタッフとの協働の様子がまとめられており、デル・トロ本人の発言から影響を受けた作品や制作秘話も楽しむことができる。資料に基づいた考察は、デル・トロのコアなファンに新しい発見をもたらすだけでなく、これから作品に親しむ人にも入門書として楽しめる内容になっている。 膨大な知識量を誇り、尽きることのない情熱を燃やし続けるこのメキシコ生まれの映画監督は、魔術師でありオタクという他に類を見ない存在だ 。ホラー、おとぎ話、SF、ゴシック・ロマンス、スーパーヒーロー、ストップモーションアニメーション、フィルムノワールといったジャンルを縦横無尽に駆け巡り、独創的な世界を作り上げていくデル・トロ。本書によって、並外れた想像力の扉が日本の読者に向けて開かれる。 ★豊富なスチール写真に加え、メイキングカットやオフショット、さらには影響を与えた諸作品の資料(スチール、本国のポスター)をフルカラーで多数掲載。 ★映画監督としてだけではなく、小説家、プロデューサーとしての側面についても解説。 ★映画化を夢見続ける『フランケンシュタイン』、撮影までたどり着けなかった『狂気の山脈にて』など多数の未完プロジェクトを詳細に解説。 ★盟友アルフォンソ・キュアロン 、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥとの共同作業について詳述。 【目次】 イントロダクション 1. 昔々、メキシコで 幼少期と『クロノス』(1993) 2. トンネルビジョン 『ミミック』(1997) 3. 未完の仕事 『デビルズ・バックボーン』(2001) 4. 血の滾り 『ブレイド2』(2002) 5. ビッグ・レッド 『ヘルボーイ』(2004)&『ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー』(2008) 6. 通過儀礼 『パンズ・ラビリンス』(2006) 7. ハイ・コンセプト 『パシフィック・リム』(2013) 8. フリークハウス 『クリムゾン・ピーク』(2015) 9. ラブ・アクアティック 『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017) 10. 夢を紡ぐ者 『ナイトメア・アリー』(2021)&『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』(2022)
-

ナウシカ考 風の谷の黙示録
¥2,420
SOLD OUT
著者:赤坂憲雄 発行元:岩波書店 374ページ 194mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 一九八二年から雑誌『アニメージュ』に連載され、映画版の制作を挟み九四年に完結した、宮崎駿の長編マンガ『風の谷のナウシカ』。 この作品の可能性の種子は、時代の喘ぎのなか、いま、芽生えと育ちの季節を迎えようとしているのかもしれない――。多くの人に愛読されてきたこのマンガを、二十余年の考察のもと、一篇の思想の書として徹底的に読み解く。 【目次】 はじめに 第一章 西域幻想 1 秘められた原点 アニメとマンガのあいだ はじまりの風景から 宮崎駿の種子をもとめて 2 神人の土地へ 小さな谷の王国 旅立ちのときに 奴隷とはなにか,という問いへ 第二章 風の谷 1 風の一族 部族社会としての風の谷 腐海のほとりに暮らす 風車とメーヴェのある風景 2 蟲愛ずる姫 背負う者の哀しみとともに ギリシャ神話のなかの原像 血にまみれた航海者との出会い 3 子守り歌 孤児たちの物語の群れ あらかじめ壊れた母と子の物語 擬態としての母を演じる 4 不思議な力 物語られる少女の肖像 境界にたたずむ人 王蟲の心を覗くな,という 第三章 腐 海 1 森の人 水と火と調和にかけて 火を捨てて,腐海へ 世界を亡ぼした火とともに 2 蟲使い たがいに影として森に生きる 武器商人から穢れの民へ 森が生まれるはじまりの朝に 3 青き衣の者 ふたつの歴史の切断があった 邪教と予言が顕われるとき 犠牲,または自己犠牲について 4 黒い森 腐海の謎を読みほどくために 第三の自然としての腐海 喰う/喰われる,その果てに 第四章 黙示録 1 年代記 年代記と語りと声と いくつかの歴史語りが交叉する 文字による専制が産み落とした偽王たち 2 生命をあやつる技術 悪魔の技の封印がほどかれる 帝国を支える宗教的呪力の源泉として 対話篇,シュワの庭にて 3 虚無と無垢 呪われた種族の血まみれの女 内なる森を,腐海の尽きるところへ 名づけること,巨神兵からオーマへ 4 千年王国 千年という時間を抱いて 墓所の主との言葉戦いから 物語の終わりに 終 章 宮崎駿の詩学へ おもな参考文献 あとがき
-

ホラーの哲学 フィクションと感情をめぐるパラドックス
¥3,520
SOLD OUT
著者:ノエル・キャロル 訳者:高田敦史 発行元:フィルムアート社 500ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 分析美学の第一人者であり、映画・大衆芸術(マス・アート)研究の分野でも活躍するノエル・キャロルによる、ホラーの哲学の初めての体系的著作。 『フランケンシュタイン』『ジキル博士とハイド氏』『ドラキュラ』『エクソシスト』『オーメン』『エイリアン』、さらにはH・P・ラヴクラフト、スティーヴン・キング、クライヴ・バーカー、シャーリイ・ジャクスンなど…… 本書では、古典的名作から現代のヒット作品、さらには無名のB級作品まで、膨大な作品群を縦横無尽に取り上げながら、ホラーとは何か、その本質や定義、物語構造とプロット分析、ホラーの魅力、さらにはホラーモンスターの作り方についてなどを論じる。 そして、哲学的な観点から、存在しないとわかっているものをなぜ怖がってしまうのか(フィクションのパラドックス)、また、恐怖を与えるホラー作品をなぜわざわざ求めるのか(ホラーのパラドックス)について考察する。 吸血鬼、ゾンビ、人狼、悪魔憑きの子ども、人造人間、スペースモンスター、幽霊、その他の名もなき怪物たちが、なぜわたしたちの心を摑んで離さないのか。 フィクションの哲学、感情の哲学、ポピュラーカルチャー批評を駆使して、その不思議と魅力の解明に挑む! 【目次】 謝辞 序 本書が置かれた文脈/ホラージャンル摘要/ホラーの哲学とは? 第1章 ホラーの本質 ホラーの定義 まえおき 感情の構造について アートホラーを定義する アートホラーの定義に対するさらなる反論と反例 幻想の生物学とホラーイメージの構造 要約と結論 第2章 形而上学とホラー、あるいはフィクションとの関わり フィクションを怖がる──そのパラドックスとその解決 フィクション錯覚説 フィクション反応のフリ説 フィクションへの感情反応の思考説 要約 キャラクター同一化は必要か 第3章 ホラーのプロット ホラープロットのいくつかの特徴 複合的発見型プロット バリエーション 越境者型プロットおよびその他の組み合わせ 典型的ホラー物語が与えるもの ホラーとサスペンス 疑問による物語法/サスペンスの構造 幻想 第4章 なぜホラーを求めるのか? ホラーのパラドックス 宇宙的畏怖、宗教的経験、ホラー ホラーの精神分析 ホラーの魅力の一般理論と普遍理論 ホラーとイデオロギー ホラーの現在 訳者解説
-

映画術 その演出はなぜ心をつかむのか
¥2,530
SOLD OUT
著者:塩田 明彦 発行元:イースト・プレス 255ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 視線、表情、声、動きはここまで計算されていた! 観る者を魅了する人物は、どのように作られるのか? 映画監督の著者が、偏愛するさまざまなシーンを取り上げながら、心をつかむ<演技と演出>の核心に迫る連続講義。 【目次】 第一回 動線 第二回 顔 第三回 視線と表情 第四回 動き 第五回 古典ハリウッド映画 第六回 音楽 第七回 ジョン・カサヴェテスと神代辰巳 あとがき
-

アニエス・ヴァルダ 愛と記憶のシネアスト (ドキュメンタリー叢書#03)
¥2,200
編者:若林良 吉田悠樹彦 金子遊 発行元:neoneo編集室 196ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 日本では初となる、映画作家アニエス・ヴァルダの全貌に迫った論集。 娘であり、晩年のヴァルダの展覧会のプロデュースなどにあたった娘ロザリーへのインタビューをはじめ、『幸福』『歌う女・歌わない女』『冬の旅』などの代表作品、夫ジャック・ドゥミとの関係、ヌーヴェル・ヴァーグの諸作家との比較、写真やインスタレーション作品などに迫った論考や作品ガイドを収録する。 【目次】 《インタビュー》 ロザリー・ヴァルダ(アニエス・ヴァルダの長女)インタビュー アニエス・ヴァルダは愛情深く好奇心旺盛、同時に要求が厳しい母親でした 魚住桜子 《論考》 大寺眞輔 アニエスからあなたへ 原田麻衣 アニエス・ヴァルダの「エッセー」 松房子 持続する瞬間 アニエス・ヴァルダと写真 千葉文夫 アニエス・Vによるジャック・ドゥミ 東志保 現実の世界に住まうこと 『冬の旅』における周縁性へのまなざし 児玉美月 やわらかな革命者が『歌う女・歌わない女』で奏でる音色 吉田悠樹彦 記憶・文化史・映像メディア 『ダゲール街の人びと』『顔たちところどころ』を中心に 金子遊 カリフォルニアのアニエス・V 若林良 虚構と自然のはざまで 『幸福』に見るアニエス・ヴァルダの視線 菊井崇史 映画の渚、まなざしの記述 《作品ガイド》 『5時から7時までのクレオ』『幸福』『落穂拾い』……アニエス・ヴァルダ作品ガイド 若林良、大内啓輔、上條葉月、柴垣萌子、井上二郎
-

サスペンス映画史
¥3,740
著者:三浦哲哉 発行元:みすず書房 328ページ 188mm × 128mm ハードカバー ~出版社紹介文より~ 「ひとは何を求めて映画を見るのか。自由の幻想を求めてである、という答えが第一にありうるだろう。(…)しかし、それだけではない。自由ではなく不自由の体験を観客に与えようとするフィルム群があることは、誰しもが知るところであるだろう」 “サスペンス”とは、宙吊りの状態、未決定の状態に置かれること。登場人物および観客をもそんな状態に巻き込むのが、サスペンス映画である。ひとはなぜ自らすすんで、そんな不自由と恐怖を求めて映画を見るのか。 感情移入とカタルシスに基づく説話論的サスペンス理解を超えて、確かな足場のない宙吊りの不安、さらには不安がもたらす魅惑を、サスペンス映画はさまざまに組織し、洗練し、そして継承してきた。 「不安が最終的に解消されることなどけっしてなく、(…)ヒッチコック的な眼差しを経由したいま、日常は、映画館の外においても、つねにすでに犯罪を抱え込んだものとして現れる」 グリフィス、セネット、キートン、ラング、ウェルズ、ターナー、ヒッチコック、スピルバーグからイーストウッドまで、斬新な映像分析、小気味よい論理展開、息づまる(映画的な)場面描写によって、新たな映画の見方を提示する。表象文化論の新鋭による、読み物としても第一級の映画史。