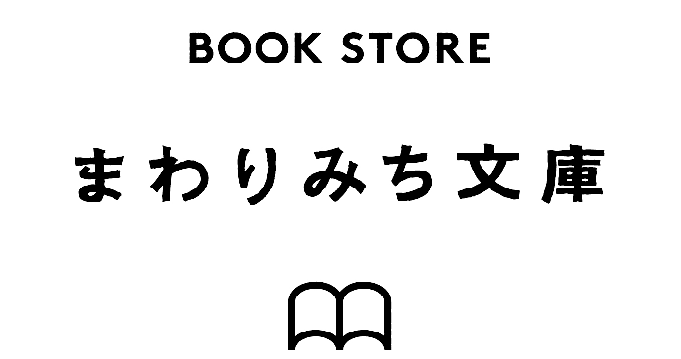-

ぼくらのコーヒー地図
¥800
デザイン:小田原史典 表紙装画:小田原裕子 編集:早坂大輔 執筆者:早坂大輔/長谷川裕子/森幸司/今井健/田中善大/千葉幸平/奈良匠 特別紀行・挿画:牧野伊三夫 *********************** 店主コメント *********************** 京都の焙煎家・オオヤミノルさんの発案で始まったプロジェクト「コーヒーブレイクは大切ですね!」 自分にとってコーヒーショップとはどんな場所なのか? その答えのヒントが詰まった岡本仁さんの著書『ぼくのコーヒー地図』(平凡社)を、コーヒーショップをはじめとする全国の個人店で1,000冊販売しようという試みです。 本の販売とともに、トークショーなど独自の企画が各エリアで展開されており、東北・北海道ブロックではBOOK NARDさんが中心となって、小冊子『ぼくらのコーヒー地図』制作。 表紙のデザインと装画は、THE STABLESさんが担当。 店主8名のコーヒーにまつわるエッセイやレコード、本の紹介のほか、画家の牧野伊三夫さんによる特別寄稿を収めた散文集です。
-

ぼくのコーヒー地図
¥2,420
著者:岡本仁 発行元:平凡社 328ページ 188mm × 122mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** コーヒーブレイクは大切ですね―― 日本全国58都市166店を紹介 manincafeのIDでInstagramにコーヒーを飲む日常をポストする編集者岡本仁によるコーヒー店案内。コーヒーの味だけではなく、店主、音楽、そして集まる客がつくりあげる、ゆるやかな、時にはピリリとした空気……老舗の喫茶店から新しいコーヒースタンド、ナショナルチェーンから個人店、時には紅茶店や日本茶店まで、街を歩いて見つけた166店で考えたコーヒーとの幸せな関係。オールカラー。
-

そいつはほんとに敵なのか
¥1,870
著者:碇雪恵 発行元:hayaoki books 188mm × 128mm ソフトカバー 176ページ ************************* 出版社紹介文より ************************* SNSを捨て、喧嘩を始めよう。 “合わない人”を遠ざける人生は、心地いいけどつまらない。 もっと沸き立ちたいあなたに送る、現代人必読の〈喧嘩入門エッセイ〉誕生! 駅でキレているおじさん、写真を撮りまくる観光客、理解できない政党と支持者、疎遠になった友だち、時にすれ違う家族や恋人……。 「敵」と決めつけて遠ざけるより、生身の体でかれらと出会い直し、逃げずにコミュニケーションをとりたい。 ZINE『35歳からの反抗期入門』が口コミで大ヒット中の書き手・碇雪恵による、待望の商業デビュー作。 憎みかけた「そいつ」と共に生きていくための思考と実践の記録をまとめた14編を収録。 【状態】 喧嘩がしたい 純度の高い親切 友情の適正体重 悪意に顔があったーー映画『ルノワール』を観て 反抗期、その後 誰の場所でもない 身内をつくる(ひとりで考えてみた編) 身内をつくる(実践スタート編) 対戦じゃなくて協力モードで ティンプトンから始まるーー映画『ナミビアの砂漠』にみる恋愛と喧嘩 自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(準備編) 自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(実践編) ほんとは敵じゃない 時折自分を引き剥がすーー映画『旅と日々』を観て
-

ミスドスーパーラブ
¥1,650
発行元:トーキョーブンミャク 160ページ 210mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** ミスドに愛を叫ぶアンソロジー『ミスドスーパーラブ』が完成致しました。 豪華クリエイター陣によるグラフィック、短歌、小説、童話、エッセイ、ヴィジュアル作品で表現されたドーナツ、パイ、飲茶など26のメニューが収録されています。 おやつのお供にぴったりな一冊。ミスドに行く前にも行った後にも。 あなたのいつものお気に入り、新しいお気に入りを是非見つけてください。 各話には、タイトルのドーナツの写真・イラストもそれぞれ収録しておりますので見ても読んでも楽しめるスタイルとなっております。 【収録メニュー/参加クリエイター】 ・『表紙』カトウトモカ ・『生きてるだけでパーティ』(ビジュアル作品)イリエナナコ×小出薫×小野紗友美 ・『ポン・デ・リング』eri ・『ポン・デ・黒糖』夜夜中さりとて ・『ポン・デ・ストロベリー』ごはんとアパート ・『オールドファッション』mayan ・『チョコファッション』ネネネ ・『オールドファッション ハニー』まりさん ・『フレンチクルーラー』オルタナ旧市街 ・『エンゼルフレンチ』田中泉 ・『ストロベリーカスタードフレンチ』櫻井朋子 ・『ハニーディップ』吉玉サキ ・『シュガーレイズド』西川タイジ ・『チョコリング』アベハルカ ・『ストロベリーリング』青. ・『エンゼルクリーム』鶴見 ・『カスタードクリーム』堀静香 ・『チョコレート』すなば ・『ココナツチョコレート』西川☆タイジ ・『ダブルチョコレート×ホットチョコレート』小林えみ ・『ゴールデンチョコレート』けんず ・『ハニーチュロ』なつめ ・『ドーナツポップ』サトウリョウタ ・『エビグラタンパイ』まーしゃ ・『ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト』旦 ・『汁そば』ひらいめぐみ ・『きなこボール』野菜/イラスト:カトウトモカ ・『ブラン』友田とん/イラスト:カトウトモカ ・『君がここに着く前に』(ビジュアル作品)すなば×三浦希
-

5秒日記
¥1,870
SOLD OUT
著者:古賀及子 発行元:ホーム社 販売元:集英社 188mm × 128mm ソフトカバー 256ページ ************************* 出版社紹介文より ************************* 『日記は1日のことをまるまる書こうとせずに5秒のことを200字かけて書くと良い』 そんなつぶやきから生まれた、「北欧、暮らしの道具店」の人気連載がついに書籍化! 「鳩サブレーは、はんぶんこが難しい。袋の上から慎重に慎重にふたつになるように割った。娘には別のお菓子があるから、学校から帰ってきた息子と私のふたりで分けた。どうも尾の側のほうが大きそうで、そちらを息子に渡す。私は少食のくせに意地汚く欲ばりで、でも、こういうときは躊躇なく大きなほうを子どもに渡すのだった。大きいほうを渡すときはいつも、山賊の親も子にはこうだろうと思う。」 「冷奴を生姜ではなくわさびで食べようと食卓に出したら、息子が白いご飯にわさびをのせて醤油をかけ、『海鮮丼の瞬間の味』と言って味わっており、私も真似した。海鮮丼そのものの味はしない。けれどたしかに、瞬間の味はする。」(本文より) 日常のささいな瞬間のきらめきがぎゅっと詰まった珠玉の日記エッセイです。
-

日々のあわあわ
¥2,200
著者:寺井奈緒美 発行元:リトル・モア 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 歌人、エッセイスト、そして土人形作家として大注目の寺井奈緒美。 歌集『アーのようなカー』、短歌とエッセイ『生活フォーエバー』『おめでたい人』に続く、待望の最新エッセイ集!\短歌と土人形も/ ■ ○ ▲ □ ● △ ■ ○ ▲ □ ● △ オノマトペ × 短歌・エッセイ・土人形! △ ● □ ▲ ○ ■ △ ● □ ▲ ○ ■ ピロピロ、もちもち、シャキシャキ、 ぴかぴか、ぼそぼそ、ビューン、どよーん、 キイキイ、わたわた、もちゃもちゃ、 ハラハラ、すん、バタバタ、びしょびしょ…… オノマトペに誘われて、 身のまわりのアレコレに目をやると、 日常はとってもオモシロイ! ちょっと落ち込んで、 少し笑って、 変なものに目を奪われ、 奇妙な空想に救われて。 スイスイ読めて、ニヤニヤとほころぶ。 気持ちをゆるゆる緩めてくれる。 共感がヒシヒシ湧きおこる!
-

人といることの、すさまじさとすばらしさ
¥2,200
著者:きくちゆみこ 発行元:twililight 188mm × 128mm ソフトカバー 272ページ ************************* 出版社紹介文より ************************* 人間関係101の人たちへ。 “「ああもう無理だ、くたくただ 」、相変わらずベッドに大げさに倒れ込みながら、「でも それってなんでなの?」「じゃあどうしたら楽になる?」まるで何かの実験みたいにしつこく自分に問いかけて、消耗しない人との距離を、毎日言葉でさぐっている(わからなくなれば、入門クラスの生徒よろしく、書店に、図書館に駆け込んで、先達たちの言葉をあおぎながら)”(「はじめに」より) 2010年よりパーソナルな語りとフィクションによる救いをテーマにしたzineを定期的に発行し、2023年にはtwililightから初めてのエッセイ集『だめをだいじょぶにしていく日々だよ』を刊行した翻訳・文筆家のきくちゆみこ。 今作『人とともにいることの、すさまじさとすばらしさ』は、あたらしく引っ越してきた郊外の団地で、長年苦手としてきた「人とともにいること」の学びと向き合う日々を綴った日記エッセイ。 “遠くの生に思いを寄せながらも、身近なところにいる、それでも自分とはちがう「他者」へのまなざしを変えなくては、たどり着けない場所があるような気がしていた。ケアをじゅうぶんに発揮しながら絶え間なく人と向き合い、それでいて自分を消耗させない方法をなんとか見つけたかった。 だからこそ、家族よりは遠く、それでも「いま・ここ」で日々関わることになった団地やコミュニティについて、そこにどっぷり浸かっている自分について、書いてみたかったんだと思う。”(「あとがき」より) 前作同様、twililight web magazineでの連載をまとめ、書籍化にあたって全12回に「アフター・トーク」を書き下ろしました。 装画は中島ミドリ、デザインは横山雄。 “書くことが、時間をかけることが、わたしをケアフルでいさせてくれることを、これまでの経験で知っていたから。くり返しにしか思えない日々のなかにこそ、奇跡のような瞬間が隠れていることを、見慣れたはずの顔の上に、ふと思いがけない表情が浮かぶことを、書くことがずっと教えてくれていたから。”(同前)
-

光と糸
¥2,200
著者:ハン・ガン 訳者:斎藤真理子 発行元:河出書房新社 192mm × 130mm ハードカバー 214ページ ************************* 出版社紹介文より ************************* 2024年にノーベル文学賞受賞後に韓国で刊行された初の単行本。受賞記念講演・エッセイ・詩を著者本人が編んだ、光と命をめぐる祈りのメッセージ。 世界は、なぜこれほど暴力的で、同時に、なぜこれほど美しいのか? 著者自身が構成を編み上げた、ノーベル文学賞受賞後初の作品がついに刊行。光へ向かう生命の力への大いなる祈り。 【目次】 光と糸 いちばん暗い夜にも 本が出たあと 小さな茶碗 コートと私 北向きの部屋 (苦痛に関する瞑想) 声(たち) とても小さな雪のひとひら 北向きの庭 庭の日記 もっと生き抜いたあとで 訳者あとがき
-

ふつうの人が小説家として生活していくには
¥1,760
SOLD OUT
著者:津村記久子 聞き手:島田潤一郎 発行元:夏葉社 208ページ 179mm × 119mm ハードカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 小説家に聞いた 4 日間。生きるヒントにあふれるインタビュー。 2005 年に太宰治賞の受賞作『君は永遠にそいつらより若い』でデビューした津村記久子さんは今年、デビュー20 周年を迎えます。 休むことなく、『ポトスライムの舟』、『ディス・イズ・ザ・デイ』『つまらない住宅地のすべての家』、『水車小屋のネネ』などの傑作を発表し続けた作家はどのように暮らし、どのように小説を書いてきたのか? 同世代の編集者が共通の趣味である音楽、サッカーの話をまじえながら、その秘密を根掘り葉掘り聞きました。「オープンソースだけで仕事をしてきた」と語る「ふつうの人」がなぜ、唯一無二の作家となったのかを解き明かす、元気が出て、なにかを書き たくなる、ロング・インタビュー。 名言がたくさんです。
-

暮らしの本
¥2,200
発行元:MINOU BOOKS 173mm × 105mm ソフトカバー 285ページ *********************** 店主コメント *********************** 35人の書き手が「暮らし」というテーマで、一冊の本を紹介する。 それぞれの文脈で語られる「暮らしの本」は、日々の営みの指針を照らし出す。 すべての読書は暮らしに通ず、と思えるような書評エッセイ集。 (執筆者)※ 順不同 敬称略 山村光春 / 城下康明 / 三宅玲子 / 大井実 / 島田潤一郎 / はしもとゆうき / 牟田都子 / 小坂章子 / 浅野佳子 / 加藤木礼 / 米村奈穂 / 酒井一途 / 北川史織 / 中前結花 / 碇雪恵 / 丹治史彦 / 鯨本あつこ /土門蘭 / 服部みれい / 豊嶋秀樹 / ちえちひろ / 千葉智史 / ひらいめぐみ / 林央子 / おぼけん / 黒田杏子 / 青木真兵 / 福永あずさ / 永野三智 / 村上由鶴 / 戸倉江里 / 大竹昭子 / 古賀及子 / 永井玲衣 / 関根愛 【目次】 ・読書の悦び ・暮しの指針 ・わたしの生き方 ・自然のなかで ・日々を問いなおす ・他者と共に生きる ・暮らしと平和
-

貧乏讀本
¥1,980
SOLD OUT
編者:鹿美社編集部 発行元:鹿美社 226ページ 180mm × 115mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 〈豊かさとは何か〉 24名の詩、小説、俳句、短歌、随筆、日記、ルポルタージュ、翻訳 「貧乏」に纏わる前代未聞の哲学的総合文芸アンソロジー 種田山頭火 俳句十五選 林芙美子「放浪記以前」 横山源之助「日本の下層社会」(抄) 太宰治「清貧譚」 ランボオ/中原中也「教会に来る貧乏人」 小林多喜二「失業列車」 山上憶良/折口信夫「貧窮問答歌」 三好達治「貧生涯」 与謝野晶子「おとくの奉公ぶり」 芥川龍之介「十円札」 山之口貘「妹におくる手紙」 黒島伝治「電報」 岩野泡鳴「何の為めに僕」 萩原朔太郎「大井町」 小山清「落穂拾い」 樋口一葉 日記より 石川啄木『一握の砂』より 辻潤「瘋癲病院の一隅より」 幸田露伴「貧乏の説」(抄) 河上肇「古今洞随筆」 八木重吉「神の道」 森茉莉「贅沢貧乏」
-

旅は老母とともに
¥2,750
著者:伊藤礼 発行元:夏葉社 384ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 唯一無二のユーモアがよみがえる。すこし厚めの遺稿集。 伊藤整の次男、伊藤礼さん(1933-2023)は自転車にまつわる『こぐこぐ自転車』や『大東京ぐるぐる自転車』などのエッセイの書き手として知られています。 還暦を過ぎてロードバイクに乗りはじめ、全国各地を旅した顛末を描いたエッセイは抱腹絶倒で、そこには旅の魅力と、融通無碍な礼さんの文章の魅力があります。 本書にはその自転車にまつわるエッセイも収録されていますが、中心となっているのは家族のこと、とりわけ、父・伊藤整のことです。といっても、堅苦しい話はほとんどなく、ユーモアたっぷりに昭和の文豪の姿を描いています。礼さんの筆をとおして眺める伊藤整は人間味にあふれ、読む者の記憶にくっきりと残ります。伊藤整や自転車に興味がなくても、おもしろい読み物を読みたいという読者におすすめできます。装画は南伸坊さんです。
-

星とアスパラ
¥2,530
著者:本条恵 発行元:短歌研究社 208ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 本条さんの言葉は、のびのびしているけど、背伸びはしていない。 等身大の言葉でしか書けないことを、確かな手触りで伝えてくれる歌たち。 その一つ一つが愛おしい。日常の中に詩があることを、あらためて思う。 俵 万智(帯より) ふたりめの子どもが生まれ、子どもたちが それぞれに幼稚園・小学校などへと進み、 その後病を得て入院。そうした目まぐるしくもかけがえのない 十二年間の作品が詰まった一冊。 どんな陽を風を言葉を浴びてきたチリ産アスパラ98円 「迷う」って打とうとしたのに三回も間違えて、もう「魔王」で生きてく 夕闇に自転車を漕ぐどうしても寝てしまう子を後ろに乗せて イヤホンを通じて脳に送られる中島みゆきという名の麻酔 「月を跨ぎそうだよ」LINEに銀河ほどの背丈になったあなたを思う (収録歌より)
-

大工日記
¥1,980
著者:中村季節 発行元:素粒社 178mm × 128mm ソフトカバー 240ページ *********************** 出版社紹介文より *********************** 36歳女性、異国で夢破れ、家業である大工の世界に飛びこんだ――ハードモードな“現場”の日々を、体当たりの知性とユーモアで疾走する驚きのデビュー作! 自主制作版『大工日記』(2024年)を大幅改稿。 「なんでもいいから今年は大工をやれ。やろう。そうしよう。いくぞ。そうして始めた私の大工見習いの日々の記録です」(本文より)
-

文通 答えのない答え合わせ
¥1,870
SOLD OUT
著者:古賀及子/スズキナオ 発行元:シカク出版 256ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「感情的」という言葉は子どもや若者の特徴のように扱われがち。 しかし大人だからこそ振り回されたり、大人になったから知る感情もあります。 切実なのに軽んじられがちな大人の感情を見つめ、それぞれの目線で汲み上げて綴った ちょっと弱気な対話の記録。 本書の前半部分を収めたZINE『青春ばかり追いかけている、何もかも誰より一番慣れない』は、独立書店と即売会だけで1300部を半年間で完売。 読書好きの間で密かな話題となりました。 本書ではZINEに収録された以降のやりとりも加え、倍のボリュームで装いも新たに書籍化。 答えは出ないけれど、読むと自分の感情を見つめなおしたり、漠然と抱えていた気持ちに気付けるかもしれない。そんな1冊です。
-

お金信仰さようなら
¥1,980
著者:ヤマザキOKコンピュータ 発行元:穴書 188mm × 128mm ビニールカバー 224ページ ************************* 出版社紹介文より ************************* 働いて働いて働いて働いて働いて、 収入を伸ばし、貯蓄を増やし、経済最優先の社会の中で、 労働と成長ばかり求められてきた。 私たちは、「お金信仰の時代」に生まれ育った。 しかし、一部の間ではもう新たな時代が始まっている。 ーーーーー ・どれだけの資産があれば人は幸せになれるのか? ・売れないものには価値がないのか? ・経済成長すれば私たちの暮らしは豊かになるのか? 金融界のみならず、国内外のパンク・シーンや多種多様な地下カルチャーを渡り歩いてきた著者が、 そこで培った独自の視点でひとつひとつの疑問を解き、 貯蓄でもなく、選挙でもない、新しい選択肢を提示する。 『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(6刷)で話題をさらった、 投資家でパンクスの著者による最新作。 今度こそ、くそつまらない未来は変えられる。 お金信仰が終わったあとの時代で、 何を指針に生きるのか? まだ名前の付いてない、新たな時代へと突き進む私たちのための入門書。 【目次】 この本を書くにあたって 第1章 自分の〈いま〉に名前を付ける お金を信仰する時代 退屈で残酷な、グローバル資本主義社会 お金の大小しか見ない、一次元的な世界観 ①市場信仰 ②貨幣信仰 お金ではなく、お金信仰に別れを告げる 第2章 未来に不要なものは置いていく 新しい時代の歩き方 ハードコアパンクバンドが示してくれたアンサー お金持ちになったら幸せになる? 国が豊かになったら貧困問題は解決する? 〈見えざる手〉は人々の理想を実現できる? 私たちの暮らしは本当に豊かになっている? お金がここまで強く信仰される理由 第3章 新しい価値観に名前を付ける 新たな世代の、新たな価値観 アメリカのFIREムーブメント 中国の寝そべり主義者宣言 パラレルワールドをいまからやる 欧州パンクの共同体における知性あふれる価値観の共有 昔の商店街に見る、活気主義の世界 自分が本当に価値を感じるもの 接続性=人や社会とのつながり×文脈としてのつながり ①社会的接続価値 ②文脈的接続価値 お金信仰は終わらせる力、接続性はつなぐ力 お金信仰に別れを告げるときが来た さいごに 私が出した、ひとつの答え
-

光子ノート
¥3,850
SOLD OUT
著者:やべみつのり 発行元:たろう社 992ページ 182mm × 130mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 矢部太郎の父・やべみつのりが描いた38冊の子育て日記から厳選 姉・光子と弟太郎のささやかで瑞々しい日々 ひとり娘の光子ちゃん、外へ働きに出るお母さん、家にいるお父さん。 その日常を手書きの絵と少しの文章で、来る日も来る日も描き続けたお父さん。 「おとうさんはまいにちなにをしてるの」(本文 光子ちゃんからお父さんへの手紙より) 1970年代はじめ、高度成長期の東京、娘を見つめ、自分をもういちど生き直す父の記録。 「どんづまりだった」父は、娘が世界と出会うその過程のすべてを記録しようとするかのようにノートを描き続けます。 お友達と遊んだり、保育園に行ったり、 はじめて字を書いたり、動物園に行ったり、 お誕生日が来たり、お風呂屋さんに行ったり、 プールに行ったり、お友達と遊んだり、お誕生日が来たり……。 そんな一瞬一瞬を誰かに読んでもらうためでもなく、ただ描かれ続けたノート。 父はやがて絵本作家になり、お母さんは赤ちゃんが産まれると光子ちゃんに伝えます。 生きている、それが続いていく、そのかけがえのなさを。
-

自炊の風景
¥1,760
SOLD OUT
著者:山口佑加 発行元:NHK出版 188mm × 128mm ソフトカバー 208ページ ************************* 出版社紹介文より ************************* 生活も人も料理も毎日少しずつちがう。その日にしかない偶然があるから、自炊は面白い 食、暮らし、旅、家族・友人などさまざまな場面で料理の片鱗に触れて心が動いた瞬間を、ありのままに綴った自炊料理家・山口祐加初のエッセイ集。初めて料理をした7歳の頃から、料理家としての独立を経て、世界の自炊を求めて海外を訪ね歩いた現在までに食べてきた食卓の数々の風景を凝縮し、豊富な写真とともに17のレシピも収載。「自炊」にとことん向き合い、著者と料理との関係性を浮き彫りにする、いま最注目の料理家の日常の記録。 【目次】 「自炊」ってなんだ 自炊料理家漂流記/料理の「コツ」ってなんだろう?/私が自炊を教える理由/冷蔵庫の食材テトリス/母のめんつゆ炒め/おばあちゃんの質素なお雑煮/「今日のごはん、何がいい?」って聞かれたら、何と答えるのが正解なのか/畑仕事と資本主義社会/秘密の汁かけ飯/一人暮らしで得た自炊の自由/一人ごはん実験室/友達を家に呼んで食べる時に考えていること/料理と偶然出会うこと/先に食べてるよ/繰り返しの毎日に飽きないために 未知の自炊を求めて世界へ 海の向こうの自炊/手の動きが美しい国、台湾/チヂミには酢醬油につけた玉ねぎを/「敵にレシピは教えないでしょう?」/インド人青年のミッドナイトパスタ/自分で選ぶ・作る生活/フランス人から学んだコース料理の美学/おいしいミネストローネの秘密/パリ郊外の友達の家にて、冷蔵庫にあるもので自炊/メキシコで作る働き者のためのハンバーグ/未知なる料理のオンパレード。メキシコのお母さんが作る家庭料理/ペルーの山奥で暮らすおばあちゃんの食卓/料理家の海外持ち物リスト/ラオスは原始の料理が残る国 そして、自炊は続く 忘れたくない家、街/未完成の食卓/食欲さんの家出/クリスマスぎらい/作り置きの出産祝い/春は風味を食べる季節/現代おせち批評/岡山で出会った「じゃぶじゃぶ」と「牡蠣飯」/75歳の自炊の先輩/つわりと食生活/二度と作れないカレー/献立に「なる」 はじめに おわりに
-

now loading
¥2,200
著者:阿部大樹 発行元:作品社 176ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* はじめて言葉を話した日から はじめて嘘をついた日までの記録 精神科医で、翻訳家で、一人の親 進んで止まってまた進む、こどもと過ごす日々 「保育参観のとき親は見つからないように変装をする。 眉毛まで隠すこと、声を出さないことがコツだという。 こう真面目に変装について考えることが今後あるかどうか。」 ――本書より
-

私労働小説 負債の重力にあらがって
¥1,870
著者:ブレイディみかこ 発行元:KADOKAWA 272ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** Don‘t Blame Yourself! セクハラ、パワハラ、カスハラ、人種差別に事なかれ主義やポジティブ教の上司まで。 ジョブには最低なものとの戦い(ワーク)がつきまとう。 ホールスタッフ、激安量販店の店員、屋敷の掃除人にローンの督促人etc. 「底辺託児所」の保育士となるまでに経た数々のシット・ジョブを軸に描く、自伝的小説にして魂の階級闘争。 「あたしたちは負債の重力に引きずられて生きている。」 だが、負債を返済するために生き続けたら人間は正気を失ってしまう。シット・ジョブ(くそみたいに報われない仕事)。 店員やケアワーカーなどの「当事者」が自分たちの仕事を自虐的に指す言葉だ。 他者のケアを担う者ほど低く扱われ、「自己肯定感を持とう」と責任転嫁までされる社会。自らを罰する必要などないのに。 働き、相手に触れ、繋がる。その掌から知恵は芽吹き、人は生まれ直し、灰色の世界は色づく。 数多のシット・ジョブを経た著者が自分を発見し、取り戻していった「私労働」の日々を時に熱く、時に切なく綴る連作短編集。 みんな誰かに負債を返すために生きている。それこそが、闇だ ■面倒を避け続ける職場では、いいことは悪いことになり、悪いことがいいことになる。 ■上から目線の人々は、あまりに視線の位置が高すぎて、その位置から下の人間の姿が見えてない。だけど、なんとなく下のほうに人がいる気配がするので、とりあえず声はかけておくが、相手の姿は見えないし声も聞こえないのだ。 ■嫌と言えない理由があるから貸すのであり、返さなくてもいいという暗黙の了解もあるのだ。こういう特殊な取り決めが成り立つ関係を、家族と呼ぶのだろうか。 【目次】 第一話 ママの呪縛 第二話 失われたセキュリティを求めて 第三話 アジアン・レストランの舞台裏 第四話 ある見習い掃除人の手引書 第五話 店長はサクセスお化け 第六話 ある督促ガールの手記 あとがき
-

人生の「成功」について誰も語ってこなかったこと 仕事にすべてを奪われないために知っておきたい能力主義という社会の仕組み
¥1,705
著者:勅使川原真衣 発行元:KADOKAWA 272ページ 182mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「成功者」って増えるの? 「公平な競争」は存在する? 「誰にでもできる仕事」なんてある? 「自分の人生は合っているのか?」――答えも納得も成長も、実はあなたが定義しなければならない。 能力主義をときほぐす今もっとも支持される組織開発専門家、最新刊 「本当にひとりひとりの生を大切にするのなら、「成功」が必要なのではなく、 成功や失敗なんて安直な二項対立ではなく、どんな人であれ、生存権が保障されていることではないだろうか。」(本文より) 【目次】 第1章「成功」とは何か? 第2章「成功者」は増えるのか? 第3章「成功者」が増えない「成功」哲学はなぜ廃れないのか? 第4章「失敗」とは何か? 第5章「成功」の陰で見えなくされたもの 終章 これからの「成功」──ポスト「成功」哲学とはなにか?
-

わたしたちの停留所と、書き写す夜
¥2,000
著者:キム・イソル 訳者:小山内園子 発行元:エトセトラブックス 133ページ 191mm × 131mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** わたしの言葉を、 わたしはまだ取り戻せるだろうか。 40代未婚の「わたし」は、老いた父母やDVを受けて実家に戻ってきた妹親子のケア労働に果てなく追われ、詩人になる夢も「あの人」とのささやかな幸せもすべてを諦めて生きている。一日の終わりに、好きな詩を筆写することだけが自分を取り戻す時間であった「わたし」が、それすら失ってしまう前にとった選択とは――。 韓国フェミニズムのうねりのなか生まれ、いま「停留所」に佇むすべての人におくる、真に大切なものを静かに問いかける「人生小説」。
-

しゃべって、しゃべって、しゃべクラシー! 憲法・選挙・『虎に翼』
¥1,870
SOLD OUT
著者:カニクラブ 國本依伸 編者:浪花朱音 発行元:タバブックス 192ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 目的のないおしゃべりこそ、民主主義の第一歩! しゃべクラシー=おしゃべり+民主主義(デモクラシー)。 『虎に翼』が縁でつながった、共に関西在住の女性3人おしゃべりユニットとベテラン弁護士。法について学び、選挙の行方を憂い、政治、社会、エンタメ、表現など、縦横無尽に語りまくった。緊急発行して話題となったZINE「参政党憲法をかわりに読んでみた。」を大拡張、読んだらきっとあのモヤモヤを誰かとしゃべりたくなる、元気と勇気と笑いにあふれた1冊。 【目次】 まえがきのおしゃべり NHK連続テレビ小説『虎に翼』をきっかけにつながったカニクラブと國本さん。出会いからZINEの制作、今日に至るまでのまえがきを4人の「おしゃべり」でお届けします。 1章 法でみんな、生き残ることはできる? 『虎に翼』をきっかけに、法や法律について考え始めたカニクラブ。日常にはびこる差別、終わらない戦争や虐殺などに立ち向かう「法」の力はないのだろうか? そんな疑問に答えてもらうべく、法のプロ・國本さんの元を訪ねました。 2章 参政党憲法をかわりに読んでみた。 2025年7月に行われた参議院選挙。「日本人ファースト」を掲げ、差別を煽動する参政党が躍進していることに、危機感を募らせていたカニクラブ。國本さんの呼びかけで、参政党の憲法草案を読み合い、緊急編のZINEを制作することに……。 3章 選挙後、これからどうする? さまざまな問題や課題を残したまま、参議院選挙が終了。この先も続くであろう不安定な状況の中で、ひとりの市民として、チームとして、マジョリティとして、どんなことをやっていけるのか。再び集い、ざっくばらんにおしゃべりしました。 おまけ タイトル案をカニクラした 本書のタイトル「しゃべクラシー」は、おしゃべり+民主主義(デモクラシー)から生まれた言葉です。どんな紆余曲折を経て、このタイトルにいきついたのか。4人で「カニクラする(長時間しゃべることを意味する)」ようすをお届けします。
-

アニータの夫
¥1,870
SOLD OUT
著者:坂本泰紀 発行元:柏書房 188mm × 128mm ソフトカバー 266ページ ************************* 出版社紹介文より ************************* 青森14億円横領事件。何もかも「アニータ」に捧げた男。 「誠意を持って真実をお話しします」。新聞社に勤める記者のもとに、一通の手紙が届く。差出人は、青森県住宅供給公社から14億5000万円を横領し、そのうち少なくとも8億円を妻アニータに送金した千田郁司(ちだ・ゆうじ)だった。 なぜ、千田は公金を自在に動かすことができたのか。 なぜ、その金は海を越え、チリへ送られたのか。 朝日新聞連載時から大きな反響を呼んだ「事件のその後」がついに書籍化。 青森からサンティアゴへ、地球の表と裏を往還しながら、記者はふたりの数奇な人生を追う。 「めまいがしそうな夫婦の大逆転劇。結婚後、ここまで明暗が分かれた夫婦が、ほかにいるだろうか」(本書より) 犯罪史に残る巨額横領事件の渦中にいた「夫婦」の深淵に迫る、圧巻のノンフィクション。 【目次】 プロローグ 《Side A》 1 キャンディ 2 ウエディング・ベル 3 MONEY 4 少年時代 5 異邦人 6 ラヴ・イズ・オーヴァー 7 逃亡者 8 酒と泪と男と女 9 息子 10 逆流 11 碧い瞳のエリス 《Side B》 12 初恋 13 銃爪 14 津軽平野 15 Geisha 16 Yes‒No 17 失恋レストラン 18 腕に虹だけ 19 黒い瞳のアニータ エピローグ あとがき 付録