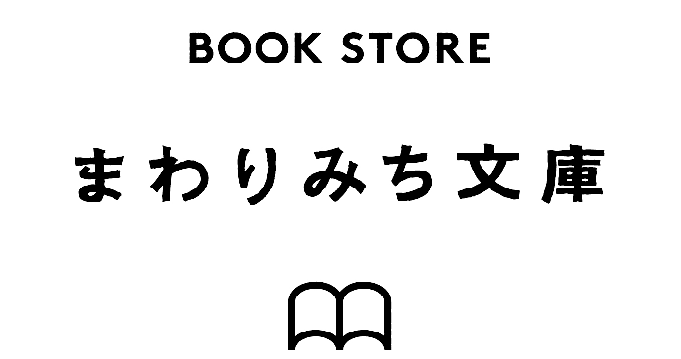-

オルタナティブ民俗学
¥1,980
著者:島村恭則/畑中章宏 発行元:誠光社 183ぺージ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 民俗学がオルタナティブ 民俗学のオルタナティブ 在野のネットワークを重視し、新たな記述法を模索、アカデミアが注目しない周縁や身の回りにこそ目を向けた、「未来の学問」を語り尽くす! 【目次】 まえがき 〔第一回〕柳田も折口もオルタナティブだ 〔第二回〕〈民間学〉としての民俗学 〔第三回〕〈東北〉〈沖縄〉は周縁か、中心か 〔第四回〕〈民俗学〉と〈民藝〉は、アートをどう捉えたか 〔第五回〕〈女〉の民俗学、〈性〉の民俗学 〔第六回〕民俗学の未来 あとがき
-

置き配的
¥2,310
著者:福尾匠 発行元:講談社 240ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* コロナ禍以降、社会は置き配的なものとなった―― 「紀伊國屋じんぶん大賞2025 読者と選ぶ人文書ベスト30」の1位に輝いた気鋭の批評家が放つ最初にして最高の2020年代社会批評! 群像連載の「言葉と物」を単行本化。酷薄な現代を生き抜くための必読書! 「外出を自粛し、Zoomで会議をし、外ではマスクを着け、ドアの前に荷物が置かれるのに気づくより早く、スマホで通知を受け取る。個々人の環境や選択とはべつに、そのような生活がある種の典型となった社会のなかで、何が抑圧され、何が新たな希望として開かれているのか。そうした観点から、人々のありうべきコミュニケーションのかたちを問うこと、それがこの本のテーマです。(中略) つまり、狭義の置き配が「届ける」ということの意味を変えたのだとすれば、置き配的なコミュニケーションにおいては「伝える」ということの意味が変わってしまったのだと言えます。そして現在、もっとも置き配的なコミュニケーションが幅を利かせている場所はSNS、とりわけツイッター(現X)でしょう。保守とリベラル、男性と女性、老人と若者、なんでもいいですが、読者のみなさんもいちどは、彼らの論争は本当に何かを論じ合っているのかと疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。 (中略)置き配的な社会を問うことは、書くことの意味を立ち上げなおすことにも直結するはずです。」(本文より) 【目次】 序文 第1回 郵便的、置き配的 第2回 出来事からの隔離生活、あるいは戦争の二重否定 第3回 「たんなるパフォーマンス」とは何か 第4回 ネットワークはなぜそう呼ばれるか 第5回 フーコーとドゥルーズの「言葉と物」/青森で石を砂にした話 第6回 いま、書くことについて 第7回 置き配写真論、あるいは「コンテンツ」時代の芸術作品 第8回 ポジションとアテンション 第9回 サイボーグじゃない、君は犬だ、と私は言う 第10回 私でなくもない者たちの親密圏 第11回 暴力的な平等性と創造的な非対称性 あとがき
-

なぜ人は締め切りを守れないのか
¥1,980
著者:難波優輝 発行元:堀之内出版 295ページ 188mm × 110mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 私たちは実のところ、「締め切り」のことをよく知らないまま生きている。 ときに私たちを苦め、ときに私たちを奮い立たせる「締め切り」とは何なのか? 「締め切り」から、現代社会に深く埋め込まれたルールを描き出し、豊かな生き方を探る哲学的冒険。 時間について:時間とはそもそも何なのか? 計画について:昔の人はもっとのんびり生きていた 仕事について:無理な要求から逃れる方法は? 死について:最大にして最後の締め切りを考える ●締め切りの間を縫って、私たちが〈いい時間〉を手に入れるために “残業によって得られる賃金は計算できる。さまざまな締め切りの集合体である「プロジェクト」は、時間を対価に成果を提示する。いっぽうで、愛する人と過ごす時間、趣味に没頭する時間の価値は計算が難しい。私たちは、〈いい時間〉を計量することができずにいるのだ──。” 【目次】 目次 序章 なぜ人は締め切りを守れないのか 第1章 いい時間とわるい時間──私たちはどんな「今」を生きたいのか? 第2章 プロジェクト──私たちから時間を奪うもの 第3章 生きている時間──私たちはいつも何かに間に合わない 第4章 いろいろな遊びの時間を旅する──時間の遊び論 第5章 いい時間をつくる──時間正義のためのデザイン 第6章 デッドライン──死から締め切りの本性を考える あとがき ブックガイド 新しい時間をデザインするために 参考文献
-

生類の思想 体液をめぐって
¥2,970
SOLD OUT
著者:藤原辰史 発行元:かたばみ書房 288ページ 188mm × 129mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 大気・海洋・土壌汚染、アレルギーの増加、免疫の不調、 日常化する暴力、子どもの商品化、奪われる睡眠時間……。 この世界の現実をどう捉えるか。 「人間」と「環境」を根源から定義しなおし、 ありえたかもしれないもうひとつの世界を描きだす。 世界の高速回転化と自己攻撃化にあらがう 驚くべき思考の集成。 【目次】 はしがき Ⅰ わずらう 体液をめぐる思考――生類の思想が編み直されるところ 慢性と急性――人文学的省察 「自己する」の不調――アレルギー時代の人文学的考察 Ⅱ あそぶ 家庭科の哲学――「人間する」を遊ぶ 墨色と泥色の記憶――かこさとしの絵の淡い濁りについて 子どもの商品化に抗する思想 いま環境について考えるとはどういうことか Ⅲ はぐくむ 農業技術への問い――ハイデガーの概念「はぐくむhegen」について 土の思想をめぐる考察――脱農本主義的なエコロジーのために さつまいもと帝国日本 賢治と道子をつなぐもの――「植物医師」と硫安 Ⅳ たべる 培養肉についての考察 食の闇について 人間チューブ論――食のダイナミズムを考える エディブル・プラネット Ⅴ まじる 「規則正しいレイプ」と地球の危機 表皮の脱領域的考察 もれる――膜が食い破られること 「たかり」の思想――食と性の分解論 あとがき
-

フォルモサ南方奇譚
¥2,750
著者:倉本知明 発行元:春秋社 368ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 日本軍に切り落とされた亀神の首、城壁にかけられた三百年のマジナイ、湖に暮らす龍の母子、祖霊が眠る山に隠された黄金郷。無縁仏の怨霊に異神、義民に逆賊、西洋の「文明人」と原住民の頭目、帝国の支配に抗して蜂起した匪賊……。 大国による支配の痕跡と土着の文化が絡み合う、神々の楽園・台湾のディープ・サウス。歴史と伝承の狭間にある数々の奇譚から、すでにないのにそこにある、台湾の「いま」へと迫る17章。各章末に怪談コラムを付す。〔カラー口絵16頁〕 【目次】 口絵 はじめに 1 羅漢門の皇帝陛下 遊園地の思い出 2 客家と仮黎(ガライ) よそ者たちが唱った故郷 墓地に響く歌声 3 清あるを知って日本あるを知らず 六堆客家興亡史 Y字路の怪談 4 左営旧城三百年のマジナイ 骨 5 高雄版ドラゴンクエスト 曹公と龍の母子たち 義賊と知県 6 伝説の黄金郷を探して 死者をのせたバス 7 浸水営古道クロニクル 忘れられた騒乱 祖霊の声 8 亡霊たちの眠る町 タイワンザルと博物学者 エレベーター前に立つ女鬼 9 荖濃渓サバイバル 帰ってきた紅毛の親戚と合従連衡するマイノリティ 集落を救った少年 10 瑯嶠八宝公主譚 カミさまとなったおひいさま 心に住む鬼 11 1871漂流民狂詩曲(ラプソディー) トイレの「小紅」さん 12 ワタシハダレ? 台湾出兵と忘れられた拉致事件 赤い目のパリ 13 「鬼」をもって神兵となす とある婚姻 14 神を燃やす 仏さまとなった羅漢脚 15 土匪と観音、ときどきパレスチナ ハリネズミになった男 16 フォルモサ水滸伝 媽祖VS玄天上帝 下淡水渓法力大合戦 17 生きべくんば農民と共に、死すべくんば農民のために 宙に浮く棺桶 主要参考文献
-

ヒップホップ・レザレクション ラップ・ミュージックとキリスト教
¥3,520
著者:山下壮起 発行元:新教出版社 264ページ 188mm × 150mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 反社会的な音楽文化としてしばしば非難の対象となってきたヒップホップは、なぜ繰り返し神や十字架について歌うのか――黒人神学の泰斗ジェイムズ・コーンの議論を継承し、アフリカ系アメリカ人の宗教史の文脈のなかでラッパーたちの声に耳を傾けながら、その秘めたる宗教性を浮かびあがらせる。ヒップホップの現場を知りつくした気鋭の神学者による、異色の歴史神学にしてヒップホップ研究の新たなクラシック。 著者の山下壮起氏は日本基督教団阿倍野教会牧師。同書のもととなった博士論文「ヒップホップの宗教的機能――アフリカ系アメリカ人ヒップホップ世代の宗教観」は、公益財団法人国際宗教研究所の2018年度国際宗教研究所賞奨励賞を受賞した。 【目次】 序章 第1章 Hip Hop Generation ヒップホップ・ジェネレーション ――ヒップホップの宗教性を生み出したもの 第2章 The Roots ザ・ルーツ ――アフリカ系アメリカ人の歴史と宗教 コラム1 新しい霊性 ネオ・スピリチュアリティ ――アフリカ系アメリカ人と宗教の多様性 第3章 Nothin’ But The Spiritual Thang ナッシン・バット・ザ・スピリチュアル・サング ――世俗音楽の宗教性と宗教音楽の限界 コラム2 ヒップホップ ――ローカルが示す生から聖へ 第4章 Holy State of Mind ホーリー・ステイト・オブ・マインド ――聖俗二元論を超えて 結論 Bonus Track ヒップホップという言語
-

私が諸島である カリブ海思想入門
¥2,530
著者:中村達 発行元:書肆侃侃房 344ページ 195mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「なぜハイデガーやラカンでなければならない? 僕たちにだって思想や理論はあるんだ」 カリブ海思想について新たな見取り図をえがく初の本格的な入門書。 西洋列強による植民地支配の結果、カリブ海の島々は英語圏、フランス語圏、スペイン語圏、オランダ語圏と複数の言語圏に分かれてしまった。それらの国々をそれぞれ孤立したものとしてではなく、諸島として見るということ。カリブ海をひとつの世界として認識し、その独自の思想を体系化する画期的著作。これからのカリブ海思想研究のためのリーディングリストを付す。 「web侃づめ」の大好評連載が大幅増補され、ついに書籍化! この海の下で我々は手を取り合う━━。カリブ海思想研究の俊英による待望のデビュー作。 【目次】 序章 冒険の季節 第1章 ひとつの世界としてのカリブ海 第2章 1492を越えて、人間であること 解呪の詩学 第3章 カリブ海を定義する者へ 存在論的不純性 第4章 神話とカリブ海 悲しくも希望に満ちた叙事詩 第5章 出会いを押し進めるために 相互歓待 第6章 カリブ海の社会モデル論 プランテーション、多元、クレオール 第7章 環カリブ海的経験のクレオライゼーション この海の下で我々は手を取り合う 第8章 カリブ海によるクレオール的時政学 海が歴史である 第9章 ミサイルとカプセル 円環性の実践としての弁潮法 第10章 ニヒリズムに抗うクロス・カルチュラルな想像力 カリブ海的身体と幻肢 第11章 カリブ海のポストモダンの地平 カリビアン・カオス(前編) 第12章 カリブ海のポストモダンの地平 カリビアン・カオス(後編) 第13章 押し付けられた言語は誰の存在の家か 私ー像を描く言語 第14章 クレオール礼賛の裏で カリビアン・フェミニズム 第15章 クレオールの精神 カリビアン・クィア・スタディーズ 終わりに 参考文献 カリブ海思想研究リーディングリスト
-

啓蒙の海賊たち あるいは実在したリバタリアの物語
¥2,640
著者:デヴィッド・グレーバー 訳者:酒井隆史 発行元:岩波書店 230ページ 195mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 西洋なんて存在しなかった?──近代知の起源とされる「啓蒙思想」は、ヨーロッパ貴族のサロンではなく、じつはマダガスカルの海賊と女性たちの社会実験によって創造されたのではないか。海賊王国の知湧き心躍る「本当の」歴史をたどり直し、自由、国家、民主主義をめぐる無数の常識をくつがえす。グレーバー生前最後の著作。 【目次】 序 文 (とびきり)ラディカルな啓蒙主義 第一部 マダガスカル北東部の海賊と偽王 海賊がマダガスカルにやってきた 掠奪品の問題 サントマリーの実体経済 実在のリバタリアⅠ──アンブナヴラ さらなる偽王、ジョン・プランタン 年代にかんするいくつかの問題 第二部 マダガスカル人の目に映った海賊の来訪 アブラハムの子孫たちに抗する性革命? 政治のコマとしての女性 女商人と魔法のお守り 家内の諸事象 軍事的権力と性的権力の対立について 第三部 海賊の啓蒙 発端の状況 最初の挑戦 大カバリ 誓約儀礼 王になったラツィミラフ 英雄たちの戦い 宮廷と王国、そしてザナマラタの台頭 結 論 実在のリバタリアⅡ──ベツィミサラカ連合 地 図 海賊と啓蒙の時系列 訳者あとがき 文献注 参考文献
-

かずをはぐくむ
¥1,980
SOLD OUT
著者:森田真生 絵:西淑 発行元:福音館書店 216ページ 200mm × 140mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 子どもと共に探し、育む、「数」の世界 「生まれたばかりの息子を初めて腕に抱いたとき、いつか彼が数をかぞえたり計算をしたりする日が来るとは、まだとても信じられなかった。言葉もない、概念もないのだ」(本書より)。 しかし、やがて、子どもの心の中には数が“生まれ”、おとなと共に“育み”あうようになる。3歳と0歳のきょうだいが、8歳と5歳になるまでの驚きに満ちた日々。独立研究者、森田真生があたたかく見守り、やわらかに綴る。画家、西淑による挿絵もふんだんに掲載。
-

アンチ・アンチエイジングの思想 ボーヴォワール『老い』を読む
¥2,970
著者:上野千鶴子 発行元:みすず書房 328ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 老いには誰も抗えない。それなのに、私たちはなぜ老いを恐れるのだろう。平均寿命が延び、老人としての生が長くなったことで、誰もが老いに直面すると同時に不安も高まっている。 自分が老いたことを認めたくないのは、社会が老いを認めないからだ。それを惨めにしているのは文明のほうなのだ。「老いは文明のスキャンダルである」――この言葉に導かれて、ボーヴォワール『老い』への探究がはじまる。 さらに日本の介護の現場を考察し、ボーヴォワールのみた景色の先へと進む。認知症への恐怖、ピンピンコロリという理想、安楽死という死の権利。その裏側にある老いへの否定から見えてくるのは、弱いまま尊厳をもって生ききるための思想がぜひとも必要だということだ。 ひとが最後の最後まで人間らしく生きるには、徹底的な社会の変革が必要なのだ。 老いて弱くなることを否定する「アンチエイジング」にアンチをとなえ、老い衰え、自立を失った人間が生きる社会を構想する。 【目次】 第1章 老いは文明のスキャンダルである 第2章 文化の中の老い 第3章 歴史の中の老い 第4章 近代化の中の老い 第5章 「生きられた経験」としての老い 第6章 知識人の老い 第7章 老いと性 第8章 女性の老い 第9章 高齢者福祉の起源 第10章 ボケ老人へ向ける眼 第11章 アンチ・エイジズム 第12章 三つの死 第13章 「死の自己決定」はあるか 第14章 ボーヴォワールの「宿題」 第15章 「自立神話」を超えて 引用・参照文献 ボーヴォワール略年譜 あとがき
-

いっしょにいきるって、なに? [新版](こども哲学)
¥1,760
SOLD OUT
著者:オスカー・ブルニフィエ 訳者:西宮かおり 監修:重松清 絵:フレデリック・ベナグリア 発行元:朝日出版社 104ページ 235mm × 183mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** こどもの素朴な「 なぜ? 」は、世界から感じとった不思議をそのまま口に出すもの。大人としては、つい、「そういうものなんだよ」と反応してしまいそうになります。でも、そういう気持ちや不思議さは、既成のことばでは、解決できません。そして、いつでも使える「答え」がないことが、ほとんどです。 本書は、そんなこどもの疑問、大人にとっても超難問の、根源的に大切な問題を、楽しく考えるシリーズです。絵本の中で次々と出会う考え方に、賛成したり、反対したり、その理由を考えたり。家族で、学校で、語り合いながら、新たなページを加えていってください。 考えることは、こどものおもちゃ! ◆この本の6つのテーマ ひとり: ひとりっきりで、生きてゆきたい? そんちょう: どんなときでも、みんなをだいじにするべき? 意見: いつも、みんなとおなじ考え? 平等: ぼくたち、みんな平等? しごと: ぼくたちみんな、はたらかなくちゃいけないの? リーダー: みんなでいっしょに生きてゆくには、リーダーとルールが必要?
-

人生って、なに?[新版](こども哲学)
¥1,760
SOLD OUT
著者:オスカー・ブルニフィエ 訳者:西宮かおり 監修:重松清 絵:ジェローム・リュイエ 発行元:朝日出版社 104ページ 235mm × 183mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** こどもの素朴な「 なぜ? 」は、世界から感じとった不思議をそのまま口に出すもの。大人としては、つい、「そういうものなんだよ」と反応してしまいそうになります。でも、そういう気持ちや不思議さは、既成のことばでは、解決できません。そして、いつでも使える「答え」がないことが、ほとんどです。 本書は、そんなこどもの疑問、大人にとっても超難問の、根源的に大切な問題を、楽しく考えるシリーズです。絵本の中で次々と出会う考え方に、賛成したり、反対したり、その理由を考えたり。家族で、学校で、語り合いながら、新たなページを加えていってください。 考えることは、こどものおもちゃ! ◆この本の6つのテーマ しあわせ: しあわせっておもうのは、どんなとき? 将来のゆめ: いつか、いちばんになれるかな? 不幸: 人生って、なんでつらいんだろう? 存在: どうして、人間は存在するの? 人生の意味: ぼくたち、なんで生きてるの? 死: どうして、ひとは死ぬの?
-

アリの放浪記 多様な個が生み出す驚くべき社会
¥3,190
SOLD OUT
著者:オドレー・デュストゥール/アントワーヌ・ヴィストラール 訳者:丸山 亮 監修:丸山 宗利 発行元:山と渓谷社 408ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** いざ、アリの眼から見る世界へ! あなたが一匹のアリを踏みつぶしたとき、一遍の叙事詩が終わりを告げる。 世界的アリの研究者二人による全仏ベストセラー 本書は、地球上に2万種存在するともいわれているアリの専門家であるオドレー・デュストゥールとアントワーヌ・ヴィストラールの二人が、アリの魅惑的な社会生活を紹介した、わくわくするようなアリの一大放浪記だ。 焦点を当てるのは、個体の5~10%しかいない巣の外に出て食べ物を探し求めるアリ「採餌アリ」で、コロニー全体の食料供給を担っている。そのアリたちは、クロールで水辺を渡る水泳選手、仲間を救助し治療する看護師、地下でキノコを栽培する造園家、敵を巻き込んで自爆する特攻隊、空中を舞って落下するグライダー部隊などなど、とても多様な社会的カテゴリを有する。 アリたちの視点で世界を見ることで、自分たちの社会構造や自然との付き合い方を問い直す一冊だ。 【目次】 はじめに 序章 放浪記のヒロインたち/コロニー、超個体、集合知 第一の試練 巣を出て、方向を見定める 森の呼び声/ダーティ・ダンシング/われを慕うものはわれに従え/道をたどる/悪銭身につかず? 第二の試練 食糧を見つけ出す 芳香/プレデター/無慈悲な襲撃/待ち伏せ/罠 第三の試練 食糧を育てる 恵みの収穫/キノコひとすじ/善悪の園/危険な関係/愛と宿命の泉/潜水服は蝶の夢を見る 第四の試練 食糧を運ぶ 重量挙げ/指輪の仲間/悪魔のいけにえ/盗まれた口づけ/現金輸送車/ハチミツとスポンジ 第五の試練 環境に適応する 砂丘/風と共に去りぬ/流れに逆らって/メデューズ号のいかだ/二つの岸を結ぶ橋/大都市(メトロポリス) 第六の試練 他者を利用する 寄生虫/ストックホルム症候群 第七の試練 縄張りを守る 身近な敵/無蟻地帯(ノー・アンツ・ランド)/ファイトクラブ 第八の試練 外敵から身を守る スカイフォール/ジョーズ/鬼の訪問/カミカゼ/生ける屍 第九の試練 攻撃する・反撃する 恐れ慄いて/ロボコップ/人食いハンニバル 第一〇の試練 選択し、最適化する アリアドネの糸/オン・ザ・ロード・アゲイン/二車線道路/栄光の道 第一一の試練 救助し、治療する ライフガード/パルナサス博士の鏡 最後の試練 死 死につきまとわれて おわりに 翻訳家あとがき 参考文献
-

世界史の構造(岩波現代文庫/学術 323)
¥900
SOLD OUT
著者:柄谷行人 発行元:岩波書店 発行年:2015年2月15日 第2刷 543ページ 文庫判 148mm × 105mm 【状態】 小口に汚れ(写真2枚目) それ以外に目立った汚れや傷みはありません。 ※こちらの商品は店頭でも販売しております。品切れの場合もございますので予めご了承くださいませ。
-

〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィー ヤンキーの生活世界を描き出す
¥2,640
著者:知念渉 発行年:青弓社 276ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** ヤンキーは何を考え、どのようにして大人になるのか――。 高校で〈ヤンチャな子ら〉と3年間をともに過ごし、高校を中退/卒業してからも継続して話を聞いて、集団の内部の亀裂や、地域・学校・家族との軋轢、社会関係を駆使して生き抜く実際の姿を照らす。 【目次】 序 章 〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィーに向けて 1 巷にあふれる「ヤンキー語り」と調査の不在 2 〈ヤンチャな子ら〉を調査・研究する意義 3 本書の目的と独自性 4 調査の概要 5 本書の構成 第1章 ヤンキーはどのように語られてきたのか 1 若者文化としてのヤンキー 2 生徒文化としてのヤンキー 3 階層文化としてのヤンキー 4 これまでのヤンキー研究の課題 5 分析の方針 第2章 〈ヤンチャな子ら〉の学校経験――教師との関係に着目して 1 〈ヤンチャな子ら〉と教師の対立? 2 学校文化の三つのレベル 3 家庭の文化と学校文化の葛藤 4 〈ヤンチャな子ら〉と教師の相互交渉 5 教師への肯定的評価と学校からの離脱 6 〈ヤンチャな子ら〉と「現場の教授学」 第3章 〈ヤンチャな子ら〉とは誰か――〈インキャラ〉という言葉に着目して 1 集団の曖昧さ 2 類型論的アプローチを超えて 3 〈インキャラ〉という解釈枠組み 4 文脈のなかの〈インキャラ〉 5 〈インキャラ〉という解釈枠組みのゆらぎ? 6 集団の内部の階層性 第4章 「貧困家族であること」のリアリティ 1 「子ども・若者の貧困」研究における本章の位置づけ 2 「記述の実践としての家族」という視点 3 記述の実践としての「貧困家族」 4 アイデンティティとしての家族経験 第5章 学校から労働市場へ 1 〈ヤンチャな子ら〉の仕事への移行経路 2 〈ヤンチャな子ら〉の移行経験――六人の語りから 3 移行経路と社会的ネットワーク 終 章 〈ヤンチャな子ら〉の移行過程からみえてきたこと 1 〈ヤンチャな子ら〉集団内部にある「社会的亀裂」 2 重層的な力学のなかにヤンキーを位置づけた意義 3 「ヤンキー」と括られる人々の内部に目を向けることの重要性 4 アンダークラスとしてカテゴリー化することの危険性 5 〈貧困の文化〉か、〈社会的孤立〉か 6 社会関係の編み直しに向けて 巻末資料 参考文献 初出一覧 あとがき
-

庭の話
¥3,080
著者:宇野常寛 発行元:講談社 368ページ 195mm × 140mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** *プラットフォーム資本主義と人間との関係はどうあるべきなのか? ケア、民藝、パターン・ランゲージ、中動態、そして「作庭」。一見無関係なさまざまな分野の知見を総動員してプラットフォームでも、コモンズでもない「庭」と呼ばれるあらたな公共空間のモデルを構想する。『遅いインターネット』から4年、疫病と戦争を経たこの時代にもっとも切実に求められている、情報技術が失わせたものを回復するための智慧がここに。 【目次】 #1 プラットフォームから「庭」へ #2 「動いている庭」と多自然ガーデニング #3 「庭」の条件 #4 「ムジナの庭」と事物のコレクティフ #5 ケアから民藝へ、民藝からパターン・ランゲージへ #6 「浪費」から「制作」へ #7 すでに回復されている「中動態の世界」 #8 「家」から「庭」へ #9 孤独について #10 コモンズから(プラットフォームではなく)「庭」へ #11 戦争と一人の女、疫病と一人の男 #12 弱い自立 #13 消費から制作へ #14 「庭の条件」から「人間の条件」へ
-

人類の会話のための哲学 ローティと21世紀のプラグマティズム
¥4,180
SOLD OUT
著者:朱喜哲 発行元:よはく舎 284ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ローティという不世出の哲学者を、〈人類の会話〉の守護者であろうとし続けた人物として再発見する。」朱喜哲は、混沌とした現在の日本・世界でローティが注目されるべき意味を鮮やかに記した。 古代ギリシア以来の伝統につらなる哲学を筆頭として「唯一の真正な声」を求める営みは、ひとびとの小さな声をつぐませる。 「雑多で多様な複数の声たち」、その会話こそが人類が豊かに暮らす希望ではないか。 哲学者ローティは多くの批判を引き受けながら、その声たちを守ることこそを哲学の任務として引き受けた。 本書は、第一部はミサック、第二部はセラーズ、第三部はブランダムを中心的に扱うことで、先行研究から後世の視点も含め包括的なローティ像を描き出している。 また、同時に現代的な意義、政治や社会の状況に対してどのように参照しうるのかを明らかにした。こうしてローティの思想を中心にプラグマティズムの意義が明らかにしていくことで、本書は古典から未来へ繋がる哲学の姿をも希望をもって浮かび上がらせる。
-

生きるのが楽になるスヌーピー 心をゆるめてくれる禅の言葉
¥1,540
著者:チャールズ・M・シュルツ 訳者:谷川俊太郎 監修:枡野俊明 発行元:光文社 192ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 店主コメント *********************** 『ピーナッツ』のワンシーンや登場人物のセリフから「禅に通じるもの」を見出し、禅の言葉を解説するシリーズ第3弾。 物事の真理は身近な自然の風景にありのままの姿で存在し、人間もまたその一部であることを教えてくれます。複雑化した社会で忘れがちな自然体を意識することは、きっと自身の生きやすさにつながるのではないでしょうか。 【目次】 Part1 サンデー版で読む禅語 前を向くための言葉 Part2 サンデー版で読む禅語 心をゆるめる言葉 Part3 春夏秋冬を過ごす 禅語×ピーナッツコミック
-

自分を受け入れるスヌーピー いろいろある世界を肯定する禅の言葉
¥1,540
SOLD OUT
著者:チャールズ・M・シュルツ 訳者:谷川俊太郎 監修:枡野俊明 192ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 店主コメント *********************** 『ピーナッツ』のワンシーンや登場人物のセリフから「禅に通じるもの」を見出し、禅の言葉を解説するシリーズ第2弾。 自分のカラーを見つけ、それぞれのカラーを認める。互いに尊重し合う多様性の認識へと導いてくれる禅の言葉が詰まった一冊です。巻末にはシュルツ・スタジオからのメッセージが詰まったイラスト集「COLOR OF PEANUTS」を掲載。 【目次】 Part1 自分のCOLORを見つけて Part2 それぞれのCOLORをみとめる Part3 COLOR OF PEANUTS
-

死すべき定め 死にゆく人に何ができるか
¥3,080
SOLD OUT
著者:アトゥール・ガワンデ 訳者:原井宏明 発行元:みすず書房 312ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 今日、医学は人類史上かつてないほど人の命を救えるようになった。しかし同時に、人はがんなどの重篤な病いと闘う機会が増え、寿命が飛躍的に延びた。老人ホームやホスピスなど家族以外の人々も終末期に関わるようになり、死との向き合い方そのものが変わってしまったのである。この「新しい終末期」において、医師やまわりの人々、そして死にゆく人に何ができるのだろうか? インドの田舎町で長老として過ごすおじいさん、子供と離れて一人で都会的な生活を送るおばあさん、母親になってすぐに末期がんと向き合う女性……。本書の著者アトゥール・ガワンデは、外科医としていくつもの最期の決断に立ち会い、家族として決断に迫られる。ガワンデが直面する医療にできること、できないこととは——。 現役外科医にして「ニューヨーカー」誌のライターである著者が描く、迫真の人間ドラマ。人生の終盤をよりよくするために奔走した人々のエピソードが圧倒的な取材力と構成力で綴られた本書は、読む者に自らの終末期の選択について多くの問いを投げかけるだろう。 終末期をどう生き、最期の時をどう迎えるのか。私たちは豊かに生きることに精いっぱいで、「豊かに死ぬ」ために必要なことを、こんなにも知らない——。 【目次】 序 1 自立した自己 2 形あるものは崩れ落ちる 3 依存 4 援助 5 よりよい生活 6 定めに任せる 7 厳しい会話 8 勇気 エピローグ *********************** 店主コメント *********************** フレイル(衰弱状態)によって一人暮らしがままならない高齢者や難病を患う終末期患者に対する医療とケアのあり方を考えるルポルタージュ。 老化や病の進行と共に必要になってくる依存と援助。生命の限界が見えつつあるとき、その人は「自律」した生活を望むことはできないのか?現役の医師である著者が、これまでに関わった患者や彼らを支援する職員たちとの出会いによって見出した死生観を読者に提示する。 医師から提案された治療の選択に苦悩する患者と家族、新たな支援の試みに奮闘する職員など人物背景が丹念に書かれているので感情移入しながら読むことができます。 決して他人ごとではない現実と向き合う読み応え十分の一冊です。
-

土と脂 微生物が回すフードシステム
¥3,520
SOLD OUT
著者:デイビッド・モントゴメリー/アン・ビクレー 訳者:片岡夏実 発行元:築地書館 416ページ 195mm × 138mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 今も売れているベストセラー『土と内臓』の著者による最新作!! 内臓にある味覚細胞、健康な土、 身体に良い脂肪・悪い脂肪から、コンビニ食の下に隠された飢餓まで、 土にいのちを、作物に栄養を取り戻し、食べものと身体の見方が変わる本。 前著に続き、目からうろこが落ちる記述が満載! ◎相乗的に作用しあうファイトケミカル、ミネラル、脂肪。 ◎植物は、体外に胃袋を持つ。 外部の胃袋としての根圏マイクロバイオームによって、体外で消化を行うのだ。 ◎非菌根型菌類は有機物を分解し、植物が吸収できる形で栄養を放出する。 ◎育種のベクトルを、収量から菌根菌、細菌との協力関係にシフトさせる。 ◎農業政策は、公衆衛生と医療の重要な一分野。 【目次】 序章 「土壌の健康が食物の質に影響する」は本当か? 土壌生物がもたらす作物の健康 健康な土と良い食べものをつなぐ科学的な根拠 ジャンクフードの下に隠された飢餓 第1章 健康というパズルの重要なピース 食べものの役割に関心が薄い医学 「正しい食べもの」がかつて含んでいた栄養 収量という罠 隠れた飢餓─親より寿命が短くなるアメリカ人 食べものの栄養素密度を予防医学として考える 土壌の健康を通して農法を考える 土 SOIL 第2章 人は岩でできている 店頭のニンジンとホウレンソウの栄養価 岩を食べた植物を食べる人間 植物の生長と健康を支える極小のパートナー 土壌微生物の植物学的重要性に気づく 微生物は日和見主義の政治的同盟者 品種改良によるミネラル低下 単純な実験─ミネラルを土から作物へ運ぶ微生物の育て方 第3章 生きている土 食べものを疑ったイギリス人 農業慣行がつくる作物の健康と食品の栄養価 非現実的な神秘主義と合理的思考 緑の女王バルフォア 自分の農場を一大実験場に 有機農地のウシとニワトリ 微生物生態学の進歩が明かしたバルフォアの洞察の正しさ 第4章 慣行農業の行きづまり 土壌の健康は世代を超えた信託物 耕起による土壌生態系の破壊 耕起がもたらす菌根菌・細菌へのインパクト 土壌のジャンクフード─窒素肥料 植物の防御システムを解除する化学肥料 はびこる問題15年で広がった除草剤耐性雑草 グリホサート─鉱物元素を奪い植物を枯らす もう一つの道─土づくりから始める 第5章 農民の医師 植物の根と菌根菌 作物の健康は菌類と腐植で成り立つ ビタミンBを含まない化学肥料施肥の種 全粉粒パンには鉄が3倍、ビタミンBが7倍 白米の普及と脚気、2型糖尿病 手がかりを追って 戦時中に英国人の食事を変えた科学者 野菜や飲料水を汚染する硝酸塩 大量の窒素施肥がもたらすもの 植物 PLANT 第6章 植物の身体 土がなくても作れる有機作物? 植物の錬金術師─ファイトケミカル 作物の生長・収量と健康を混同する研究者 議論が終わらない理由 ファイトケミカルが有意に多い有機作物 農法による収量差と収益性 第7章 偉大なる園芸家 私たちの手作り野菜の栄養組成 タバコ・ロード農場の不耕起集約的野菜栽培 裸地を作らず、常に何かを栽培する キノコが生える畑─森から土を入れる 歌うカエル(シンギング・フロッグズ)農場─アグロフォレストリーの野外実験 固定資産税を支払うため、不耕起栽培で年3回収穫 不耕起─土壌からの窒素流亡が起こらないわけ 慣行ブドウ園との土壌比較 土づくり─畑の生命の躍動を見守る 成功事例を小規模農場で再現する 第8章 堆肥が育てる地下社会 農業コンサルタントへの疑問 土壌比較調査 堆肥の力 ジョンソン=スー・バイオリアクターの発明 生産性をつかさどる菌類・細菌比 多様な菌類群集の速い推移 高まる関心 第9章 多様な植物由来の見過ごされた宝石 ワシントン大学薬草園 ファイトケミカルの種類は5万種 フラボノイド、カロテノイド、フェノール ヒト細胞を浄化する抗酸化物質 抗酸化物質含有食品を健康のために食べる 食べる薬 薬理効果とトマト、チョコレート 動物 ANIMAL 第10章 沈黙の畑 農薬への曝露 農家以外の農薬曝露は食事から 害虫への対抗手段としてのファイトケミカル 抵抗の根─多様性で病害虫防除 農務省を辞めて自分で研究農場を始めた昆虫学者 昆虫群衆の相互関係 農学の研究制度の壊滅を思い知る そろそろ変わるときだ 生き物の賑わいが戻った研究農場 第11章 地の脂 マイクロバイオームの大部分を収めた生態系 脂肪が人体を支配する 地の脂が乳となり人間になる トウモロコシを食べるウシ 食餌で変わる牛乳の中身 オメガ6と共役リノール酸 バターとチーズとファイトケミカル 乳牛の健康問題 第12章 肉の中身 脂肪悪玉説のはじまり 食事─心臓仮説がもたらした混乱 肉について考える イヌイット食の謎の脂肪 アザラシ肉に匹敵するDPAの摂取源 草を食わせろ 肥育場病─食餌と生活環境が引き起こすもの 第13章 身体の知恵 多種を少量ずつ食べる草食動物 草と牛─マルチパドック輪換放牧を生んだ着想 土壌中のミネラルバランスに注目する 野生動物が知っている薬効植物 身体の知恵の3本の柱 味のフィードバック、もしくは植物と踊るダイナミックなダンス 平均という問題─費用対効果の真実 正常な満腹信号を歪める食味増強剤 永続する多様性─適応と回復力を生む群れの中の変わり者 人間 PEOPLE 第14章 健康の味 脳のそばの隠された細胞 味は単色タイル、風味は複雑なモザイク 腸内の神経細胞にもある味覚受容体 喉にある苦味受容体の役割 壊れた羅針盤─身体の知恵を狂わせる甘味、塩味、うま味 食の相乗効果 栄養研究の難しさ 健康のための食事指針は、食べものが何を食べてきたのかを考えない 第15章 バランスの問題 『美味礼讃』が伝えたかったこと 低脂肪食品の効能は薄い─ボーイング社員で徹底研究 よい脂肪、共役リノール酸 太古の脂肪 炎症のバランスを取る脂肪 オメガ3とオメガ6のバランスのよい蓄え オメガ3サプリの効果 脂肪と心の健康 日本食の評価 第16章 作物に栄養を取り戻す 本場フランスのバゲットがおいしくなかった理由 パン研究所で学ぶコムギ製粉の歴史 コムギの育種─貯蔵寿命と収量の最大化 世界から集めた1000種類のコムギ 必要な多様性がすべて揃った畑 化学肥料を与えない畑に合うコムギの育種 穀物に足りないもの─栄養より収量でいいのか 近代の品種と古代の品種 食べものに栄養を取り戻す 主要作物の復活─SRIによるコメ栽培 第17章 畑の薬 超加工食品を食べない人々の歯はなぜ健康か 伝統食と栄養 健康のための農業 栄養素欠乏が引き起こすもの 菌類からの化合物の活躍 新しい栄養学のススメ 食の多様性 第18章 健康を収穫する 土地をどう扱うかで人間の健康が決まる 新たな方向性─土壌に必要な生物も育てる農業 選択肢は慣行農法か有機か、ではない 不耕起、被覆作物、多様な作物の輪作で1セット 未来の農業 未来の選択─農業のやり方が人間のありようを形作る 謝辞 訳者あとがき 参考文献 索引
-

土と内臓 微生物がつくる世界
¥2,970
著者:デイビッド・モントゴメリー/アン・ビクレー 訳者:片岡夏実 発行元:築地書館 392ページ 195mm × 138mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 肥満、アレルギー、コメ、ジャガイモ―― みんな微生物が作り出していた! 植物の根と、人の内臓は、豊かな微生物生態圏の中で、 同じ働き方をしている。 マイクロバイオーム研究で解き明かされた人体での驚くべき微生物の働きと、 土壌根圏での微生物相の働きによる豊かな農業とガーデニング。 農地と私たちの内臓にすむ微生物への、医学、農学による無差別攻撃の正当性を疑い、 地質学者と生物学者が微生物研究と人間の歴史を振り返る。 微生物理解によって、たべもの、医療、私達自身の体への見方が変わる本。 【目次】 はじめに――農地と土壌と私たちのからだに棲む微生物への無差別攻撃の正当性が疑われている 第1章 庭から見えた、生命の車輪を回す小宇宙 死んだ土 堆肥を集める 夢にみた庭づくり 夏の日照りと冬の大雨 スターバックスのコーヒーかすと動物園の糞 手品のように消える有機物 花開く土壌生物の世界 5年間でできた沃野 庭から見えた「自然の隠れた半分」旅する胞子 第2章 高層大気から胃の中までどこにでもいる微生物 どこにでもいる微生物 生き続ける原始生物 遺伝子の水平伝播もしくはセックスによらない遺伝的乱交 牛力発電度 第3章 生命の探究生物のほとんどは微生物 名前――リンネの分類法 ちっぽけな動物たち――顕微鏡の発見 発酵する才能――パスツールが開いた扉 生命の木を揺さぶる手――ウーズの発見 ウイルスの分類 第4章 協力しあう微生物 なぜ「種」という概念が疑わしくなるのか 微生物の共生 細胞の一部でありながら一部ではない――ミトコンドリアと葉緑体 マーギュリスとグールド シンビオジェネシス――別個の微生物が合体する 生命の組み立て 第5章 土との戦争 氷期のあとで 光合成の発見 最少律 小さな魔法使い 還元の原則――ハーバーボッシュ法とハワードの実践的実験 化学肥料はステロイド剤 触媒としての微生物 「農業聖典」とアジアの小規模農業 土壌の肥沃度についてのパラダイムシフト 第二次大戦と化学肥料工場マッシュルーム栽培の始まり 第6章 地下の協力者の複雑なはたらき 土中の犬といそがしい細菌 太古のルーツ 根圏と微生物 食べ物の力 植物と根圏微生物の多彩な相互作用 菌類を呼ぶ――植物と菌類のコミュニケーション 沈黙のパートナー――土壌生態学が解明する地下の共生・共進化著者のつぶやき 第7章 ヒトの大腸微生物と免疫系の中心地 がんが見つかる 手術後に考えたこと――がんと食生活 サケの遡上と川の環境 コーヒーとスコーンの朝食 がん予防の食事――ハイジの皿 美食の海で溺れる 食事をラディカルに見直す ヒトマイクロバイオーム・プロジェクト 人体の中の微生物 大腸はなぜ免疫系の中心なのか 第8章 体内の自然 減った病気と増えた病気 免疫の二面性 過ぎたるはなお 二つの免疫 恐れ知らずの探検家 抗原という言語 炎症のバランス 微生物の協力者 共生生物の種 バクテロイデス・フラギリスの奇妙な事例 ちょうどよい炎症 太古からの味方癌の治療法はすでに存在している 第9章 見えない敵細菌、ウイルス、原生生物と伝染病然 ポリオ 天然痘 センメルワイス反射 第10章 反目する救世主コッホとパスツール シルクとパスツール 顕微鏡とコッホ 細菌の分離 細菌論のルーツ――培養できる微生物に限定される 奇跡の薬 奇跡の値段 第11章 大腸の微生物相を変える実験 内側からの毒――腸内微生物と肥満 脂肪の二つの役割 腸内細菌相の移植 消化経路――胃・小腸・大腸の役割 ゴミを黄金に――大腸での発酵細菌の活躍 第12章 体内の庭 プレバイオティクス 婦人科医療と細菌のはたらき 糞便微生物移植の効果 穀物の問題――完全だった栄養パッケージをばらばらにする 内なる雑食動物躍 食生活を変えて腸内の微生物ガーデニングを意識する 第13章 ヒトの消化管をひっくり返すと植物の根と同じ働き 自然の預言者 減った栄養素 諸刃の遺産 ミクロの肥料 見えない境界線――根と大腸は同じはたらき 第14章 土壌の健康と人間の健康おわりにかえて 謝辞 訳者あとがき キーワード解説 (巻末より)原註 参考文献 索引
-

反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー
¥4,180
SOLD OUT
著者:ジェームズ・C・スコット 訳者:立木勝 発行元:みすず書房 296ぺージ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ある感覚が要求してくる——わたしたちが定住し、穀物を栽培し、家畜を育てながら、現在国家とよんでいる新奇な制度によって支配される「臣民」となった経緯を知るために、深層史(ディープ・ヒストリー)を探れ、と…」 ティグリス=ユーフラテス川の流域に国家が生まれたのが、作物栽培と定住が始まってから4000年以上もあとだったのはなぜだろうか? 著者は「ホモ・サピエンスは待ちかねたように腰を落ち着けて永住し、数十万年におよぶ移動と周期的転居の生活を喜んで終わらせた」のではないと論じる。 キーワードは動植物、人間の〈飼い馴らし〉だ。それは「動植物の遺伝子構造と形態を変えてしまった。非常に人工的な環境が生まれ、そこにダーウィン的な選択圧が働いて、新しい適応が進んだ…人類もまた狭い空間への閉じこめによって、過密状態によって、身体活動や社会組織のパターンの変化によって、飼い馴らされてきた」 最初期の国家で非エリート層にのしかかった負担とは? 国家形成における穀物の役割とは? 農業国家による強制の手法と、その脆弱さとは? 考古学、人類学などの最新成果をもとに、壮大な仮説を提示する。 【目次】 はじめに 序章 ほころびだらけの物語——わたしの知らなかったこと 国家と文明の物語のパラドックス/国家の正しい位置づけ/手短な行程表 1 火と植物と動物と……そしてわたしたちの飼い馴らし 火/集中と定住——湿地仮説/湿地と定住/なぜ無視されてきたのか/ギャップに注目する/そもそもなぜ植えるのか 2 世界の景観修正——ドムス複合体 新石器時代の植え付けから百花繚乱へ——耕作の影響/進化のモジュールとしてのドムス/狩猟民の獲物から農民の囲い物へ/人間の類似点に関する推論/わたしたちの家畜化 3 動物原性感染症——病理学のパーフェクトストーム 苦役とその歴史/後期新石器時代複数種再定住キャンプ——病理学のパーフェクトストーム/多産と人口に関する注釈 4 初期国家の農業生態系 国家作りの農業地理/穀物が国家を作る/壁が国家を作る——防御と閉じこめ/文字が国家を作る——記録と識字力 5 人口の管理——束縛と戦争 国家と奴隷制/メソポタミアの奴隷制と束縛/エジプトと中国/「人的資源」戦略としての奴隷制/略奪的資本主義と国家建設/メソポタミアの奴隷制および束縛の特殊性/飼い馴らしと重労働と奴隷制に関する推測的覚書 6 初期国家の脆弱さ——分解としての崩壊 初期国家の罹患率——急性疾患と慢性疾患/病気——過度の定住、移動、国家/環境破壊——森林破壊と塩類化/政体の消滅——戦争とコアの搾取/崩壊万歳 7 野蛮人の黄金時代 文明とその野蛮な周辺部/野蛮人の地理、野蛮人の生態系/略奪/交易ルートと課税可能な穀物コア/闇の双生児/黄金時代だったのか? 索引/原注/参考文献
-

哺乳類の興隆史 恐竜の陰を出て、新たな覇者になるまで
¥4,290
著者:スティーブ・ブルサッテ 訳者:黒川耕大 日本語ば版監修:土屋健 発行元:みすず書房 496ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 約3億年前に爬虫類の祖先と分かれたグループが、幾多の絶滅事件を乗り越えて私たちに至るまでの、途方もない歴史を描く書。 今、地球には約6000種の哺乳類が生息している。この動物たちは、哺乳類というグループが織りなしてきた豊かな系統樹のごくごく一部にすぎない。過去には、車のような大きさのアルマジロ、犬のような小ささのゾウ、マメジカのような華奢な四肢を持つクジラの祖先など、奇想天外な動物たちがいたことが化石記録から明らかになっている。 哺乳類の系統樹の枝は、小惑星の衝突や火山の噴火、気候の変動などに起因する絶滅事件により、大半が刈り込まれてしまった。しかし絶滅哺乳類が獲得した進化の遺産は、私たちの身体に確かに引き継がれている。たとえば、耳や顎の骨の形状、妊娠や乳児の成長の仕方、咀嚼を可能にした臼歯の形状や乳歯・永久歯のしくみは、私たちの祖先が3億年の間に一つ一つ獲得したものだ。 古生物学者たちは、世界中を探索し、化石記録やDNA解析を元に、絶滅の危機を辛くも耐え抜きついに繁栄を勝ちえた哺乳類の歩みを明らかにしてきた。本書はその発見と解明の興奮を追体験する書でもある。 図版多数収録。 【目次】 哺乳類の年表 哺乳類の系統樹 地質時代の世界地図 序章 我らが哺乳類一族 第1章 哺乳類の祖先 第2章 哺乳類が出来上がるまで 第3章 哺乳類と恐竜 第4章 哺乳類の革命 第5章 恐竜は滅び、哺乳類は生き残る 第6章 哺乳類、現代化する 第7章 極端な哺乳類たち 第8章 哺乳類と気候変動 第9章 氷河時代の哺乳類 第10章 ヒトという哺乳類 終章 未来の哺乳類 謝辞 訳者あとがき 参考文献 索引