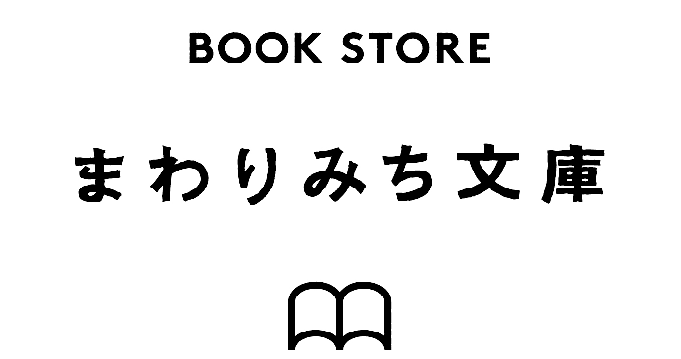-

Tokyo Jazz Joints 消えゆく文化遺産 ジャズ喫茶を巡る
¥4,180
SOLD OUT
著者:フィリップ・アーニール 発行元:青幻舎 176ページ 165mm × 195mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 北アイルランド出身の写真家フィリップ・アーニールによるプロジェクト「Tokyo Jazz Joints」。 店という意味を表すスラングの「Joint」をプロジェクト名に入れたこの活動は、東京からはじまり日本全国を3年かけて回った、愛すべきジャズ喫茶、ジャズバーの記録である。訪れた先には、岩手のBASIEや京都のjazz spot YAMATOYA、東京のジャズ喫茶 いーぐる、直立猿人、そして神奈川のダウンビートなどの名店も。 ジャズ好きが耳を傾け、時にその愛を語らうこの空間は、日本特有の文化であり、アーニールは日本で暮らしていくなかでその興味深さに魅せられてきた。 そして2015年、友人であり協力者のアメリカ人放送記者、ジェームス・キャッチポールと時代とともに次々に姿を消してゆくこの市井の文化的遺産を撮影するプロジェクトを始動した。 2023年にドイツの出版社から刊行し、世界中の読者を魅了した本作。日本語版オリジナルの仕様で、待望の刊行!
-

フォルモサ南方奇譚
¥2,750
著者:倉本知明 発行元:春秋社 368ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 日本軍に切り落とされた亀神の首、城壁にかけられた三百年のマジナイ、湖に暮らす龍の母子、祖霊が眠る山に隠された黄金郷。無縁仏の怨霊に異神、義民に逆賊、西洋の「文明人」と原住民の頭目、帝国の支配に抗して蜂起した匪賊……。 大国による支配の痕跡と土着の文化が絡み合う、神々の楽園・台湾のディープ・サウス。歴史と伝承の狭間にある数々の奇譚から、すでにないのにそこにある、台湾の「いま」へと迫る17章。各章末に怪談コラムを付す。〔カラー口絵16頁〕 【目次】 口絵 はじめに 1 羅漢門の皇帝陛下 遊園地の思い出 2 客家と仮黎(ガライ) よそ者たちが唱った故郷 墓地に響く歌声 3 清あるを知って日本あるを知らず 六堆客家興亡史 Y字路の怪談 4 左営旧城三百年のマジナイ 骨 5 高雄版ドラゴンクエスト 曹公と龍の母子たち 義賊と知県 6 伝説の黄金郷を探して 死者をのせたバス 7 浸水営古道クロニクル 忘れられた騒乱 祖霊の声 8 亡霊たちの眠る町 タイワンザルと博物学者 エレベーター前に立つ女鬼 9 荖濃渓サバイバル 帰ってきた紅毛の親戚と合従連衡するマイノリティ 集落を救った少年 10 瑯嶠八宝公主譚 カミさまとなったおひいさま 心に住む鬼 11 1871漂流民狂詩曲(ラプソディー) トイレの「小紅」さん 12 ワタシハダレ? 台湾出兵と忘れられた拉致事件 赤い目のパリ 13 「鬼」をもって神兵となす とある婚姻 14 神を燃やす 仏さまとなった羅漢脚 15 土匪と観音、ときどきパレスチナ ハリネズミになった男 16 フォルモサ水滸伝 媽祖VS玄天上帝 下淡水渓法力大合戦 17 生きべくんば農民と共に、死すべくんば農民のために 宙に浮く棺桶 主要参考文献
-

黒人と白人の世界史
¥2,970
著者:オレリア・ミシェル 訳者:児玉しおり 解説:中村隆之 発行元:明石書店 376ページ 195mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ヨーロッパ人は、アフリカ人を奴隷にしたために人種主義者になった」。本書は、大西洋奴隷貿易、奴隷制、植民地主義とともに、「人種」がどのように生み出され、正当化されていったのかを歴史的に解明する。ル・モンド紙が「まるで小説のように読める」と評す、人種の歴史の新たな基本書。 【目次】 序文 イントロダクション―ニグロと白人、言葉の歴史 第Ⅰ部 奴隷制と帝国 第1章 奴隷という制度 制度としての奴隷 奴隷制の社会的意味 第2章 サハラ砂漠以南のアフリカにおける奴隷制 古代以来のナイル川北部とサハラ砂漠の商業上の地位 アラブ世界の拡大と奴隷売買ルートの発展 西アフリカにおける奴隷交易国の形成 奴隷制の歴史的重み 第3章 ヨーロッパのダイナミズム ヨーロッパ建設における一つのパラドックス 一五世紀の南大西洋におけるポルトガル人とカスティーリャ人 大西洋の植民地化のメカニズム/交易の支配 大西洋の農園 第4章 アメリカの発見 アメリカにおける事業 インディアンの奴隷化 “ニグロ”貿易 結論 奇妙な帝国 第Ⅱ部 ニグロの時代 第5章 ニグロのプランテーション(一六二〇~一七一〇年) プランテーション―ブラジルからカリブ海の島々まで ブラジルからカリブ海の島々に向かったオランダ人 黒人奴隷貿易国 一八世紀への変わり目における植民地拡大 第6章 不可能な社会(一七一〇~一七五〇年) 捕獲という奴隷生産 拉致からプランテーションまでの「長い旅」 プランテーションと良い農園主 不安定な秩序 ニグロという虚構 第7章 危機に向かって(一七五〇~一七九四年) 経済発展の危機――入植と奴隷貿易の対立 フランスにおけるパラダイムの変化 奴隷制と奴隷貿易への異議 人種隔離主義、“血の純潔”および植民地の階級化 パリとサン゠ドマングの間の革命危機 結論 ニグロと暴力 第Ⅲ部 白人の支配 第8章 ドミ・ネーション(一七九〇~一八三〇年) 徴用された国家(一七九四~一八一五年) アメリカ合衆国の奴隷制維持とフランスの奴隷制復活/解放奴隷をどうするか 植民地の転換とイデオロギーの急変(一八一五~一八三〇年) 奴隷制擁護派、リベラル派、一八二〇年の危機/奴隷制廃止主義と新たな支配/所有者の国家 第9章 奴隷制から人種へ(一八三〇~一八五〇年) 奴隷制からの脱却(一八三〇~一八四〇年) 人種の科学(一八四〇~一八五〇年) 「ニグロの虚構」から白人の虚構へ 第10章 新たな支配(一八五〇~一八八五年) 奴隷制なき植民地労働の再編(一八五〇~一八七五年) アメリカにおける社会関係の転換の難しさ/アフリカにおける新たな生産計画/白人の科学 ベルリン会議(一八八五年) 第11章 人種の統治(一八八五~一九一五年) ネオプランテーション(一八八五~一九一〇年) 人種政策 白人優位の物語を強化する 国家の退廃と純粋さの間にある国家身体 第12章 妄想、悪魔、民主主義(一九二〇~一九五〇年) 第一次世界大戦後の人口調整 都市――人種と近代化/植民地 一九三〇年代――人種主義者という群衆 一九三〇年代に入る時期の二つの人種危機/否認と熱狂の間で 結論 人種の策略 「ニグロの虚構」 「白人の虚構」 人種を終わらせるために 謝辞 解説 中村隆之 原注 参考文献
-

猫マッチラベル図録
¥2,970
SOLD OUT
著者:加藤豊/板東寛司 発行元:風呂猫 240ページ 210mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** レトロ・アートな猫マッチラベル、約2000点収録! 商標登録の燐票から広告マッチ、趣味の木版ラベル、アーチストの創作猫マッチラベル、世界の猫ラベルまで。 猫のマッチラベルの全てがこの一冊に・・・ 猫好き、アート好き、レトロ好きには堪らない! 2025年「国産マッチ創業150年」「昭和100年」記念出版! 【目次】 1 猫の商標マッチ 猫ノ歩行スル圖/招き猫/猫と鼡/猫と犬/猫と鳥/猫になつた虎/物語の猫/長靴をはいた猫/音楽猫/猫のお茶会/働く猫/天秤猫/遊ぶ猫/テニス猫/鞄猫/黒 猫/ハイカラ猫/仲良し猫/鞠 猫/逆立猫/岩上猫/猫柄登録商標 全77 2 猫の趣味木版 木版個人票/燐猫会/燐票蒐集同好会 3 猫の広告マッチ① 猫広告文案/関東の星座銀座クロネコ/新更の銀座クロネコ/全国Cafeクロネコ巡り/カフェ/カフヱーシャボテヱ/キャバレー クラブ/バー/グランド サロン スタンド/割烹 居酒屋/喫茶と洋酒 /タバコ マッチ /NIKKO vs CRAVEN/純喫茶/喫茶/Tea Room/喫茶と菓子/マリヤ/食堂/洋食 レストラン/旅館/食堂/梅の家 ホテル/Music/招き猫/目呂二と招き猫/玉猫/玉突 ゲーム/商店/日本のFelix/猫柄いろいろ/名入れ猫 4 猫の広告マッチ② 写真/イラスト/店名/キャラクター/ロゴマーク 5 猫の外国マッチ●アメリカ/インド/オーストリア/オランダ/カナダ/スイス/スウェーデン/スペイン/ソ連(旧ソ連)/チェコ/中国/デンマーク/ドイツ/ハンガリー/フィンランド/フランス/ベルギー/ポーランド/ポルトガル/旧ユーゴスラビア/イギリス/イタリア/イラン/フィリピン/ベトナム/台湾 6 猫のアートマッチ アーチスト53人による創作猫マッチラベル 【コラム等】 ●マッチの知識 ●猫のマッチラベル年表
-

ギョランギョラン 呑兵衛さんの魚卵紀行
¥1,760
SOLD OUT
発行元:星羊社 95ページ 148mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 人類初の呑兵衛向け魚卵紀行本!? 北海道では虎杖濱のタラコ天国や小樽の市場、青森県では弘前市の筋子やさん、「すじこのうつわ」を焼く津輕焼職人の工房、鰺ヶ沢町の幻の淡水魚養殖場、秋田県では八峰町のハタハタ・ブリコを提供する温泉などを巡る。 ギョランというテーマを軸に各地の歴史や豊かな食文化、地域産業の奥深さに触れる一冊。本書を通して、魅惑の魚卵ワールドを賞味あれ! 【目次】 魚卵をほどく 幻の淡水魚イトウ(青森県 鰺ヶ沢町) 鯵ヶ沢 旅の地図 津軽衆の筋子愛(青森県 弘前市) 弘前 旅の地図 希少な国産タラコ(北海道 白老町虎杖浜) 虎杖浜 旅の地図 ニシンが帰ってきた(北海道 小樽市) 小樽 旅の地図 1月のハタハタ(秋田県 八峰町八森) サケの一生 あとがき
-

徴兵体験 百人百話
¥1,650
著者:阪野吉平 発行元:17出版 256ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 110人の徴兵体験談集。新聞もラジオもない、小作・奉公人より兵隊は給料がもらえて食うものも心配ない、という今からは想像することも難しい当時の人々の生活環境。 3年間で戦死者なしという中隊。120人の中で生きて帰れたのは9人という中隊。毎日が死と隣り合わせだった人。一度も戦闘になったことがないという人。食うには困らなかったという人。排泄物まで洗って食ったという人。真っ青になってブルブル震えて飛んで行った特攻隊員。「この戦は負け戦だ。こんなところで死んではダメだ」と言った中隊長。軍隊生活が楽だったという人。軍隊よりソビエト抑留の方が楽だったという人。捕虜を度胸試しで殺したという人。死刑前日に釈放されたという人。片足を失った人。片目を失った人。病気で兵役を免れた人。終戦を知って泣く人、喜ぶ人。昭和17年に兵隊になり日本に帰って来たのは29年という人。今も目に焼き付いていることがあるがそれは話せないという人。そろそろお迎えが来るから話そうという人。 本書は阪野吉平が2002年~2003年に110人の徴兵体験者から直接聞き取ったもので伝聞ではありません。語り手は本名・顔写真付き。聞き手のペンは中庸。戦争記録として貴重な証言もある。生の声は重い。
-

ファンキー中国 出会いから紡がれること
¥2,530
SOLD OUT
編者:井口淳子/山本佳奈子 著者:井口淳子/山本佳奈子/広岡今日子/長嶺亮子/無常くん/宮里千里/二村淳子/大友良英/多田麻美/中山大樹/OKI/濱田麻矢/武田雅哉 発行元:灯光舎 195mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 音楽、クラフトビール、TikTok、豆腐屋、祭祀、ロックフェスに伝統劇―― 多彩な書き手が一堂に会し、それぞれの視点と切り口で描く、ファンキーな中国体験記! 音楽家や収集家、映画祭主催者、祭祀採音者、研究者など13人が集まり、自身の体験した「中国」をそれぞれが思う存分に綴ったエッセイ集を刊行。 80年代の「魔都」上海と食の記憶、中国の村に出現したド派手なステージでのライブ、TikTok で見つけた瀋陽公園で溌溂と踊る人々。70年代の文革期から現代中国という時代をまたにかけ、北京の胡同(フートン)から雲南省、 果てはフランスや台湾、モンゴルにまでエッセイの舞台が広がっていく。 報道では伝えられることのない、書き手たちが映し出す中国の姿。「伝統」に新しいものを豪快に取り入れる姿があり、厳しい規制があるなか、生活に染み入る絶妙な「ゆるさ」や「自由」がある。ときにはカルチャーギャップと呼ばれるような衝撃にも戸惑いながら、書き手ひとりひとりが経験した小さな「出会い」を紡ぎます。中国といえば国家や政治や歴史という大きなイメージをつい頭に浮かべてしまいがちですが、人と人が出会う小さな瞬間にこそ、かけがえのないものがある。そんな、ひとつの希望を感じるような一冊を刊行します。 本文とカバーのイラスト及び装幀は、『送別の餃子』でお馴染みの佐々木優さん。「14人目の書き手」として、自身の記憶に残る中国の街並みをカバーに描いていただきました。 【目次】 ◆中国の〝ないないづくしの音楽〟 山本佳奈子 ◆上海一九八七 広岡今日子 ◆伝統は、生のものですから。 長嶺亮子 ◆「おじさん動画」と自由の風 無常くん ◆尖閣列島わったーむん 宮里千里 ◆自由・平等・豆腐:豆腐伝道師・李石曾をめぐって 二村淳子 ◆インタビュー 中国〜アジア、地べたの音楽家どうしの交流 大友良英 ◆北京現代アートをめぐる回想:芸術区の変遷を中心に 多田麻美 ◆中国独立電影を振り返る 中山大樹 ◆滲む国境 OKI ◆北京精釀啤酒(クラフトビール)攻略記二〇一五 濱田麻矢 ◆康定人民飯店61号室:のんしゃらんチベット放浪記 武田雅哉 ◆かくも長き中国駐在 井口淳子
-

継承されるデザイン 世界の伝統ニット
¥3,080
SOLD OUT
発行元:日本ヴォーグ社 160ページ 257mm × 182mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** フェアアイル、ロピ、カウチン、ビンゲ、ボーヒュース、ガーンジー、シェットランドレースなどなどヨーロッパを中心に世界各国の伝統ニットをウエアから小物まで歴史と共に紹介した、編み物好き、手芸好きの知的好奇心をくすぐる「読む編み物本」。 日本ヴォーグ社に所蔵してあった数ある伝統ニットをピックアップして撮影しているため、現物の迫力を感じることができます。今なお継承される伝統ニットのデザインを堪能できる1冊です。
-

ダーチャ 失われゆくソビエト時代の小屋とコテージ
¥2,970
SOLD OUT
著者:フョードル・サヴィンツェフ 訳者:石田亜矢子 発行元:グラフィック社 240ページ 200mm × 160mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 本書はソ連時代に都会に住む人びとの別宅として建てられた木造の小屋やコテージである「ダーチャ」を集めた貴重な資料集。 本書は革命、戦争、共産主義の崩壊などを乗り越え、その過程で人びとの生活の不可欠な一部となったダーチャ。その特徴的な歴史的・文化的背景の解説も収録。
-

インドの台所
¥2,970
SOLD OUT
著者:小林真樹 発行元:作品社 304ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 食卓上に置かれた食器、その奥が気になる。 ディープなインド台所紀行! 南アジア各地の食器・調理器具の輸入販売者にして日本屈指のインド料理マニアのアジアハンターが、インドの端から端まで、さまざまな台所をめぐる――。 料理のみならず、食器や調理器具、調理工程に着目し、歴史や文化、社会問題などにも触れながら、これまであまり取り上げられてこなかった「食」の内側を覗き、さらにディープな食世界へと誘う、インド台所紀行! 【目次】 はじめに 北インド カシミールの宴席料理ワーズワーンの世界 シュリーナガル 1 旧市街の奥の堅牢な館 シュリーナガル 2 カシミールの農村探訪 バドガム 秋のパンジャーブの農家メシ アムリトサル 隠されたキッチン オールド・マナーリー ニハーリー屋とナーン屋 オールドデリー 1 インドの中のチベット系住民宅 オールドデリー 2 インド産ファストフードの現在・過去・未来 ニューデリー 1 孔雀が舞いおりる大豪邸 ニューデリー 2 ムグライー料理人たちの連鎖 ルドーリー コラム ムスリム職人の作るヒンドゥー神具 ムラーダーバード 南インド 白米と雑穀のはざまで チェンナイ 1 異国で食べる昭和レトロメシ チェンナイ 2 南インドの働き手問題 チェンナイ 3 並存する二つの台所 ディンディッカル 密林の中の小さな家 プンニャル マーピラのにぎやかな食卓 チャベスリー 沁みる酒、沁みる話 カキナダ1 アーンドラ人の葉皿イメージ カキナダ 2 IT系料理男子のキッチン ベンガルール 1 豊穣なるファイブスター・ホテル ベンガルール 2 コラム インダス文明からの伝統を受け継ぐ人たち マンナル 東インド 「正しい」台所とは何か コルカタ 1 ビハーリー・マン・イン・コルカタ コルカタ 2 路上生活者のキッチン コルカタ 3 コルカタの中華系の台所 コルカタ 4 アッサムの青銅食器 サルテバリ 先住民族たちのハレとケ バスタル ディアスポラ的ネパール料理 カリンポン ネワール族の家事労働 カトマンズ コラム 大地の味のチャーエ コルカタ 西インド 世界最大のスラム街 ムンバイ 1 憧憬と追憶のボンベイ ムンバイ 2 伝統と最新鋭 アーメダーバード 不意打ちの味をもとめて ビーカーネル カッチャーとパッカー サワーイー・マードプル インド屋台のイメージ インドール インド式パン文化の根源 パナジ 1 ゴア・フェニーで白昼夢を パナジ 2 コラム 新しくて古い工場 ムンバイ おわりに
-

反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー
¥4,180
SOLD OUT
著者:ジェームズ・C・スコット 訳者:立木勝 発行元:みすず書房 296ぺージ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ある感覚が要求してくる——わたしたちが定住し、穀物を栽培し、家畜を育てながら、現在国家とよんでいる新奇な制度によって支配される「臣民」となった経緯を知るために、深層史(ディープ・ヒストリー)を探れ、と…」 ティグリス=ユーフラテス川の流域に国家が生まれたのが、作物栽培と定住が始まってから4000年以上もあとだったのはなぜだろうか? 著者は「ホモ・サピエンスは待ちかねたように腰を落ち着けて永住し、数十万年におよぶ移動と周期的転居の生活を喜んで終わらせた」のではないと論じる。 キーワードは動植物、人間の〈飼い馴らし〉だ。それは「動植物の遺伝子構造と形態を変えてしまった。非常に人工的な環境が生まれ、そこにダーウィン的な選択圧が働いて、新しい適応が進んだ…人類もまた狭い空間への閉じこめによって、過密状態によって、身体活動や社会組織のパターンの変化によって、飼い馴らされてきた」 最初期の国家で非エリート層にのしかかった負担とは? 国家形成における穀物の役割とは? 農業国家による強制の手法と、その脆弱さとは? 考古学、人類学などの最新成果をもとに、壮大な仮説を提示する。 【目次】 はじめに 序章 ほころびだらけの物語——わたしの知らなかったこと 国家と文明の物語のパラドックス/国家の正しい位置づけ/手短な行程表 1 火と植物と動物と……そしてわたしたちの飼い馴らし 火/集中と定住——湿地仮説/湿地と定住/なぜ無視されてきたのか/ギャップに注目する/そもそもなぜ植えるのか 2 世界の景観修正——ドムス複合体 新石器時代の植え付けから百花繚乱へ——耕作の影響/進化のモジュールとしてのドムス/狩猟民の獲物から農民の囲い物へ/人間の類似点に関する推論/わたしたちの家畜化 3 動物原性感染症——病理学のパーフェクトストーム 苦役とその歴史/後期新石器時代複数種再定住キャンプ——病理学のパーフェクトストーム/多産と人口に関する注釈 4 初期国家の農業生態系 国家作りの農業地理/穀物が国家を作る/壁が国家を作る——防御と閉じこめ/文字が国家を作る——記録と識字力 5 人口の管理——束縛と戦争 国家と奴隷制/メソポタミアの奴隷制と束縛/エジプトと中国/「人的資源」戦略としての奴隷制/略奪的資本主義と国家建設/メソポタミアの奴隷制および束縛の特殊性/飼い馴らしと重労働と奴隷制に関する推測的覚書 6 初期国家の脆弱さ——分解としての崩壊 初期国家の罹患率——急性疾患と慢性疾患/病気——過度の定住、移動、国家/環境破壊——森林破壊と塩類化/政体の消滅——戦争とコアの搾取/崩壊万歳 7 野蛮人の黄金時代 文明とその野蛮な周辺部/野蛮人の地理、野蛮人の生態系/略奪/交易ルートと課税可能な穀物コア/闇の双生児/黄金時代だったのか? 索引/原注/参考文献
-

隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ(シリーズ「あいだで考える」)
¥1,540
SOLD OUT
著者:斎藤真理子 発行元:創元社 160ページ 168mm × 130mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** いま、韓国の文学、音楽、ドラマや映画に惹かれ、その社会や言語に関心を持つ人はますます増えている。 本書では、著者が韓国語(朝鮮語)を学び始めた背景、この言語の魅力、痛みの連続である現代史と文学の役割、在日コリアンと言語のかかわりなどを、文学翻訳の豊かな経験から親しみやすく語る。文字、音、声、翻訳、沈黙など、多様な観点から言葉の表れを捉え、朝鮮半島と日本の人々のあいだを考える1冊。 【目次】 序に代えて――1杯の水正果を飲みながら 1章 말(マル) 言葉 韓国語=朝鮮語との出会い 隣の国の人々の「マル」 マルに賭ける作家たち 2章 글(クル) 文、文字 ハングルが生まれる 文字の中に思想がある マルとクルの奥にひそんでいるもの 3章 소리(ソリ) 声 豊かなソリを持つ言語 朝鮮語のソリの深さ 思いとソリ 4章 시 (シ) 詩 韓国は詩の国 植民地支配の下で書いた詩人 現代史の激痛と文学 惑星のあいだを詩が行き来する 5章 사이(サイ) あいだ 翻訳の仕事をしている場所 サイにはソリがあふれている おわりに 韓国語と日本語のあいだをもっと考えるための 作品案内
-

スペクテイター vol.53 1976 サブカルチャー大爆発
¥1,100
SOLD OUT
発行元:エディトリアル・デパートメント 発売元:幻冬舎 183ページ 242mm × 182mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「政治の季節」と呼ばれる1960年代とバブル経済へ突入していった1980年代に挟まれて、まるでなにも起こらなかったかのように思われがちな、1970年代。 しかし、大人たちの目の届かない若者たちの世界では、文化的な爆発と呼ぶべき重要な出来事が起きていた。オカルト、アニメ、パンク、自己教育…。 4つのサブカルチャー誕生の瞬間に立ち会ったリトルマガジン関係者の証言や論考を通じて、1976年に起こったサブカルチャー大爆発の実情に迫る。 【目次】 ◆PLAY BACK 1976 作画/関根美有 ◆クロニクルズ 70年代の主な出来事 ◆論考 アナザー・スピリッツ・オブ・76 〝76年精神〟とはなにか 文/宇田川岳夫 ◆インタビュー① 氷川竜介氏(アニメ・特撮評論)に聞く『宇宙戦艦ヤマト』とファンダム形成史 取材・構成/鴇田義晴 ◆インタビュー② 武田崇元氏(八幡書店社主)に聞く『地球ロマン』とジャパニーズ・オカルト再発見 取材・構成/宇田川岳夫 ◆NIPPON 70S 写真/児玉房子 ◆寄稿① 『ロック・マガジン』にみるパンクの日本上陸 文/東瀬戸悟 写真提供/阿木譲アーカイブ・開田裕治 ◆寄稿② 自己教育の教科書として創刊された『別冊宝島』 文/長沼行太郎 ◆まんが「夜の魂」 作/まどの一哉 ◆はみだし偉人伝 その4 水谷孝 裸のラリーズと「死」 文/横戸茂 写真/中藤毅彦
-

からくり玩具 世界一周 [Moving Folk Toys Around The World]
¥3,300
SOLD OUT
著者:山口照二 写真:高見知香 発行元:大福書林 160ページ 215mm × 155mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 現代では数少なくなった職人・工人の技術が光る「からくり玩具」。紙や木など身近で安価な素材でできた、しかし工夫の凝らされた動くおもちゃを美しい紙面で紹介する。世界五大陸の玩具と、日本の貴重なからくり郷土玩具が満載。 本書には、茶運び人形のような高価で複雑なからくり玩具・オートマタは登場しない。著者が愛するのは、日本では戦後子どものころに触れたような、安価な素材とシンプルなからくりで作られた素朴で知的な玩具である。手にとって遊んでみるととても楽しい。知財などの概念がない時代のからくり玩具は、世界中で見ることができる。自分で作れるものも多いので、ぜひ作ってみてほしい。 【目次】 もくじ はじめに ヨーロッパ ドイツ 4 / イギリス 38 / イタリア 46 / 南欧 56 / スイス 58/ チェコ 61 / 東欧 66 / ロシア 70 / スウェーデン 74 / フィンランド 76 アメリカ アメリカ 77 / メキシコ 84 / コロンビア 93 / ペルー 94 / ブラジル 95 アフリカ諸国 96 アジア 中国 100 / インドネシア 110 / カンボジア・スリランカ 112 / ベトナム 113 / タイ 114 / 韓国 116 / ミャンマー 117 / インド 118 / 日本 126 オーストラリア 158 コラム ドイツのからくり玩具 26 その他の国の砂からくり 36 世界の「ついばむ鳥」 68 アジアの影絵人形 98 世界の運動人形 124 日本のからくり玩具 142 本書に登場する主なからくり玩具 159
-

ヒッピーの教科書
¥1,980
SOLD OUT
原作:赤田祐一 作画:関根美有 発行元:エディトリアル・デパートメント 110ページ(一部カラーページ) 248mm × 188mm ハードカバー *********************** 店主コメント *********************** みなさんは「ヒッピー」という言葉から何を連想しますか? 長髪、フレアパンツ、ドラッグ、性の解放など・・・反体制的で自由に生きる俗世離れした人たちをイメージするのではないでしょうか? この本ではヒッピーの前身となったビート・ジェネレーションから現在のヒッピーまでマンガ形式で解説。その歴史を読み解くと、退廃的なイメージとは違った〝生産的でクリエイティブ〟な一面が見えてきます。 2019年に刊行された雑誌『スペクテイター』44号に掲載された記事のうち「ヒッピーの歴史」というマンガ記事を抜粋し再編集。さらに、書き下ろしの記事が追加されています。 基になった雑誌の方は古書価が高騰。なかなか入手しづらい状況ですので、こちらの再編集版をこの機会にぜひ!
-

パンクの系譜学
¥2,860
SOLD OUT
著者:川上幸之介 発行元:書肆侃侃房 348ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** パンクとは常に問い、それについて行動を起こすことだ。 音楽だけでなく、アート、思想、運動の側面からも「パンク」の根源に迫る画期的著作。 ロックと現代アートから派生したパンクは、音楽活動のみならず、独自の実践を通して社会に影響を与え、人間性の回復をもたらしてきた。最新の研究を踏まえ、その系譜を現在まで辿る。Punk!展、ゲリラ・ガールズ展ほか、話題の展示のキュレーションを行ってきた研究者による初単著。松村圭一郎さん、毛利嘉孝さん推薦! 【目次】 序章 第一部 パンクの文脈と思想 第一章 アートスクール/第二章 共産主義(コミュニズム)/第三章 アナキズム 第二部 パンクの音楽における系譜 第一章 アフリカ系アメリカ人の歴史/第二章 フォーク/第三章 スキッフル/第四章 ガレージ/第五章 パンク 第三部 パンクのアートにおける系譜 第一章 現代アート/第二章 DADA(ダダ)/第三章 レトリスム/第四章 シチュアシオニスト・インターナショナル/第五章 キング・モブ 第四部 セックス・ピストルズ以降 第一章 Oi!/第二章 アナーコ・パンク/第三章 ハードコア・パンク/第四章 ライオット・ガール/第五章 パンクと人種/第六章 パンクとクィア 第五部 アジアのパンクシーン 第一章 独裁政権/第二章 ミャンマー/第三章 橋の下世界音楽祭 おわりに 参考文献
-

密航のち洗濯 ときどき作家
¥1,980
著者:宋恵媛 /望月優大 写真:田川基成 発行元:柏書房 336ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 1946年夏。朝鮮から日本へ、 男は「密航」で海を渡った。 日本人から朝鮮人へ、 女は裕福な家を捨てて男と結婚した。 貧しい二人はやがて洗濯屋をはじめる。 ----------------------------------------- 朝鮮と日本の間の海を合法的に渡ることがほぼ不可能だった時代。それでも生きていくために船に乗った人々の移動は「密航」と呼ばれた。 1946年夏。一人の男が日本へ「密航」した。彼が生きた植民地期の朝鮮と日本、戦後の東京でつくった家族一人ひとりの人生をたどる。手がかりにしたのは、「その後」を知る子どもたちへのインタビューと、わずかに残された文書群。 「きさまなんかにおれの気持がわかるもんか」 「あなただってわたしの気持はわかりません。わたしは祖国をすてて、あなたをえらんだ女です。朝鮮人の妻として誇りをもって生きたいのです」 植民地、警察、戦争、占領、移動、国籍、戸籍、収容、病、貧困、労働、福祉、ジェンダー、あるいは、誰かが「書くこと」と「書けること」について。 この複雑な、だが決して例外的ではなかった五人の家族が、この国で生きてきた。 蔚山(ウルサン)、釜山、山口、東京―― ゆかりの土地を歩きながら、100年を超える歴史を丹念に描き出していく。ウェブマガジン『ニッポン複雑紀行』初の書籍化企画。 【目次】 プロローグ 密航 1946 関釜のあいだの海/蔚山からの密航船/K村の警防団/下関での感染拡大/仙崎港の朝鮮人たち/1946年のコレラ禍 第1章 植民地の子ども 1 朝鮮 1911‐24 鯨のまち長生浦/方魚津の日本人町/蔚山の市街地/江陽里の老人たち/対馬の先へ/植民地都市釜山 2 日本 1924‐44 関東大震災後の横浜で/東京で短歌に出会う/15年後の帰郷/ふたたび江陽里にて/東京に戻る/結婚と徴用 3 朝鮮 1944‐46 朝鮮に逃げる/妻との旅(1)東京から釜山へ/妻との旅(2)釜山から兼二浦へ/1945年8月15日/妻との旅(3)38度線南下/帝国崩壊後の釜山/妻との旅(4)日山津から日本へ 送還 1946 失敗した密航/ひと月遅れのコレラ猖獗/仙崎、佐世保、博多のコレラ船/針尾収容所から大村収容所へ 第2章 洗濯屋の家族 1 尹紫遠 ユン ジャウォン 密航のち、18年の人生/自分ひとりの部屋/多摩川を泳いで渡る/故郷の戦争、弟の虐殺/横浜の検閲生活/売血もできない/米兵と黒人兵/洗濯屋のぬかるみ/ときどき作家/テープレコーダー 2 大津登志子 おおつ としこ 満洲から38度線へ/朝鮮人との結婚/日本人と朝鮮人のあいだで/夫の日記と広島の教会 3 泰玄 テヒョン たいげん Money, money, money/中目黒の外国人たち/朝鮮学校の頃/夜間学校と祖国訪問団/国籍と永住の葛藤/三菱重工爆破と朴正煕暗殺 4 逸己 いつこ イルギ 歴史を準備する人/女性でロボット屋で/混乱する国籍/差別と暴力と/少数者の痕跡 エピローグ 補遺 密航の時代 註 参考文献
-

ことづての声/ソマの舟
¥6,050
SOLD OUT
著者:ふるさかはるか 発行元:信陽堂 224ページ 210mm × 180mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 2002年よりノルウェーなどを訪れ、その地の暮らしや風土から木版画を制作してきた作家ふるさかはるか。 2017年、津軽・南部地方で山の命と直接関わるマタギ[猟師]やソマ[木こり]や漆掻き[樹液を採集する人]たちに出会い、彼らが動植物からどのようなサインを読み取り、どう自然とやりとりするのかを取材してきた。山のことばに導かれ、手仕事に深く触れ、自らも土を拾い藍を育てて絵の具を作り生みだされた木版画、ドローイング、ピンホール写真、そしてことばの記録をまとめた作品集。 ドローイング、ピンホール写真、インタビューで構成された『ことづての声』、木版画とエッセイで描き出す『ソマの舟』のふたつの世界を、たて組、ヨコ組、両開きの書籍にまとめた。「手刷り木版画」付。管啓次郎、登久希子も寄稿している。
-

秘宝館
¥2,530
SOLD OUT
著者:都築響一 発行元:青幻舎 448ページ 文庫判 148mm × 128mm *********************** 出版社紹介文より *********************** 空前の観光ブームのなか1970年代~観光地に誕生したオトナの娯楽施設「秘宝館」 斬新奇抜な創造力が溢れる、それぞれの館の演出は現代においても新鮮に映る 昭和という時代が生んだ性のアミューズメントパークは、アート空間のようだ 秘宝館のその後を追った、2023年に取材した写真、原稿も掲載。 ----------------------------------------- 本書に登場する秘宝館のほとんどはもう存在しないし、たぶんここでしか写真すら見られない秘宝館もある。子どもがオトナになるくらいの、ほんの少し前に、日本人がこんなにヘンな場所をつくって、それが裏観光名所として賑わっていた時代があったこと。それを恥ずかしく思うか、楽しく思うかで、僕らの国を見る眼差しはずいぶん変わってくるはずだ。 —— 都築響一
-

ラブホテル
¥2,530
SOLD OUT
著者:都築響一 発行元:青幻舎 448ページ 文庫判 148mm × 128mm *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ラブホテル」、それは昭和・平成の色香にむせる愛の空間。 急速に姿を消しつつあった2000年代に遊びごころ溢れるインテリアを探し 歩いた全73室。オトナの夜の夢! 2023年に取材した最新ラブホデザインも追加! ----------------------------------------- レトロとは「過ぎ去った時代のいいところだけを見てとる」技術でもある。戻れない時代に憧れるのはそれだけで楽しいけれど、このささやかな記録のコレクションから、当時のカップルがどんな驚きと興奮でこんな部屋を楽しんだか、そのドキドキワクワク感に思いを馳せ、それがいまから数十年後に「レトロ・デザイン」として愛でられるような新しいスタイルの創造につながっていくとしたら、僕としては最高にうれしい。 —— 都築響一
-

水木しげるの遠野物語
¥1,485
SOLD OUT
著者:水木しげる 原作:柳田國男 発行元:小学館 264ページ 210mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 妖怪コミックの聖典誕生。遠野物語を水木氏が漫画化! ザシキワラシ、河童、鬼……岩手県遠野市の厳しい自然の中で、人々の想像力が生み出した妖怪たちが、今動き始める! 柳田國男氏の名著『遠野物語』は、100年前のベストセラーにして日本民俗学の原点ともなった名著です。これを水木しげる氏がコミック化。格調高い文語体で書かれた原書の魅力を、水木氏ならではの想像力・描写力で完全にビジュアル化し、新たな魅力を作りあげています。ザワザワと心騒ぐ、日本の風土から生まれた怪異の世界。さらに『遠野物語』と『水木しげるの遠野物語』、百年を隔てたこのふたつの本を生み出す母胎・揺籃となった遠野地方の、現在まで残る豊穣な風土をレポートするコラム「2010年遠野の風景」も併録。
-

九月、東京の路上で 1923年関東大震災 ジェノサイドの残響
¥1,980
SOLD OUT
著者:加藤直樹 発行元:ころから 216ページ 198mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 関東大震災の直後に響き渡る叫び声 ふたたびの五輪を前に繰り返されるヘイトスピーチ 1923年9月、ジェノサイドの街・東京を描き 現代に残響する忌まわしい声に抗う―― 路上から生まれた歴史ノンフィクション!
-

世にも危険な医療の世界史(文春文庫)
¥1,210
SOLD OUT
著者:リディア・ケイン/ネイト・ピーダーセン 訳者:福井久美子 発行元:文藝春秋 480ページ 文庫判 148mm × 105mm *********************** 出版社紹介文より *********************** 爆笑と恐怖が交互に襲い来る強烈な歴史書 梅毒には水銀風呂! 夜泣きする子にはアヘン! 水難事故にはタバコ浣腸! かつて人類の常識だった残念すぎる医療の全てがここに。
-

日本宗教のクセ
¥2,090
SOLD OUT
著者:内田樹/釈徹宗 発行元:ミシマ社 248ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 政教分離、旧統一教会、カルト二世 …こうした問題を解くためにも。 行、夕日、お墓などに宿る 日本固有の「クセ」を知ろう。 「宗教的センス」を引き上げる名人対談 日本宗教のクセ ・都市仏教が大地の霊と「くっついた」のが浄土真宗!? ・内面重視ではなく「行」をとても大事にする ・形を変えながら脈々と続く聖徳太子信仰 ・習合的なモデルとしての在原業平と四天王寺 ・国と引き離してもなお成り立つ神道とは? …etc 【目次】 第一章 日本宗教のクセを考える 第二章 夕日の習合論 第三章 お墓の習合論 第四章 今こそ、政教分離を考える 第五章 戦後日本の宗教のクセ