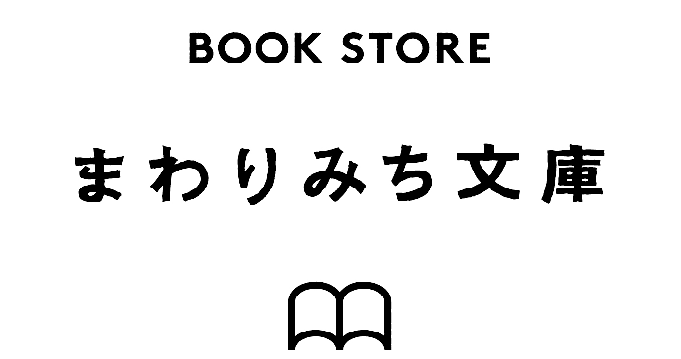-

ふつうに働けないからさ、好きなことして生きています。
¥1,760
著者:平城さやか 発行元:百万年書房 240ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ************************* 出版社紹介文より ************************* 手元には三百円しかなかった。 それでも、今度こそ自分が心底望む生き方がしたかった。 「ふつうに働けない」と弱り果てているあなたが、好きなことで生きていくための100の心得(tips)。 【目次】 はじめに 年表 序章 1 ただ休みたい 2 最高の職場で元気を取り戻す 3 所持金三百円でも 第1章 仕事の話 4 アトリエ風戸のスタート 5 自転車の補助輪を外す 6 行動はとことん休んでから 7 好き嫌いを活かす 8 弱さを細かく見る 9 やりたいことの見つけ方 10 自由業に向く人・向かない人 11 できることではなく、好きなことを 12 やりたいことをひとつに絞らなくていい 13 いびつな形の三色パン 14 好きの精度を上げる練習 15 私のアイデアは枯れない泉 16 パッチワーク思考 17 不満をアイデアで解決する 18 初期衝動 19 実験魂 20 なぞるのは嫌い 21 時代遅れでも 22 イラスト仕事 23 「もったいない」から生まれた作品 24 どんな届き方が嬉しいか 25 自己満足ありき 26 販売してもらえるありがたみ 27 私が本屋を助ける 28 結果なんて存在しない 29 望みと方法を切り離す 30 一度ダメでもあきらめない 31 くやしい? 32 SNSは自分好みのタイプだけ 33 名刺は必要ない 34 本棚の向こうと繋がる 35 人に頼る 36 つまずきの後に新しい物語が始まる 37 「ある」ものに目を向ける 38 波打ち際のワークショップ 39 やってみて気づく 第2章 お金と時間の話 40 稼ぎたい 41 小商いのキャッシュフロー 42 夏が怖い 43 イベント出店料はどこまで? 44 価格設定は自分と相談 45 簿記のすすめ 46 在庫は資産です 47 道具を買うべきか 48 在庫管理をどうするか 49 お金がないからこそ生まれる工夫 50 お金と引き換えにしない 51 不安からくる行動をやめる 52 節約は楽しくない 53 把握すると不安は減る 54 母からのお米 55 五百円のカレンダーとお赤飯 56 お時給マインド卒業 57 手間と時間をかけてこそ 58 息つぎ 59 「世間」より「自分」を知る時間を 60 出来事を点ではなく線で捉える 61 「今」を細かく捉える 62 五分あったら 63 年齢を重ねること 第3章 暮らしの話 64 勇気じゃなくて覚悟 65 理想の一日 66 ルーティン 67 衣食住のバランス 68 コンパクトな暮らし 69 アトリエ活用法 70 一器多用 71 いらない理由 72 離れたところで考える 73 どの街に住むか 74 寝袋生活 75 山の上なら…… 76 歯と同じバランスで食べる 77 土鍋ごはんで元気に 78 「まごわやさしい」お味噌汁 79 結局ぬか漬けが一番 80 不安になる食べ物を控える 81 フィーリング・クッキング 82 医食同源とブレサリアン 83 自分との会話は日常のスーパーから 84 服なんて後まわし 85 肌断食 86 やっぱりきれいでいたい 第4章 心と身体の話 87 悲しみを食べたがっている 88 ひとりになりたい 89 身体という確かなもの 90 いじめのトラウマ 91 恋の話を少し 92 映画のワンシーンと思って 93 命をつなぐ方法 94 死にたいと思った瞬間 95 やきもちの正体 96 いい人をあきらめる 97 言いたいことが言えるか 98 うぐいすの盗作疑惑 99 ワンマンタイプ 100 ただそれだけ
-

仕事の壁はくぐるのだ
¥1,980
著者:川島蓉子 発行元:ミシマ社 240ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 乗り越えなくても大丈夫! ブランディングディレクター、ライターとして活躍し、 現役のままに急逝した著者が綴り遺した、仕事と、生きることの秘訣。 人が集まり働く、そこに起こるさまざまなトラブルや葛藤=壁。 その壁をくぐったり、ずらしたり、かわしたり……。 戦略的な手段ではなく、声高な権利の主張でもなく、真摯に楽しく仕事をするため、編み出された実践の数々。 柔らかでしなやかな、川島さんからのエールが、たくさんの方に届きますように。――編集部一同 【目次】 壁・その1 上司と部下…ああ永遠の壁 壁・その2 やりたいこととできること 壁・その3 女性であるということ 壁・その4 おカネ…糧でもあり毒でもあり 壁・その5 仕事も家庭も自分も 壁・その6 その仕事に愛はあるか? 壁・その7 休むって、どうやるの?
-

リック・ルービンの創作術
¥3,520
SOLD OUT
著者:リック・ルービン/ニール・ストラウス 訳者:浅尾敦則 発行元:ジーンブックス 468ページ 215mm × 155mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** グラミー賞多数受賞、世界最高の音楽プロデューサーリック・ルービンが7年をかけて執筆した「創造性を高める78の知恵」 ニューヨークタイムズ ベストセラー第1位! 世界25カ国で発売! 「素晴らしい作品を作るためには何をすべきかを書くつもりでしたが、結果的にそれは“どう在るべきか”についての本となりました。」————リック・ルービン 世界最高の音楽プロデューサーとして名高いリック・ルービンは、アーティストが自分自身に抱く期待以上の能力を引き出し、素晴らしい才能を発揮するように導くことで、数多くの偉大な作品を生み出してきました。ルービンは「創造性の源」について長い年月をかけて思考するうちに、そもそも「創造性(クリエイティビティ)」とは、アーティストやクリエイターのためだけにあるものではなく、この世界全体と関係があると学びました。ビジネスにも、休養を取るときにも、また、日常生活や子育てなど、「創造性」は人生のどんなステージにも存在し、その才能を発揮する場所を拡げることができるのです。 本書は、誰もが歩める、創造性を高めるための道、ルービンの知恵と洞察の道を辿る学びのコースです。長年の経験から得た知恵を78項目に凝縮し、クリエイティビティを誰もが感じられる瞬間や、人生そのものを近くに引き寄せ、成功へと導いてくれる、感動的な読書体験を提供します。
-

『生 = 創 × 稼 × 暮』
¥1,980
SOLD OUT
発行元:かくれんぼパブリッシング 192ページ 176mm × 115mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** [問い] あなたが生きるとき、創ること・稼ぐこと・暮らすことのバランスをどのように保っていますか。 19名のつくり手による、上記の問いの回答をまとめたエッセイ集。 【著者】 小説家/大学生 新 胡桃 四つ葉のクローバーアーティスト 生澤 愛子 薪ストーブ職人(株式会社ファイヤピット代表) 大石 守 おおば製パン店主 大場 隆裕 農家・百姓/ファームガーデンたそがれ園主 菊地 晃生 詩人・国語教室ことぱ舎代表 向坂 くじら とおの屋要オーナーシェフ・株式会社nondo代表取締役 佐々木 要太郎 諏訪流鷹匠 篠田 朔弥 文筆家/博士(哲学) 関野 哲也 あんこや ぺ 店主 竹内 由里子 文筆家 土門 蘭 書店「かみつれ文庫」店主 西岡 郁香 花屋みたて店主 西山 美華 新渡戸文化学園 VIVISTOP NITOBEクルー 廣野 佑奈 古本よみた屋 副店長/文章で遊ぶ人 ブン はれやか農園代表 槇 紗加 江戸切子職人 三澤 世奈 本屋店主/モノ書き/時々大工 モリテツヤ 空撮写真家/NaohPhoto 山本 直洋 *********************** 店主コメント *********************** 「あなたが生きるとき、創ること・稼ぐこと・暮らすことのバランスをどのように保っていますか。」 この本には上記の問いに対する19人の芸術家の回答が収められています。 「芸術家」の定義を「独自の視点、言葉、世界観を持ち、それを作品にしている方や、体現している方」とし、その職業は農家、文筆家、花屋、料理人などさまざまです。 彼らが考えるリアルな「創ること・稼ぐこと・暮らすこと」のバランスを参考に、自分なりの心地よいバランスを見つける手引き書です。
-

大きな魚をつかまえよう リンチ流アート・ライフ∞瞑想レッスン
¥1,980
SOLD OUT
著者:デイヴィッド・リンチ 訳者:草坂虹恵 発行元:四月社 発売元:木魂社 224ページ 210mm × 130mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 暴力、セックス、夢、死体。 謎めいた映像で人々を魅了してやまない著者が、どんなふうに作品が発想されたのかを説き明かし、パワフルに創作する秘訣 ―― 長年実践している「瞑想」の効用を語り尽くす。 若きクリエイターへの心を込めたメッセージ!
-

転職ばっかりうまくなる
¥1,760
著者:ひらいめぐみ 発行元:百万年書房 224ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 20代で転職6回。 「圧倒的成長」をしたくない人のための、ドタバタ明るい転職のすゝめ。 こんな会社ばっかりの世の中なんて終わってる――。 【目次】 ◎一社目 倉庫、コンビニ アルバイトはたのしい 倉庫ではたらく お金がない 時間の換金には限度がある ◎はじめての就職活動 転職エージェントに登録する 初めての面接 「世の中そんなに甘くないんだよ」 再最終面接 ◎二社目 営業 入社一か月目 ほほえみ地蔵 社会人練習 踏んだり蹴ったり 血便、ふたたび ◎はじめての休職 ダチョウか、タカか、ペンギンか 川と裁判傍聴の日々 ◎三社目 webマーケティング おでんを食べながら働く 「圧倒的成長」をしたくない ◎四社目 書店スタッフ 滑り込み転職 手取り十五万円クライシス レモンの輪切りと人生 「好きなこと」を仕事にする (二十八歳・書店アルバイト) 転職活動、ふたたび トイレットペーパーがない ◎五社目 事務局・広報 入社して一か月で辞めたくなる 「給料も払いたくない」 「仕事ができる・できない」は環境の違い 「ひらいさんは文章で成功しない」 なにもない首里城 ◎六社目 編集・ライター 職場には川が必要 デスクでごはんを食べること、窓がないオフィスで働くこと 「書く」という仕事 甘いものが食べられない期 偏りをはかる ◎七社目 ライター・作家(フリーランス)←「社」ではないですが……。 倉庫バイト・リバイバル 働き方革命 やってみたいことを、やってみる 転職の数だけ人生の味方が増える フリーランスの生活と占い 肩書は書かない いつ、どんな理由で辞めてもいい 夢って、なんだろう ◎あとがき *********************** 店主コメント *********************** 世間ではいまだに転職回数の多さ=忍耐力の無さと思われがち。けれども転職の多さは、仕事観を模索していることの表れでもあります。 やっぱり人生にもまわりみちは必要なのだ。 この本には仕事観についてとても大切なことが書かれています。 それは、自分が社会人になってから15年以上経ってようやく気付いたことでした。下手したらそれに気付かないまま定年を迎える人もいるかもしれない。 この本に書かれているような仕事観が社会のスタンダードになってくれたら、と思う。そうしたらもっと生きやすい世の中になるはずです。
-

労働系女子マンガ論!
¥2,200
SOLD OUT
著者:トミヤマユキコ 発行元:タバブックス 224ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 労働をめぐる女子の悩みの数だけ、応答を試みるマンガが存在するー タバブックスwebサイトで2013年から不定期連載していた「労働系女子マンガ論!」ついに、ついに書籍化!! 恋愛、結婚、出産、といった人生のイベントを迎えるたび、続けるか辞めるかの選択を迫られるのは、たいてい女子の側。労働環境はここ数十年で大きく変化し、どうするのがベストなのか判断がつかない…「女子×労働」の視点で読む女子マンガに人生をサバイブするヒントがある!誰もが知っている王道作品から、知る人ぞ知る隠れ名作まで、web連載を大幅加筆修正。「女性と労働」表象を読み解く、気鋭の研究者トミヤマユキコの女子マンガ論、決定版です。 【目次】 序論「労働系女子マンガ」とはなんぞや? 1章 少女マンガ隆盛期 ― ヒロインは読者と同世代の若き労働者 自分の運命を切り拓く『ベルばら』の女たち 『ベルサイユのばら』 大正時代のラブコメが描く「この国で女が働くとはどういうことか」『はいからさんが通る』 「自立した女」のモデルのひとつは、バレエマンガにある 『アラベスク』 愛より恋より仕事をやれ 70年代作品の強烈なメッセージ 『デザイナー』 女の為政者として「政治と権力」を変革する16歳 『王家の紋章』 労働ものとして魔法少女マンガを読んでみる 『美少女戦士セーラームーン』 2章 「仕事と恋」の時代 ― 社会情勢を反映し働く読者の現実に接近 「近代化」を目指そうとした「働く女」の困難 『東京ラブストーリー』 みんなの視界に入りにくい仕事を描く意義 『動物のお医者さん』 フリーターもバリキャリも大変 就職氷河期がもたらしたリアル 『ハッピー・マニア』『働きマン』 「周縁」で働く女の自由と孤独 『ちひろ』『ちひろさん』 自分らしさに助けられたり苦しめられたりする労働 『リメイク』 恋愛要素なし、仕事人間を肯定する女子マンガの進化 『重版出来!』 3章 労働の多様化・細分化 ― 年齢、仕事観、社会問題等に着目 憧れからはほど遠い設定が生み出す深い味わい 『うどんの女』 主婦の労働と存在意義をめぐる重い問い 『ハウアーユー?』 リアルとファンタジーを行き来する大人の仕事と恋愛の物語 『娚の一生』 人生の全てを労働に捧げる 仕事に生きる女のロールモデル 『繕い裁つ人』 女の人生に必要なのは王子様じゃない、家だ 『椿荘101号室』 「仕事/趣味」「仕事/結婚」二者択一の不毛さを描く 『ZUCCA×ZUCA 』 自分の意思ではない境遇も受け入れ 働き生きる日々の愛おしさ 『海街 diary』 夢見た未来と現実の間に苦悩 続いていく労働系女子の人生 『愛すべき娘たち』
-

常識のない喫茶店
¥1,540
SOLD OUT
著者:僕のマリ 出版社:柏書房 176ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「働いている人が嫌な気持ちになる人はお客様ではない」 ――そんな理念が、この店を、わたしを守ってくれた。 失礼な客は容赦なく「出禁」。 女性店員になめた態度をとる客には「塩対応」。 セクハラ、モラハラ、もちろん許しません。 ただ働いているだけなのに、 なぜこんな目にあわなければならないのか。 治外法権、世間のルールなど通用しない 異色の喫茶で繰り広げられる闘いの数々! 狂っているのは店か? 客か? あらゆるサービス業従事者にこの本を捧げます。 喫茶×フェミニズム―― 店員たちの小さな抵抗の日々を描く、 溜飲下がりまくりのお仕事エッセイ! *********************** 店主コメント *********************** サービス業経験者として深く共感できるエッセイ。 本書の内容は、ストレス発散の側面だけでなくサービス業のあり方を改めて考えるきっかけにもなるかもしれません。 現場で働く人だけではなく、普段は現場に立つ機会が少ないポジションの方々にも読んでほしいです!
-

コシラエルとはなんだったのか
¥3,080
SOLD OUT
著者:ひがしちか 加藤さえ子(株式会社ウェルカム) 伊藤ガビン(編集者) 矢沢路恵(山食堂 女将) 星佳奈(内装設計) 今村真紀(アコテ店主) 森岡督行(森岡書店店主) 塩川いづみ(イラス トレーター) 小林紀子(watari 店主) 前田ひさえ(イラストレーター) 山口妙佳 発行元:HeHe 126ページ 182mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 2010年、日傘作家ひがしちかによる、一点ものの日傘作りからスタートした「Coci la elle(コシラエル)」。 手描きの日傘や、刺繍した日傘、デコラティブな日傘など、唯一無二の日傘のほか、雨傘、晴雨兼用、小物などを製作。2022年の夏に閉業。 本書は、2022年9月に本店跡地にて開催された展覧会「傘の素(もと)」にあわせて制作された冊子です。 日傘屋にたどり着くまでのエッセイ、コシラエルの傘に秘められた見えないアレコレ(奥や裏側)をふんだんなテキストでまとめました。 コシラエルに縁があるさまざまな書き手によるコラムも収録。
-

底にタッチするまでが私の時間
¥1,760
SOLD OUT
編者:木村衣有子 発行元:木村半次郎商店 136ページ 188mm × 130mm 雁垂れ製本 新宿の大衆喫茶食堂ベルク。 コーヒーやホットドッグなど、こだわりのメニューを良心的な価格で提供しているお店です。 同店が発行するフリーペーパー「ベルク通信」の創刊号から150号まで、その中から印象に残る文章や心に刺さる言葉を集めたリトルプレス。 「コスパの良さ」だけでは片づけられない同店のこだわりと意気込みが伝わってきます。 その精神性は読者の生活や仕事のスタイルにも良い刺激となるのではないでしょうか。 編者の木村衣有子さんは、食文化や書評を中心に執筆されている文筆家。 本書は木村さん個人の出版レーベル「木村半次郎商店」から発行されたリトルプレスです。
-

喫茶店のディスクール
¥1,870
SOLD OUT
著者:オオヤミノル 発行元:誠光社 143ページ 180mm × 131mm 仮フランス装 *********************** 帯文より *********************** われわれは一体誰と契約をしているのか? SNSとグルメサイト、クラウンドファンディングとポイントカードに骨抜きにされた消費者万能の暗黒時代に模索する「いい店」の条件。自身の迷走を振り返りつつ、犬の目線で語る、経済、仕事、メディアにコミュニティ。金言だらけの与太話再び。 【目次】 第一考 職業意識の変化 第二考 資金の調達について 第三考 ローカルであることの必然性 第四考 いいやつで行こう 第五考 共有財産の私物化と、権威主義の横行 第六考 作り手ではなく飲み手、もらい手ではなく 出した側 あとがき *********************** 店主コメント *********************** いい店の条件ってなんだろうか? 焙煎家の著者が説く小商い論。 現代人の営みに「最悪の景色」を見る著者の言葉は辛辣。しかし、豊富な見識から放たれる金言に思わず納得してしまいます。 消費者という立場で読んでみても「良い店」について考えるキッカケになるのではないでしょうか。 お店の運営方法に正解などありませんが、主流に対するオルタナティブな考え方のひとつとして、この本の内容はとても刺激的です。ぜひ!
-

文にあたる
¥1,760
著者:牟田郁子 発行元:亜紀書房 256ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 《本を愛するすべての人へ》 人気校正者が、書物への止まらない想い、言葉との向き合い方、仕事に取り組む意識について——思いのたけを綴った初めての本。 -------------------------------------- 〈本を読む仕事〉という天職に出会って10年と少し。 無類の本読みでもある校正者・牟田都子は、今日も校正ゲラをくり返し読み込み、書店や図書館をぐるぐる巡り、丹念に資料と向き合う。 1冊の本ができあがるまでに大きな役割を担う校正・校閲の仕事とは? 知られざる校正者の本の読み方、つきあい方。 -------------------------------------- 「校正者にとっては百冊のうちの一冊でも、読者にとっては人生で唯一の一冊になるかもしれない。誰かにとっては無数の本の中の一冊に過ぎないとしても、べつの誰かにとっては、かけがえのない一冊なのだ。」 *********************** 店主コメント *********************** 印刷物の誤字脱字のチェックや記述内容の事実確認などを行う校正の仕事は、やはり一筋縄ではいかない。 一見誤植のようでも作者の意図が隠れていたり、時代によって認識が異なったり。 校正にまつわる様々なエピソードはその奥深さを伝えてくれます。
-

本屋で待つ
¥1,760
著者:佐藤友則/島田潤一郎 発行元:夏葉社 208ページ 180mm × 120mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 広島県庄原市にある書店「ウィー東城店」。店長の佐藤友則さんは赤字続きだったこの店を、「お客さんの要望にこたえる」という姿勢を徹底して貫くことで、黒字化させます。こわれた電気機器の相談や、年賀状の宛名書き。山間の田舎の書店に望まれることの多くは、高齢者たちの生活の相談にのることでした。それだけでなく、店は美容院を併設し、エステルームをつくり、コインランドリーをもつくります。 本書はそうした「書店の複合化」の物語である一方、引きこもっていた若者たちが書店をとおして成長していく物語でもあります。ある日、「学校に行けなくなった子どもを働かせてほしい」と相談され、それからウィー東城店にはそうした若者たちが次々とやってきて、レジを担当し、棚を担当します。彼らはお客さんと接し、本と接することで次第に快復し、何人かは社員となり、そのうちのひとりは佐藤友則さんの次の店長となって、店を支えます。 装画、挿絵は『急がなくてもよいことを』で注目を浴びる漫画家、ひうち棚さん。 本屋の可能性を伝える、感動的な一冊です。 *********************** 店主コメント *********************** 「タイパ」という言葉が生まれてしまうほど、現代人は短時間で成果を求めがち。 そして、企業は即戦力となる人材を欲する。 そんな世の中にあって、広島県の書店「ウィー東城店」は地道な行動を積み重ねながら、信頼の獲得や人の成長を「待つ」。経営難だった書店の立て直し、そして、アルバイトとして働く若者たちの成長の道のりが綴られた物語です。
-

いいお店のつくり方 保存版
¥2,200
SOLD OUT
発行元:インセクツ 496ページ 188mm × 128mm ソフトカバー ******************** 出版社紹介文より ******************** ふだん何気なく「あそこ、いいお店だから」と口にするけれど、 あらためて、いいお店って?って聞かれたら、なんて答える? そもそも、いいお店の“いい”ってなんだろう。 大阪に拠点を構え、地域としてのローカリティだけでなく、感性や共感といった同時代性的ローカリティを軸とした、雑誌「IN/SECTS」。 Vol.6.5(2016年刊)とVol.9(2017年刊)では「いいお店のつくり方」と題して、編集部それぞれがオンリーワンの“いい”と考えるお店を紹介してきました。それは、立ち飲み屋、書店、フランス漁師店、レコードショップ、銭湯など…多岐にわたるお店の、開店までの経緯や店主の秘めたる思いに迫る“いい”をひもとく試みでした。 本書では、そんなVol6.5とVol.9に収録した約6年前の記事とともに、コロナ禍を経た2022年、どのような考え方のもとお店を続けているのか、改めて取材を敢行。当時それぞれの店主が描いていた“いい”は変わったのか、道半ばなのか? それとも以前と変わらぬ思いで働いているのか。 17店のオンリーワンな道のりを、お楽しみください。 【目次】 <いいお店のつくり方 取材先 一覧> 1 アノニム(フランス料理店) 2 井倉木材(立ち飲み屋) 3 サウナの梅湯(銭湯) 4 スペース・オー(オルタナティブ・スペース) 5 誠光社(書店) 6 ビヨンドコーヒーロースターズ(珈琲焙煎所) 7 ホラオーディオ(オーディオメーカー/スペース) 8 ミズタマ舎(器と生活雑貨) 9 メディテーションズ(レコードショップ) 10 スジャータ/豆醍珈琲(コーヒーとお酒) 11 LVDB BOOKS(新刊古書店) 12 アニエルドール(フランス料理店) 13 VOU(雑貨、ギャラリースペース) 14 酒菜の大きに/オキニコウ(立ち飲み屋) 15 IMA:ZINE(アパレルショップ/ギャラリー/編集業) 16 VINYL7 RECORDS(中古レコードショップ) 17 タビコーヒーロースター(焙煎所・コーヒースタンド) 特別寄稿 井川なおこ/吉本ばなな
-

生きる はたらく つくる
¥1,540
SOLD OUT
著者:皆川明 発行元:つるとはな 256ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 魚市場でアルバイトをしながら、たったひとりで始めたブランド「ミナ ペルホネン」。創業25周年を迎えて初めて明かす、これまでの人生と、はたらくことの哲学。 手描きの図案によるオリジナルのテキスタイル、流行に左右されない息の長いデザイン、生地をつくり、服を縫製する工場との二人三脚のものづくりの姿勢など、独自の哲学と方法により、比類のない服づくりをつづけているブランドは、いかにしてつくられていったのか。 幼い頃に両親が離婚。小学校時代はスポーツに夢中になり、中学高校時代は陸上選手を目指したものの、大きな怪我を負い、断念。目標を失い、ヨーロッパを旅行するなかで、偶然、ファッションの世界に出会う。やがて、人の仕事を手伝いながら、はたらくこと、つくることの価値を発見してゆく。 しかし、自分のブランドをスタートした当初は、とてもそれだけでは食べてはいけなかった。白金台に初めての直営店をスタートさせたとき、預金通帳の残高は五万円、しかも金融公庫からの借金は五百万円、という「崖っぷち」の状態だった。それでもなお、前を向くことを諦めなかったのはなぜか。 生きづらさ、未来への不安を覚える世代に、また、経済的にままならない状況におかれている多くの方々にも、ヒントとなることばが、考え方が、見つかるはずの一冊。
-

観察の練習
¥1,760
SOLD OUT
著者:菅 俊一 発行元:NUMABOOKS 256ページ 148mm × 105mm ハードカバー ************************ 出版社紹介文より ************************ 駅やオフィス、街や家の中で出くわす、小さな違和感。あるいは、市井の人々が生み出すささやかな工夫や発明のようなもの。著者が日々収集し続けている数多の「観察」の事例を読み解く思考の追体験をしていくことで、読み手にもアイデアの種を与えてくれる。 過去の膨大な量のリサーチの中から50あまりの「観察」の成果を厳選し、テキストはまるごと書き下ろし。著者のこれまでの人気連載コラム「AA'=BB'」(modernfart)、「まなざし」(DOTPLACE)を愛読していた方も必読の、初の単著にして決定版的な一冊。 【目次】 はじめに/この本の読み方 第1章「痕跡から推測する」 1‐1 平らに見える歩道の正体 1‐2 無意識に取る最短経路 1‐3 整列されたゴミ 1‐4 箱の中の記録 1‐5 最低価格の掘り出し物 1‐6 自力で動きを予測する 1‐7 現場検証の限界 第2章「先入観による支配に気づく」 2‐1 見慣れた組み合わせ 2‐2 ソースの描く軌跡 2‐3 最短ルートは店の中 2‐4 胃内皮、腸フ、科科科 2‐5 泡立たない洗剤 2‐6 無表情なボタンが生む不安 2‐7 デフォルトの逆転 第3章「新しい指標で判断する」 3‐1 センサーに反応させるための指 3‐2 おいしさの定義 3‐3 音による手がかり 3‐4 単位が変わると見えてくる 3‐5 ◯◯として、見てください 3‐6 システムの裏をかく工夫 3‐7 後付けの目印 第4章「その環境に適応する」 4‐1 薄いゴミ箱の設計理念 4‐2 窓から見えた看板 4‐3 雪国に最適化されたゴミ収集所 4‐4 シャッターの内側は 4‐5 駐輪場の使い方 4‐6 物言うシャツ 4‐7 三つの顔を使い分ける 第5章「世界の中から構造を発見する」 5‐1 一度の操作で二つの機能 5‐2 作り足されたレイヤー 5‐3 「いらっしゃいませ」が含む意味 5‐4 赤青鉛筆の秘密 5‐5 エラーの生まれ方 5‐6 冬の夜のサイレン 5‐7 包み紙によるメッセージ 第6章「理解の速度を推し量る」 6‐1 顔に見えるメールアドレス 6‐2 「普通」が分からなくなるとき 6‐3 お釣りの渡し方 6‐4 「使用禁止」の伝え方 6‐5 白線の中と外 6‐6 とっさに押す方のボタンは 6‐7 誰でも分かるエラーの形 第7章「リアリティのありかを突き止める」 7‐1 生々しさの発生 7‐2 シワの取られた千円札 7‐3 理想の風の姿を見る 7‐4 因果関係をでっち上げるタイミング 7‐5 記憶の糸口 7‐6 風を増幅する装置 7‐7 潜在的にある記憶 第8章「コミュニケーションの帯域を操作する」 8‐1 地下を流れる綺麗な液体 8‐2 新しい注意の作り方 8‐3 騒音をすり抜ける声 8‐4 強引な解釈を要求する矢印たち 8‐5 見慣れた言葉が指し示すもの 8‐6 串焼きメニューのプロトコル 8‐7 先回りして用意された注意 おわりに 初出一覧/著者プロフィール
-

バイトやめる学校
¥1,540
SOLD OUT
著者:山下陽光 発行元:タバブックス 144ページ 173mm × 123mm ソフトカバー ~出版社紹介文より~ 「シリーズ3/4」始動! 3/4くらいの文量、サイズ、重さの本。それぞれのやり方で、余白のある生き方をさがすすべての方へ送る新シリーズです。 「景気がめちゃくちゃわるくて、世の中で起きることの、ほぼ全て悪い方向に向かっている。そんな中で好きなことで暮らしていくのは難しいと思って、やりたくない仕事で働きまくって、たまの休みに好きなことに金を使いまくるのはあまりにも効率が悪すぎる。 心配すんな。 「バイトやめる学校」では、何をどうやれば自分で自活して暮らしていけるのかという理論と実践をギャンギャン紹介していきます。」 ネットで新作を出すたび30分で完売するリメイクファッションブランド「途中でやめる」の山下陽光。高円寺の貧乏人反乱集団「素人の乱」に参画後、長崎、福岡に移住、服を作りながら「バイトやめる学校」を日本全国 各地で開催、一歩踏み出せない人の背中を押し続けています。本書は「資本主義が得意じゃない人」が楽しく生きていくための、独創的かつ実用的な「バイトやめる学校」のテキストです。 【目次】 「バイトやめる学校」とはなにか 1時間目 全員にバイトやめる装置が配られた 2時間目 実録・「途中でやめる」 3時間目 1対1の時代になった 実践編 バイトやめた/やめるかもな人との対話
-

大坊珈琲店のマニュアル
¥3,080
SOLD OUT
著者:大坊 勝次 発行元:誠文堂新光社 256ページ 208mm × 128mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** コーヒー好きに愛されながら、2013年に閉店した大坊珈琲店 38年間の営みを振り返り、店主が綴った大切なこと 2013年の12月に閉店するまでの38年間、自家焙煎とネルドリップというスタイルを変えずに、一杯ずつ丁寧にコーヒーを作り続けた「大坊珈琲店」。 閉店から5年という月日が経ってもなお惜しむ声が絶えず、伝説の珈琲店としてその存在感は増している。 本書は店主の大坊勝次が大坊珈琲店での日々を振り返り、心掛けていたことをまとめたエッセイ集。 前半にはコーヒーやお店に対する考え方が、後半には大坊が好んで使っていた器や店内に掛けていた絵の作家について、独自の視点で綴られている。 青山という場所柄、年齢も職種もさまざまな人々が通った大坊珈琲店が、一時の憩いの場所として、なぜそんなにも愛されたのか? 本書に綴られた大坊の思いや感性から、その理由を探ってほしい。 【目次】 閉店 焙煎・抽出・テイスティング 珈琲屋になるまで 心掛けていたこと キムホノ陶 私の平野遼 塩貞夫の鎮魂